場長室より(風景とひとこと)
道総研上川農業試験場のサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。
このページ「場長室」では、上川農業試験場の近況や作業風景、催しもののお知らせ、お知らせすることがないときは場長のたわいないひとりごとを記載いたします。お目汚しの写真とつたない文章ではありますが、もしお時間が許しましたら、ときどきこのページにもお付き合いいただけますと幸いです。
2026.2.19 気になる新技術2026
今年、新たに普及に移すこととなった新品種・新技術が、道総研農業研究本部のサイト(農業技術広場>研究成果一覧>一般課題R8)に公開されました。
前回の新品種に続いて、私が特にご紹介したいと思っている新しい技術をかいつまんでご紹介します(選定は私の独断にて失礼します)。
○畑作物のリン酸施肥に関する新技術(加工用ばれいしょ、直播てんさい、春まき小麦、たまねぎ)
今年の新技術で、特に丁寧な説明をしていきたいと考えている成果のひとつです。
土の健康診断(土壌分析)を行った上で、土に含まれるリン酸量に応じて肥料を調節できます。もっと端的に言うと、リン酸の施肥量を減らしましょう、という提案です。
リン酸は作物の生長に欠かせない成分で「肥料の三要素」としても知られています。特に火山性土壌や低温の影響を受けやすい地域では、リン酸を肥料としてしっかり与えることで作物生産が安定するようになった経緯があります。
現在では、生産現場で長年取り組まれてきた土づくりの成果として、リン酸肥沃度が十分高まってきているほ場が多いことが分かってきています(R7指導参考事項)。リン酸は土から比較的流亡しにくい“蓄えられる”養分ですので、長年の貯金がしっかり貯まっている状態といってよいでしょう。この試験では、肥沃度が十分に高いほ場では、土のリン酸量に応じて肥料を減らしても収量はほとんど低下しないことが明らかとなりました。近年の肥料価格高騰への対応や、環境への負荷軽減という視点でも、大事な視点となります。
なお、作物によってリン酸の必要量は異なるため、作物ごとに確認を行っています。今回の新技術は、数種類の畑作物に限っての成果であることを、ご理解ください。
水稲についても鋭意取り組みを進めていることを申し添えます。来年のこの時期にご報告できるよう取りすすめて参ります。

肥料を減らすことは、生産者にとって勇気の要ることです。作物栽培は1年に1回です。その年の収穫量が激減するような失敗をするくらいだったら、最初から心配のない量を与えたい、という気持ちは容易に想像できます。十分な情報がなければ、たぶん私もそうします。
この試験では、いくつもの条件の違う畑で気象条件が変動する数年間の試験を繰り返し、実際にほ場で得られたデータを基礎的な知見や理論とも照らし合わせ、これで問題なくいける、という段階まで試験担当者達が検討を行ってきました。
土壌診断を行っていただくことが前提ですが、経営的なメリットは小さくないと思いますので、生産現場で取り入れていただきたい技術のひとつです。
上川農試の発表会(2/25)では、国内外の土壌肥料学会でも活躍する、畑作土壌の専門家がご説明します。ちょっと見た目がワイルドな、中身は気の良いオジさんです。

○かぼちゃに関する新技術(成績概要書)
「成績概要書」は他の成果と同じページ数(2ページ)ですが、中身は盛りだくさんで、省力栽培に適した多収品種の選定、施肥技術、収穫後の乾燥技術、貯蔵技術と4つの成果が含まれています。
このうち、収穫後の乾燥技術は、「つる枯病」の対策として効果的な技術です。さらにもっと踏み込んで、従来行われてきたキュアリング(収穫後の乾燥)作業は不要、という実に大胆な提案がなされています。
この乾燥技術は、上川農試でつる枯病の対策試験(H30指導参考事項)を行った病理担当研究員が、中央農試へ異動した後も継続して取り組んできた試験の成果です。病気の対策は薬剤防除と考えてしまいがちですが、つる枯病対策は薬剤防除だけで不十分で、収穫後の乾燥技術が重要であることを明らかにしました。病理学をベースとしながら、専門分野の枠を超えた試験を組み生産現場で具体的に活用出来る技術提案に至ったという意味で、私としては非常に農業試験場らしい実直な取組だとちょっと感動しています(本人の前では言いにくいのでここでコソッと)。
上川農試の発表会(2/25)では、上記担当者が中央農試から駆けつけてくれる予定です。私も話を聞けるのが楽しみです。
○花き(アルストロメリア)ハウス栽培の環境制御技術(成績概要書)
収益性の改善効果が大きい環境制御技術です。花き栽培はもともと収益性の高さが魅力でしたが、資材高騰に伴う収益低下が大きな課題でした。この成果では、温度や二酸化炭素を自動制御することで、植物へのストレスを減らしのびのび育てられ、収穫量=収益性がしっかり向上することが示されています。これら技術のベースには光合成の基礎研究が活かされています。上川農試もこの試験に共同参加しており、温度制御プログラム(気象ノード)の作成を担当しました。
上川農試の発表会(2/25)では、園芸専門のベテランがご説明します。農試内でも、園芸作物のことならまずこの人に相談すれば間違いないという、知識と経験が豊富な研究員です。私も頼りにしています。
○令和8年度特に注意すべき病害虫(成績概要書)
全道の農業試験場や普及センターが連携して行っている「病害虫発生予察調査」を元に、令和7年の病害虫発生を振り返りながら、新たに発見された病害や最近増えてきている害虫など、次年度の作物栽培に向けた注意情報を整理して、毎年この時期に「新技術」の一部として報告しています。
ここ数年の状況として、発生する害虫の種類が変化したり、発生時期が早まったり、発生サイクルが増えるなどの傾向があるようです。おそらく気温が高い影響と思われます。これまでと同じ時期に同じ防除をする、という考え方では対応しきれない可能性があることを痛感させられます。
上川農試の発表会(2/25)では、気鋭の害虫担当がご説明します。好きな虫はアブラムシです。

新技術の概要を読みながら、あらためて農業試験場の役割を確認しています。農業を取り巻く条件がおおきく変わっていく中で、品種も栽培技術も対応していかなければなりません。生産者の段階で大きな失敗が生じないよう、将来の課題を見越した品種の開発や、ここまでやったら良い悪いここまでなら大丈夫という技術の目安を示すことは、農業試験場の大きな役割だと思っています。
また、先んじた取り組みを行うのは、実際にはチャレンジ精神の高い生産者の方である場合が多いです(「試験場発」と言えると格好良いですがほとんどの場合その「芽」は現場から生まれたものです)。そういった生産現場にある「技術の芽」を、しっかりしたデータと客観的な理論で裏付けした上で、誰でも取り組むことのできる技術として磨き上げることも、公的機関の重要な役割だと感じています。
普及に移される新技術の一覧は、こちらのページをご覧ください。
新しい品種と技術について、全道及び各地域農試で「新技術発表会」を開催し、試験担当者本人から概要説明を行う機会を設けています。ご都合がよろしければ、お近くの会場へお越しいただけますと幸いです。
開催情報
| 地域(専門) | 主催 | 開催日 | 場所 | 案内リンク・申込など |
|---|---|---|---|---|
| 全道(全分野) | 道農政部・道総研農業研究本部 | 2月20日(金) | 札幌市(会場のみ) | HPから事前申込2/13まで |
| 道北地域 | 上川農試 | 2月25日(水) | 比布町(会場のみ) | 事前申込あり(当日受付でもご参加いただけます) |
| 道央地域 | 中央農試 | 2月27日(金) | 江別市(会場のみ) | 詳しくはこちら |
| 道南地域 | 道南農試 | 2月27日(金) | 北斗市(会場・Zoom併用) | |
| 十勝地域 | 十勝農試 | 2月25日(水) | 幕別町(会場のみ) | 事前申し込みあり |
| オホーツク地域 | 北見農試 | 2月25日(水) | 北見市端野町(会場のみ) | 事前申し込み(当日受付でもご参加いただけます) |
| 畜産分野 | 畜試・十勝農協連・NPO法人グリーンテクノバンク | 2月27日(金) | 帯広市(会場のみ) | 事前申し込みが必要です |
| 花野菜分野 | 花野菜技術センター | 2月24日(火) | オンライン(Zoom) | 農業関係者を対象(上限200名)・HPより参加登録 |

発表会の場で、ご来場いただいた方とお話しできることも、たいへんありがたく嬉しいことと感じています。
気になる技術がありましたら、どんなご意見・疑問でも、雑談でも結構ですので、お近くの研究員にお声がけください。一見無表情な研究員が、内心すごい喜びを感じながら、持っている知識と経験を精いっぱいお伝えいたします。
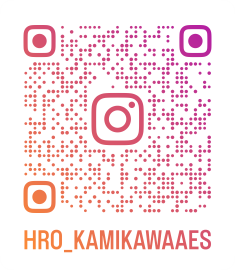
過去記事はこちら | 上川農試ホームに戻る
