試験研究は今 No.3「ラーバとは何ですか。また、ラーバ調査はどうして必要なのか」(1989年9月8日)
Q&A ラーバとは何ですか。また、ラーバ調査はどうして必要なのですか。
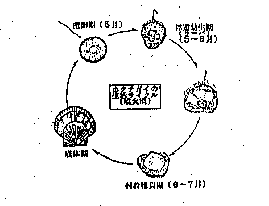
この浮遊幼生の時期や底生生活に移行する段階までは、稚仔の減耗が非常に大きく、例えばホタテガイの場合は1個体から1億粒以上の卵を産出しますが、底生生活するまでの間にほとんどが死んでしまいます。こうした減耗を低く抑えるため、天然採苗で採捕された稚貝は、中間育成に移されることになります。
天然採苗は、ラーバの浮遊生活から底生生活に移行する過程をうまく利用したものです。しかし、この底生生活に移行する時期や場所を的確に把握し選定することは難しく、このため水試や指導所では水温や潮流、ブランクトンネットを用いてのラーバの出現状況調査をしています。このような調査から採苗器の投入時期や場所が選定されるわけです。
こうした浮遊幼生の分布や動態の調査は多くの地区で実施されています。中でも網走水試では、ホタテガイの天然採苗の安定化を図るため、水試と留萌、網走、根室管内の指導所、漁協とを結ぶパソコンネットワークによって、浮遊幼生の分布や動態調査、採苗に関する情報を広域的、かつ迅速に伝える連絡網を作っています。
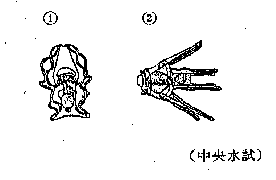
トピックス
「日高地域ミニ試験研究プラザ開催」
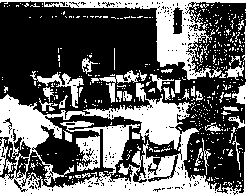
地元の水産加工でかかえている問題点、サケ筋子の品質改善、地元資源の有効利用、水産廃棄物の利用や処理等について活発な意見交換がされました。
(函館水試)
「移動加工相談室」開催のお知らせ~ご案内
「移動加工相談室」が、9月11日(月曜日)午後3時から小樽市職員会館で、また、9月14日(木曜日)午後1時30分からは岩内町水産研修センターで開催されます。
この移動相談室は、市町村の協力を得て、グルメ時代にマッチした、新たな水産加工食品の開発や加工技術の向上に役立てようと毎年開催されていますが、今回は特別講演として「クリーンルームの構造と機能」「工場の衛生管理」についての話題も予定しております。お気軽にご参加ください。
(中央水試)
この移動相談室は、市町村の協力を得て、グルメ時代にマッチした、新たな水産加工食品の開発や加工技術の向上に役立てようと毎年開催されていますが、今回は特別講演として「クリーンルームの構造と機能」「工場の衛生管理」についての話題も予定しております。お気軽にご参加ください。
(中央水試)
「スケトウダラ、ホッケ資源研究グループ会議の開催」
7月25日、26日の両日、稚内水産試験場こおいて、スケトケダラ及びホッケ資源に関するグループ会議が開かれました。この会議は、北海道全域に分布するスケトウダラ、ホッケの資源動向や生態などの情報交換を行うため開催されているもので、海域別漁況のデータなどを持ち寄って活発な意見交換が行われました。来年は網走水試で開催の予定。
(稚内水試)
(稚内水試)
「中国人研修生受け入れ」
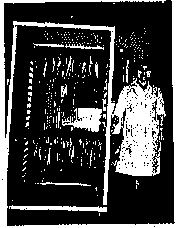
(函館水試)
クイズの答え
【答え】(1)マナマコ、(2)エゾバフンウニ
