試験研究は今 No.11「アワビの漂流効果について」(1989年11月17日)
ページ内目次
Q&A アワビの放流効果について教えて下さい。
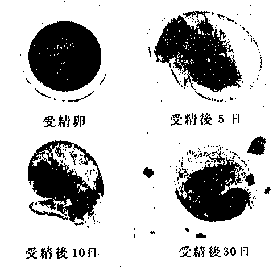
先ず、種苗放流コストより水揚げ高を多くするための考え方についてですが、それには人工種苗の単価を安くし販売単価を高くしたり、放流したものをより多く採る必要があります。
アワビの場合、人工種苗をつくる方法は10年以上にわたって改善の努力がされてきましたが、北海道は本州に比べて水温が低いため、どうしてもコストが高くなります。また、アワビの販売単価は他の魚貝類に比べてはるかに高いのですが、東北各県に比べると成長が遅いため、放流後の同じ年令で見ると本州の方が単価が高くなります。ちなみに成長ぶりを比較すると、北海道では放流して3年目で75~80ミリメートルになりますが、岩手県では同じ年令で95ミリメートル前後、重さでは1.5倍になります。
こうしたことから、現在の北海道の種苗価格や販売価格から考えると、放流した種苗のうち20~25パーセント以上を漁獲しないと、放流した効果があったことにな.りません。この放流した種苗がどれくらい漁獲されたかの調査は全国的にも少なく残念ながら20パーセントを越える例は多くありません。しかし、最近では、道南で40パーセント以上、秋田県でも30パーセント以上の漁獲が記録されています。
こうした放流種苗の漁獲率を高めるためには放流種苗の生残率を引き上げることが何より基本となりますが、このため水試では、放流技術の改良試験を行っています。大成町地先海面では放流初期における人工種苗の減耗率の把握と放流後の保護施設の設備改良、また、知内町地先海面ではカニ類の食害が予想以上に多いことから食害の影響とその防除方法の調査です。そのうち、大成町における人工種苗の馴致効果確認調査からは中間報告の段階ですが、約1ヶ月間、馴致施設に入れたアワビ種苗の施設内での減耗がほとんどなく、その後の生残率調査でも馴致した方が馴致しないものより発見率が高いことが分かり馴致効果が充分あることなどが判明しています。
次に種苗放流によって前浜の資源が増えたかどうかについてですが、漁場での天然種苗と人工種苗の割合をみると、水産技術普及指導所の中間報告(右表)では、人工種苗の割合が非常に高くなっています。
これは前浜の天然アワビ資源が少なくなったためと言えま.すが、前浜の資源を支えているのは今や人工種苗であるとも言うことができるかと思います。
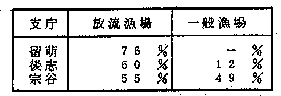
(函館水試)
トピックス
中国農業部余大奴水産司長(MR,She Da Nu)一行函館水産試験場を視察

函館水試では川村場長が北海道の水産業の現状、北海道のウニの増養殖の事例、取り組みについて説明。また、増殖部水島魚貝科長からは噴火湾におけるホタテガイ養殖業の状況を説明しました。
中国では養殖ホタテガイの生産が100トン台になったことから、ホタテガイ養殖の今後の在り方について検討しており、日本のホタテガイ養殖の生産が多い噴火湾の現状について注目していました。特に天然採苗、本養成の技術、採算性等についてに質問が集中し、試験研究を通じて日中友好の輪が広がりました。
貝毒モニタリング調査結果まとまる
噴火湾で昨年発生した貝毒(麻ひ性)の原因プランクトンは、本年は、既に見られなくなっています。しかし、例年に比べて、毒性値が高かったこと、現在でも100~200MUの毒性値が見られることなどから、出荷自主規制の解除はやや遅れるものと考えられます。
