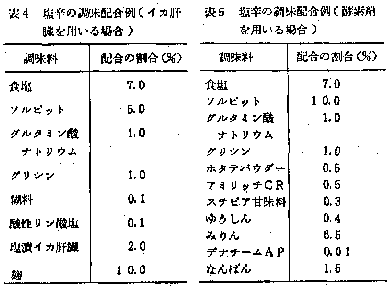試験研究は今 No.33「 ホタテガイ外套膜を原料とする加工品について」(1990年6月8日)
Q&A? ホタテ貝外套膜を原料とする加工品について教えてください。
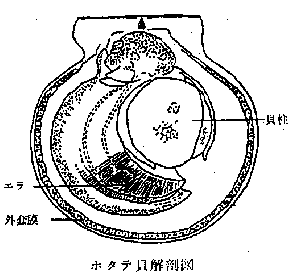
全国のホタテ貝生産量は昭和63年度で32万トン(北海道では25万3千トン)に達しますが、ホタテ貝外套膜の歩留まりは時期と貝年令によって7.5~10パーセントと変化するので、仮に歩留まりを8パーセントとすると、全国のホタテ貝外套膜の生産量は2万5千6百トンになります。
しかし、生貝やボイル製品など外套膜が付いたものや廃棄されているものもありますので、これらを考慮しますと、3~4割程度が加工原料として利用可能な数量と思われます。
このホタテ外套膜は、昭和40年代後半まではホタテ貝の生産量が少ないこともあり乾ミミとして販売され、佃煮用、あるいは家庭の漬物用材料として利用されていましたが、昭和50年代に至って生産量の増大にともない、ホタテ外套膜も大量に産出されるようになりました。
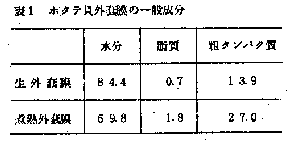
ミミの調味乾品
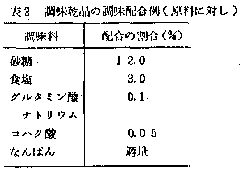
また外套膜の端を重ね合わせ続けて乾燥させますと、乾ノリ状のものができます。乾燥時間は晴天の天日乾燥で約半日です。干し上がり製品はゼラチン様の透明感がある棒状のもので、スルメの足に似た歯ざわりがあります。
のしミミ
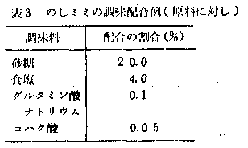
塩辛
原料は生外套膜と乾燥外套膜を用いる方法があり、乾燥外套膜は水温5度の止水に24時間ひたしてから用います。いずれも黒膜を除去したものを長さ約3センチメートルに切断し漬け込みますが、イカ肝臓を使用した調味配合例を表4に、酵素製剤を使用した調味配合例を表5に示しました。生外套膜と乾燥外套膜とでは、乾燥外套膜の方が特有の生臭みが少なく、また、イカ肝臓と酵素製剤とでは、イカ肝臓の方が熟成は早くなりますが、イカ肝臓臭がします。
以上、最近の加工技術から数点について、紹介しました。ホタテ貝外套膜を用いる加工品種は少なく、その利用の拡大が望まれていますが、最近ではシーフード・サラダ向けとした商品も市販されているようです。
以上、最近の加工技術から数点について、紹介しました。ホタテ貝外套膜を用いる加工品種は少なく、その利用の拡大が望まれていますが、最近ではシーフード・サラダ向けとした商品も市販されているようです。
(網走水試)