 |
海域堆積物(5パターン)
海域堆積物は,常時,海水で満たされている領域で形成された堆積物である.この領域で形成された堆積物から試料を採取することは困難であるため,地質学的証拠から過去に海域で形成したと考えられる堆積岩を対象に検討した.
海域堆積物は,波浪の影響を強く受ける領域の砂質堆積物と波浪の影響が小さい,もしくは,影響力が無い領域の泥質堆積物に大きく区分される.後者は,砒素・セレンが溶出基準値を超過する事例が多く知られている.対して前者は,多くの場合において溶出量および含有量基準値を超過することは稀である.
|
 |
沿岸域堆積物(7パターン)
沿岸域堆積物は,陸域でありながら常時もしくは一時的に海水の影響を受ける領域で形成された堆積物である.本報告書では,標高が20m以下となる地域に分布する堆積物を一括して沿岸域堆積物とした.この「沿岸域堆積物」には,過去に沿岸域で形成した後に地下に埋没した堆積岩も含まれる.
陸域にありながらも常時海水の影響を受けている汽水湖や塩性湿地,高潮や高波などが一時的に侵入する領域,淡水と塩水の密度差により河川で形成される塩水くさびが発達する領域などが,この区分に該当する.
|
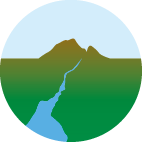 |
内陸域堆積物(9パターン)
内陸域堆積物は,海水の影響を受けない領域で形成された堆積物である.本報告書では,標高が20m以上となる地域に分布する堆積物を一括して「内陸域堆積物」とした.この「内陸域堆積物」には,過去に陸域で形成した後に地下に埋没した陸成堆積物も含む.
標高20m以上であっても,実際には堆積物に含まれる有害物質の溶出/含有特性には海水の影響が現れる可能性もあることに留意されたい.
|
 |
火山砕屑物(9パターン)
火山砕屑物は,地下深部から上昇してきた高温マグマが,地表へ噴出,もしくは地下に貫入してできた地質体である.この区分である火山砕屑物には,地質時代を通じて起こったマグマ活動の産物も含まれる.
火山砕屑物のみの場合,自然由来有害物質が土壌汚染対策法の基準値を超過することは稀である.しかし,マグマリスクの高い変質帯を形成する熱源や有害物質の供給源として重要な役割を担うことも多い.このため火山砕屑物の分布する領域では,後述する変質帯の存在確認もあわせて実施しておくことが望ましい.
|
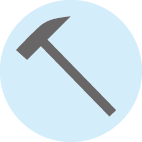 |
変質帯(13パターン)
変質帯は,他の形成環境が主に溶出リスクであるのに対して,いわゆる第2溶出基準値や含有量基準値も超過する可能性を有するリスクが高い領域である.このため,土木工事を行う際には,計画立案以前に予定工事区域内に存在する変質帯の領域を確認することに加えて,変質作用のタイプも事前に把握しておくことが必要である.また,可能ならば,高いリスク領域での工事の実施は避けるべきである.
北海道内には,大小あわせて1,000を優に超える鉱床(経済価値が見込まれた変質帯)が知られている.このような鉱床の下流域の盆地・平野は,有害物質のリスクが高くなっていることも多いので,平野域の工事の場合,あわせて上流域の鉱床についても留意しておくことが望ましい.
|