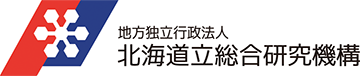A 沿革
I 道南農業の沿革と発展
1 貞応元年(1222)まで
北海道における作物栽培の起源についてはあまり明確にされていない。そもそも、北海道がまだ蝦夷といわれていたころ、その土地の住民はアイヌ人であった。彼らは元来漁猟民族といわれ、漁猟を主とした生活を常としていたが、それだけで十分な生活が出来ない所では極めて原始的な方法ではあるが農耕も営んでおり、粟、ひえ、かぶなどを作っていたという。しかし、大部分の植物性の食物は手をかけずに採集できる自然の野草に頼っていたものと思われ、主食はどこまでも魚と獣肉であり、ほかのものは副食であり、酒の原料であった。栽培していた栗、ひえなども和人が蝦夷に渡る以前から作っていたのか、ひそかに和人から入手して作ったものか、その点はよく知られていない。
北海道と和人との関係は、斎明5年(659)阿部比羅夫が軍船180隻を率いて本道に遠征し、粛慎を討ち郡領を後方羊蹄に置いて帰還したのが始まりとされているが、これは戦いであり本道に住むために来たのではない。その後、大分年代がたった文治5年(1189)源頼朝に敗れた奥州藤原泰衡の残党が逃げ渡って居住したり、建保4年(1216)強盗、海賊の類50余人を蝦夷島に追放し、これらの人は渡(わたり)党と称されていたという記録がある。また、北海道市町村行政区画によれば、文治年間(1186~1189)今の亀田、銭亀沢に和人が住んでいたと記きれているが、これらの人の中には前述の藤原の残党などもいたと考えられ、このほかにも、本州の漂流民が帰ることができなくなって土着したり、漁業のための出稼ぎからついにとどまった人などもあった模様であるが、一般的には漁のための仮の一時的な宿泊の場所であるにすぎず、畑を耕して農業を営むという人はまだいなかった。また、元久2年(1205)とも、もっと後代ともいわれているが、今の知内町で砂金掘りが行われていたときれているが、これも農業ではなかった。
2 安東氏時代(1223~1589)
貞応3年(1223)和人の渡島とともに蝦夷地の認識が高まり、鎌倉幕府は安東尭秀を蝦夷管領に任命し、道南地方は中央行政の支配に属することになった。永仁4年(1296)日蓮上人の高弟日持上人が銭亀沢の石崎に住み4年間布教活動をしていたり、応永年間(1394~1427)には知内での砂金掘りも活発に行われていたし、箱館から貞治6年(1367)に刻んだという板碑が掘り出されているなど、その頃既にかなりの和人が道南地方に住みついていたことを物語っている。その後、嘉吉3年(1443)安藤盛季が津軽から蝦夷島に脱出し、享徳3年(1454)には安藤政李と共に武田信広らが南部から逃れて渡道し、潅峡地帯にとりでを作って居住するようになった。そのとき、宇須岸(現函館)に河野政道が作った館が箱のように見えたので箱館の名が生れている。字須岸の全盛のころは毎年3回づつ若狭から商船が来て、海岸に家を構えていた問屋のたるき柱にともづなを結んだとあり、当時の必需品のほとんどは本州から船で運ばれており、米、味噌、酒、衣類などの記録はあるが野菜については記きれていない。多少一時的な補給程度の長持ちするようなものがあったにしても量は少く、常に要求される新鮮なものはやはり野草に頼ったり、いくらかの土地を耕して自家用程度の野菜を作るとか、あるいは交換するか地元で買入れる方法があったものと思われる。しかし、長禄元年(1457)コシャマインの乱が起り道南地方の和人の中心拠点であった館が陥れられたが、花沢の館に居た武田信広が七重浜でコシャマイン父子を倒し乱は平定したが、その後も度々アイヌの襲撃があり、定住して農業を営むなどという情勢ではなく、ただ難を逃れ転々として居を移す始末であり永正9年(1512)字須岸、志苔、与倉前の箱館近辺の館が攻略されたため箱館は衰微し永正11年(1514)には箱館にくらべて港としては決して良港ではなかったが大館(現松前)に中心が移ってしまった。
「農」という字が記録に現われてくるのは、文明年間(1469-1486)「南部より農民浜道安兵衝、漁民小林権兵衛なるもの農業、漁業の目的にて渡来、湯の尻浜に居を構えた」と「行政区画」にあるが実際農業を行ったかどうかは不明である。「開拓使事業報告」によれば、「永禄5年(1562)畑地開墾を以て北海道の嚆矢とす、すなはち亀田郡亀田村是なり」とあり、亀田村では五穀を作ったというのと野菜を播種すという両様の記録もあり、その細部については不明であるが、いずれにしても北海道の農業の起源と見てよいであろう。しかし、これらも当時の状況地形から見て農業の専業ではなくコンプ採りも兼ねていたものと思われる。松前郡では永禄(1558~1569)以後、皆宅地のそばに野菜を作ったとあり、天正16年(1588)近江国の建部七郎右エ門が野菜種子の行商人となって松前に渡ったともいうが、これはもっと後の時代と推定されている。このように渡道の目的が漁業であっても自家用の野菜はどこでも多かれ少かれ作られており、中にはいくらか大豆、ひえ、栗などの栽培も行っていたようである。
3 松前氏時代(1590~1798)
天正18年(1590)蛎崎慶広は上京して豊臣秀吉に謁し蝦夷島主の待遇を受け、更に蝦夷島管理の制書を得て安東氏に代って全島を支配することになった。後慶長4年(1599)徳川家康に謁し、姓を松前と改めた。武田信広から数えて5代目の藩主である。この時代になると道南各地で大分農業も行われるようになった。元和4年(1618)七重(現七飯)で南部佐伊浦(下北郡佐井村)から移住して釆た修験者が名を平左衛門と改めて初めて農耕に従事しており、同じ年ヤソ会派の神父アンジユリスが、当時知内川上流に砂金採取に来ていたキリシタンの教化と蝦夷地開教を志して松前に来たが、その記録に、耕作されていた食用作物はひえばかりであったと記している。なお、砂金採取の目的で渡航した者は元和5年(1619)5万人、翌年は8万人にも達したとあり、金の輸送と必要物資輸送のため毎年300隻近い船が本州各港から来航していた。慶長8年(1613)松前藩は亀田に番所を設け当時の代官は白鳥氏であった。氏は南部からの出稼ぎ者の一家から1人宛を農事に従事開墾させ、こばむ者は追放したといい、このころから畑作も積極的に進められてきたようである。寛永年間(1624~1643)には兵次郎という者が濁川(現上磯町清川)に畑を開きひえ、莱、きびをまいており、「津軽一統志」によれば、寛文9年(1669)には粟の栽培があったと記されている。元禄4年(1691)には松前藩から亀田奉行に「5才も捨置候畑は新世間の者共にまかせ可申候」との達しが出ており、当時の畑作は一般には夏のコンプ採りの合間の仕事であったり、地方から出て来て季節だけ仕事をし収穫が終われば在所に帰って越年するというのが多く、その耕作方法も勝手に土地を選び草を焼いて開墾し、肥料は施さず草取りもせず土地がやせて収穫が減るとその土地を捨て、更に適地を開墾する荒起(あらき)という焼畑式農法で作り捨てめ農業であった。したがって、農耕は大体副業として営まれ耕地の所有権なども確認されていなかった。しかし、村々の百姓は1人も他村に移らぬようにし後継ぎが絶えぬようにすることも申し渡し農業を支えようと努めている。このころ、亀田附近では亀田川を中心に村が形成され、貞享元年(1684)には神山村で佐々木佐四郎が開墾に従事し、元禄7年(1694)には吉村七兵衛が加わり、元禄12年(1699)には菊谷喜之助が畑5反を耕作するなどこの地方での畑作はかなり進められている。しかし、畑作にとっても蝦夷地の気候は厳しく、元禄8年(1695)には奥羽地方の凶作で移入米が不足して飢饉を招いたが、道南の畑地帯でも種子がとれぬほどの凶作であり、翌年藩では栗、そば、大豆、小豆の種子を南部に求めているがその量から見て畑作はかなり盛んになっていたものと思われる。
馬鈴しよは寛政10年(1798)最上徳内が蝦夷地出張の際虻田附近に耕作させたのが始まりとされているが、それより以前宝永3年(1706)瀬棚場所で高田屋松兵衛という者が馬鈴しよ、だいこんをまいたという記録もある。その他、宝永7年(1710)に書かれた「蝦夷談筆記」の松前の様子の中には粟、ひえ、大豆、小豆、瓜、なす、大角豆(ささげ)の名が、享保2年(1717)に書かれた「松前蝦夷記」には、ごぼう、だいこん、えんどう、きゅうり、麻、多麻粉(たばこ)の名もあり、畑物が土地相応にできるとされており、農業は漁場の背後でも育ちつつあった。当時の馬鈴しよも漁期だけの居住地である「場所」の野菜として作られていた。朝鮮にんじんは薬用として幕府の命により享保20年(1735)には松前で植えられている。
積極的に蝦夷に雑穀を植えさせたのは享保元年(1716)松前家家老蛎崎広武の建議によるもので、それまではアイヌに種子を渡してはならぬとの達しもあった。この奨励も享和2年(1802)に中止されたが、当時の情勢としてはアイヌの耕作が広がると漁猟がおろそかになり交易物資が減りそれが利潤の減少になることをおそれたとの見方もある。ちなみに寛政(1789~1800)のころの交換率は米1俵につき生鮭5束、干鮭干鱈は各7束であり、1束は20尾、米の1俵は8升であった。
農業には最初租税を課せず、享保2年(1717)ころは畑作の最も盛んな亀田村だけ馬糧大豆1軒に付3斗の畑役に限られており、それが60俵程度にすぎなかった。しかし、漸次畑作地帯、畑耕作が増えてきたこともあって、東西村落検分の上穀役が課されるようになったのは享保5年(1720)のことである。後に明和9年(1772)には1反歩90文と定めている。なお、東西というのは松前を中心にしてのことであり、東は木古内、上磯、大野、七重、亀田、箱館方面のことであり、西というのは江差、乙部、太櫓方面のことである。
一方、稲作についてはもともと蝦夷地では米は生産できないとされており、松前藩にしても一般の大名のような石高は与えられておらず、河川の漁業権、アイヌとの交易による利益を俸禄に替えたものであった。したがって、漁業が不漁になると交易物資が少なくなり食料も乏しくなるということになった。また、入船が途絶えると必然的に移入物資、生活必需品が少なくなり飯米にも影響してくるのであるが、その代り漁さえあれば、いかに東北その他の地方が凶作であっても米は移入に頼り切っていたため、他の生産地から移入し、逆に東北などの凶作による難民が、蝦夷地に渡ると食料はある、米が食えるということで続々と渡来する始末で元禄15、16年(17021703)には延人員約5万人に粥を与えて救済したり、天明3、4年(1783、1784)の飢饉の時は道南の天産を頼って津軽から渡来した窮民8百余人、1人宛銭百文米1升を与えて送り返すということもあった。これは、主食を他地方に仰ぐ関係から著しい予想外の人口の増加は藩にとっては必ずしも望ましいことでなかったからである。このような中で最初は沿岸地域だけに在住していた人達も次第に海を離れ木こりや農を求め平地にも住むようになった。藩としても食料の自給については早くから望んでいたが、米作りは畑作と異なり水利を考えねばならず、田地の造成、栽培の技術ということもあり安易に取り組むことができなかった。
本道稲作の起源は、現在大野町文月に北海道水田発祥之地と記念碑が建てられていて元禄5年(1692)と刻まれているが、これより以前寛文年間(1661~1672)に大野文月で藩主の命によって試作したという記録、貞享2年(1685)文月村押上の高田吉右衛門が米作を試みたという記録もある。この時代には各地で新田が試みられ、大野のほかにも亀田村、上磯、江差でも行われた。11代藩主邦広(慶広から数えて7代)は特に墾田に熱心であり、その命によって大野村、福島付でも、また江差でも新田が試みられた。邦広没後も木ノ子村、及部村、福島村と再三稲作が試みられたが成功と失敗の繰返しが続きついに成功するに至らなかった。これは、気候の関係、栽培技術の幼稚なこと、品種のことなどもあるが、米の移入が比較的容易であり、その上、稲作より有利な多くの仕事があり、その時期が農耕期とぶつかるため稲作を定着きせる余地が少なく、したがって余り熱心でなかったということも考えねばならない。稲作の記録の中に元禄11年(1698)佐藤信景が阿寒の山麓で稲を作り成功したというのもあるが、これは一般史家からも架空の説として否定きれている。
この時代の農業事情を当時の記録からうかがってみると、元文4年(1739)の坂倉源次郎の「北海随筆」に「百姓といってもただ鰊をとって十五分の一を納め余分で生活していて、米は出来ないからかえって諸方から入る米が豊富で普段は下銭の者でも麦やかてを食べなかった」と記し、天明3年(1783)の立松東雲の「東遊記」には、江差より3里の「アツサブ」(厚沢部)では畑が主で少しは田も作っているとあり、更に、果物は柿は無し、梨子、栗、李あり。桃、梅も有るが多くはない、柑類は全く無く、この地の人は蜜柑を非常に望むのでよく保つ法を知って送ったならば巨利を得るであろうと述べている。天明4年(1784)の記録「蝦夷地一件」には「土地の様子は稲は寒気強く出来不仕候得共、余国より入込候米夥数、四五月の間諸商人翌年船通路の日間を考へ買込置候間米の儀少も乏敷儀無之云々…共他莱、稗余国より出来方宣敷糞を用ひ不申候て能く実候間に御座候云々」とあり、天明8年(1788)に幕府の巡見使古河古松軒の記した「東進雑記」の中の狂歌に、松前にて悪しきものと題して「雪深く山坂多し波の音、米のなきのと鬼熊はいや」とされており、寛政3年(1791)の最上徳内らの「東蝦夷道中記」には、木古内から年貢栗、大豆計6~7俵とあり、寛政9年(1797)の地誌にも、各地に耗穀あり、とは記されていているが、米の生産についてどこにも記されていない。
4 前幕領時代(1799~1820)
幕府は蝦夷地に外国船が来航するようになったことと松前の藩政が弛緩してきたことから守備強化の必要上、寛政11年(1779)知内以東の太平洋岸地域、すなわち、東蝦夷地を直轄とし、享和2年(1802)には箱館に蝶夷奉行を置き、箱館奉行と改めた。更に、文化4年(1807)には全島を支配直轄することとなり、箱館奉行を改め松前奉行として松前に移し、別に箱館役所を設けて箱館地方と東蝦夷地に関する仕事をさせた。
この時代の農業で特筆されるのは箱館附近の大開発の実績である。寛政12年(1800)幕府は文月、千代田、一本木など大野、上磯の近辺5ケ所で米の試作を行った結果237石の収穫をあげることができた。これが籾であったか玄米であったかはよくわからないが、これだけ大量の米が蝦夷地でとれたということは空前のことであった。しかも、試作は1年で終らず、年々実りよくあり、と記されている。それに自信を得て文化2年(1805)諸国の農業地から希望者を募り、居小屋を建て農具を準備して開墾にとりかかり1年で大野村庚申塚(後の本郷)に90町歩文月付に50町歩の計140町歩の水田と濁川村(現上磯町清川)に15町歩、庚申塚に3町5反歩、文月村に1町5反歩、計20町歩の畑を造成した。初年度のことであり全部の面積で栽培を行うことはできなかったが、12町歩の水田から玄米600俵(4斗入)畑からは大豆550俵(4斗入)の収量をあげ、そのほかの畑作物では、小豆、えごま、ひえ、栗、そば、あさからむし、だいこん、ねぎ、ごぼうをも収穫している。この開墾に要した経費は総額約3万両にも達し、幕府では蝦夷地の農業確立のためにと、前年釧路方面の大漁で得られた1万両の余剰金までこのために注ぎこんでいる。民間でもこれに呼応して59町歩の水田を造成している。しかし、官営は経費が多くかかるため、文化5年(1808)には縮少し、ただ既墾地を維持するにとどめてしまった。文化6年(1809)籍館附近の民営官営併せて水軋ま約300町歩、畑60町歩に達していた。畑作は先にあげたもののほかに、大麦、小麦、なす、きゅうり、七重では幕府の命により朝鮮人参まで栽培し、文化10年(1813)の文書には、だいこん、豆、なすなどは箱館その他へ売り出されたと記きれている。
5 後松前氏時代(1821~1853)
幕府は蝦夷地全島の取締りも整い平棺に向ったので、松前氏の請願もあって文政4年(1821)全島を松前氏に返還した。
幕府直轄時代に開かれた水田は、その後不順な天候に見舞われたため登熱しない年が続いたその上、天保3年(1832)は奥羽地方は飢饉、翌4年(1833)は全国的な凶作となり本道への米の移入は著しく減少し、江差地方でも魚穫が少なかった。更にこの凶作は天保9年(1838)まで続いた。このために折角造成された水田も決定的打撃を被り、壊滅状態となりひえ田に変ってしまった。しかし、畑作は大豆、小豆、栗などは収穫皆無であったにもかかわらず、ひえ、麦は所によって収穫でき、馬鈴しよ、だいこんは平年作であったといわれ、そのために畑の耕作は一応作柄は不良ではあったが漸次増加していった。しかし、このように成功と失敗の繰返しが続けられ、試田、廃絶の運命をたどりながら来た本道の稲作にようやく希望が持たれたのは民間人として自発的に、とれるかどうか確かな保証もないのに、と世間からあざけられながらも嘉永3年(1850)大野村の高田万次郎父子の努力によって24石の収穫をあげ世人の眼をみはらせたことと、安政2年(1855)開びやく以来の豊作と再び幕府による全島直轄に伴う政策の転換であった。 いる。
6 後幕碩時代(1853~1867)
安政元年(1854)神奈川条約で箱館の開港が決まると、蝶夷島を松前小藩に支配させてはおけないとして再び幕府の直轄として箱館奉行所を置いた。
安政3年(1856)には前年の豊作の影響もあり幕府の奨励もあって水田耕作者は急増した。箱館奉行が松前藩から引継いだ箱館地方の水田は116町9反5畝歩で、それまで1反歩租税180文の規定であったが連年不作のため徴収しておらず、畑は54町2反8畝歩で反当り90文の租税であった。この年も豊作であり、同年から3ヶ年、仮に定められた粗米が71石8斗1升6合にもなり、蝶夷地での最初の租米なので翌年縮館奉行は伊勢神宮、宮中、日光東照宮に献ずるためこれを江戸に送った。
この時の箱館奉行は開墾興産を重んずる拓殖方針を打ち出し、開拓者誘致の方策と御手作場と称する半官半民経営の営農方式を実行するとともに勧農係を設け農事指導をも行った。
開拓者誘致の方策として、安政2年(1855)幕府は旗本500石以下の者に蝶夷地在住、妻子同伴を許した。これにより、翌安政3年(1856)と安政5年(1858)の2回にわたって八王子千人同心計40名が七重に移住した。八王子千人同心というのは、徳川時代八王子附近にあった豪族が徳川氏の指揮下に入り、その一族千人で組織され、江戸城の警固、日光東照宮の警備と甲州地方緩急の場合の押えとなる役割を果していて、幕府から禄を貰い、用務のほかは在郷にあって百姓の仕事もしていたので、開拓と警備にはうってつけの人達であった。この千人同心は、先に寛政12年(1800)白糠と勇払に50人宛入植したが、気候風土になれず、病死者が続出しこの計画は失敗に終っている。七重に着いた一行は、河津三郎太郎が安政4年(1857)に開いた七重薬園附近などに農地を得て家屋を建設し農業に従事した。彼らによって七重附近の開拓が安定したころ、箱館戦争となり敵味方と分れて戦う場面もあったが、戦争柊了後戦った人達の幾人かは七重官園の職員として活躍し、他の人達もそれぞれの村で努力を続けた。
七重薬園の当初の目的は松や杉などの苗木の育成と、幕府の用いる薬用植物の栽培であったが、千人同心が入植してからは、この薬園の管理と千人同心の指揮をあわせて行っていた農業指導者栗本鋤雲は、北地農業の適作物の発見と農家副業としての桑、楮(こうぞ)などを植え、機織や製紙などを行うことも計画した。
この、桑、楮の栽植には千人同心世話役の秋山幸太郎がよく働き、桑の成功は養蚕に結びついていった。
庵原薔斉が安政2年(1855)から箱館近郊の亀尾、湯の川で稲作を始めていたが、その成績が良かったので幕府は官営の御手作場とし、かつ村々の勧農方をも担当させることにした。この御手作場というのは官費経営の耕作地であり、1戸1町5反歩を与え、初年度に畑3反歩、田5反歩を造成する義務があり、そのための経費5両が与えられ、ほかに馬の購入費3両、家屋の分35両、農具費10両、旅費、種子が支給きれ、更に自給できるまでとして3年間成人1日分食費25文が与えられるという募集移民に対する保護政策であった。しかし、援助が打切られると止める者が多く、一部勤勉な農民だけが残留するという結果になった。文久2年(1862)には箱館附近に11ケ所、長万部附近に4ヶ所、その他岩内原野、石狩平野にも御手作物が設けられていた。また、安政6年(1859)箱館奉行は資金の乏しい農民に対し新開地1反歩につき金2分2朱、用水路100間には1両を貸し与え10年々腑などの制度を設け、成績の良い者に村しては6年目に地検し残金の返済を免除した。このようにして官費使用によって造成された水田だけでも文久2年(1862)には260町歩余に達した。
農事指導に当っては勧農係が設けられ、先の庵原薔斉のほかに中島辰三郎、大友亀太郎らがいる。中島辰三郎は単に農事の指導だけでなく農民のよき相談相手となり信望を博し、大友亀太郎は二宮尊徳の門下であり、箱館奉行は箱館附近の開墾を尊徳に依頼する考えであったが、尊徳が死去したので相馬藩から尊徳の流れをくむ人々が招かれ開墾に当った。亀太郎はそれらの人達と同し安政5年(1858)渡遺し、初め木古内の開墾におもむき文久元年(1861)から明治元年(1868)まで大野村に在住して指導を行った。後兵部省出張所開墾樹として札幌方面におもむき大友堀こと創成川の切り開きを行った。このように栗本鋤雲をはしめとし前記の人々の熱心な農事指導が道南農業の基礎を築いていった。この間、上ノ国村でも新村久兵衛らの努力で水田、畑が増え、収穫も多くなっていった。また、家政4年(1857)アメリか貿易事務官ライスが箱館に来てアメリカ作物の種子を奉行に贈り市内で野菜を栽培したとあり、このとき初めて外国産の野菜が蝦夷地にまかれたことになるが、その種類も成否もよく知られていない。外国船が箱館に来るようになり開港が認められてから急速に需要が増えたのが馬鈴しよであり、幕府も積極的に栽培をすすめ、その加工まで行った。しかし、慶応2年(1866)は凶作であり、渡島地方の水稲は「白ひげ」と「赤毛」の種籾がとれたにすぎなかった。
7 箱館府時代(1868~1869)
明治元年(1868)明治新政府は箱館奉行を廃して箱館裁判所を開き、後これを箱館府と改称し全島統治の政庁とした。
この前年、慶応3年(1867)箱館奉行杉浦兵庫頭が農事の試作を箱館駐在のプロシヤ国副領事C.ゲルトネルに依頼した。C.かルトネルは箱館で貿易を営んでいる兄のR.ガルトネルが農業の指導者であると教え、兄の拓殖意見書を差出し試作に必要な土地の貸付を奉行に願い出た。この事業が許され、ようやく軌道に乗ろうとしたときに箱館奉行所は撤廃され、慶応4年(1868)4月(9月に明治元年となる)新政府による箱館裁判所が開設された。 ガルトネルは早速判事井上石見と契約を結んだが、いつの間にか当初の計画より大分要求が増えたものになっていた。本国から機材類も続々到着していたときに、今度は箱館戦争が始まり、榎本の統治下に入ったので蝦夷島総裁榎本釜次郎と「蝦夷地七重村開墾条約書」の調印を行った。この間、1 万坪の土地と入用金3~400両程度のものが300万坪の土地99ヶ年の租借と5万ドルの経費に変ってしまった。この土地の中には多くの地域農民の住居、耕地、林野が含まれており、住民にとっては死活問額であった。
8 開拓使時代(1869~1881)
明治2年(1869)明治新政府は開拓使を置き、蝦夷を改め北海道と称し、開拓使出張所を函館に置いた。
この年、清水谷府知事はガルトネルと改めて約定書を取り交し、農民との聞も緩和されたがこの広大な地域を治外法権的に認めておくことは問題であるとし外交問題にまで発展し明治3年(1870)開墾費用6万2千5百ドルを支払ってようやくその土地を取戻すことができた。
ガルトネルの農業上の仕事をみると300万坪の内実際に開墾したのは9万8千坪で約30分の1程度ではあったが3ケ年で達成し、引継ぎのときの道庁の明細書には牛馬20頭、豚21頭、鶏その他31羽、その他器機家作などとあり、畑には野菜栽培、麦(えん麦、裸麦、小麦)そば、大豆、煙草、五升いも、黍、りんご、梨、すもも、あんず、まるめろ、更に草地も作られて、欧風、日本風の庭園まであった。ガルトネルが外国から取り寄せたものの中には、多くの農具頬のほかに、えん麦3品種、小麦、苧麻(ラミー)、菜豆、えん豆、菜種、大麦、にんじん(赤と白)、りんご、洋梨、グスベリ、ぶどう、カーリンズ、おおとうなどのほかにアルファルフア、レッドクローバーもあり、ぶな、つげ、いたや、米団ひのきをまいて苗圃を設けている。更に、山から稚樹をとって来て植えたぶな林があり、人工樹林といえばほとんどが針葉樹なのでこの林は世界的にも珍らしいものとして現在も残っている。そのほかに、有志12名、農夫50名を選んで3ケ年交替でヨーロッパ農法の教授も行ったけれども、結局は西洋式農業の紹介には功績はあったが農業の専門家でなかったため必ずしも成功したとはいわれない。ガルトネルについては、そのずるさばかり強調されているようであるが、農業の面からみるとその功績もあり、実際彼の所で農作に従事した人達の経験が後の仕事に影響したことも考えられ、決して意義がなかったとは思われない。この建物も農具、家畜も明治4年(1871)の火事で焼失してしまった。
明治3年(1870)11月ガルトネルから地所を取り戻し、開拓使函館出張所で管理し七重開墾場と称した。開設から明治27年(1894)廃止に至るまで度々所管が変り名称も11回も変っているが全般を通じて七重官園と呼ばれている。この土地は、最初河津三郎太郎が薬園を開いた所で、後にガルトネルの農事試験の場となった所でもあり、更に七重官園として道南の農業にとどまらず北海道農業の発達に大きく寄与した。
官園で栽培された作物の中には北海道での栽培の起原とされるものも少なくないと思うが、明治3年(1870)5月東京官園から、練馬だいこん、細根だいこん、藍、陸稲、きゅうり、なす、かぼちゃ、かんしょ、里いもを、翌年は新たに、えごま、三島菜、ねぎ、ごぼう、近江かぶ、小松菜、甜瓜、おたふくだいこん、かんらんなどを取寄せて栽培している。明治6年(1873)には荒地を開墾して米国産とうもろこし、プロシャ産裸麦を作り、翌7年には牧草地を開いて米国種の牧草18種をまきチモシーとクローバーが適していることを認め、明治8年には米国種大小麦翌9年には阿波から藍を購入して栽培するなど、多種多様のものを試作したり、優良種子を購入して各村に配付も行っている。明治12年(1879)に初めてドイツ産春播大麦を栽培しあまりの多収に驚いたり、その他草花類、棟木も総計290万本余りに達し民間にも払下げている。本道への洋果樹の移植はガルトネルが始まりであるが、官園でも果樹園を設ける一方民間にも分売し、農業現術生を派遣して栽培法を教え、害虫の駆除法なども教えている。
そのほか、明治8年(1774)には、エドウィンダンが来て農業各科を教え、10年にはクラーク博士も来ている。明治9年(1775)には函館支所管内の土地の肥せき、動植物の適否の調査なども行っている。この年7月16日、明治天皇は本道に初めて御上陸になり翌17日には試験場に行幸になっている。このとき事務所の附近の道路に奉迎のため松を植えたのを更に翌年試験場の手で並木にしたのが現在残っている七飯~函館間国道5号線の松並木である。明治14年(1881)にも明治天皇は七重勧業試験場に行幸になっている。
更にまた、大野村に養蚕場、桑園を作ったり、桔梗に牧羊場を作ったりしたほか、農民の請願に応じて耕牛馬、及び農具を携えて出張して農相を指導したり、動物を希望によって貸付けたり、場内では水車場を作って製粉、挽割、製煉場を置いて粉乳、バターの製造、甜菜糖の製造からブランデー、焼酎、ブドー酒、香水の製造、製紙、製麻に至るまで広範囲にわたった事業を行った。しかし、漸次畜産が主体となり明治27年(1894)9月、北海道種畜場七重分場という名称を最後に七重官園は姿を消してしまったが、この間農事畜産の試験、指導、教育、普及に果した役割りは偉大なものであった。
一方、一般の農業はどうなっていたかというと、開拓使は、本道の開拓の第1要務は農業資源の開発にありとし、農業移民の受入れに積極的な方針を立てたが、稲作に村しては極めて消極的であり、明治2年(1869)には稲作畑作共に凶作であったこともあり、稲の奨励を中止することにさえなった。特に、開拓使の顧問がアメリカから来ると、彼らは麦主食論であり、北海道の寒冷地での稲作の無謀を唱えた。しかし、道南では、特に大野村周辺ではこれまで苦難の道を歩み続けて来た稲作を捨てることができずまた米に村する執着が根強く残っていた。このことが、明治6年(1873)島松で米作りに成功した中山久蔵の、大野から稲品種赤毛を持ち帰れたことにつながり、後の北海道稲作の振興に大きく役立ったと考えなければならない。北海道庁調査の明治3年(1870)の水田面積は347.4町歩、畑738.1町歩でその場所は渡島国亀田郡と上磯郡で占めていた。畑は明治5年(1872)に急激に増加し、その地域も渡島国以外にも拡がっているが、水田は明治9年(1876)まで400町歩台で大きな変化はなかったが、同10年に初めて561.4町歩と100町歩も増え、翌11年には1029.7町歩と大巾に増加した。しかし、それも地域的に見ると亀田、上磯郡のほかに檜山郡、福島郡、爾志郡が増えたためであり、道南以外の地域の面積はまだ数字に上るほどのものではなかった。
畑作が仝道的に拡がり漸次発展していったことから、明治11年(1878)第1回農業仮博覧会が札幌で開催され、翌年は函館と毎年交替で開かれ、札幌で2回、函館で2回行われた。出品点数も年々増え見学者も増加し農業の勧業に非常に役立ち、後にこれが北海道物産共進会に発展した。
9 三県時代(1882~1885)
明治15年(1882)開拓使を廃し、本道の行政は函館、札幌、根室の3県制となった。
稲作に村して消極的であった開拓使も、七重官園、札幌官園では早くから試作を行っていて数年の間成績が良好であったので米作拡張を図ろうとしたが、明治17年(1884)の凶作に遭い米作の奨励は行き詰まりの状態となった。
10 北海道庁時代~現在
(1)試験場設立まで(1886~1908)
明治19年(1886)三県時代は政令分治の傾向があったため、ここに北海道庁が成立することになった。
明治25年(1892)先に米作新論を著した米作の権威者、酒勾常明が道庁の財務部長に就任するに至って、ようやく道庁も稲作奨励に転換し、翌年官園の七重村種畜場内と上白石、真駒内の3ケ所に稲作試験場を設けた。それまで北海道では開拓使時代から米作排斥論の強かった札幌農学校系技術者の反対はあったが、それも民間の米作熱や道庁の方針などによつ次第に克服されていった。道南では、明治19年(1886)と23年は豊作であったが、明治15年、17年、21年、22年、26年と不作であったがそれにもめげず、明治28年(1895)藤田市五郎の努力が実り大野村に千代田用水が完成し、それまで水不足で耕作できなかった所が水田の拡張が可能になり、また明治35年(1902)土功組合法制定を契機に造田に対する積極的な補助援助が行われ急激に水田は増えていった。
七重の稲作試験場を担当したのは、福岡県の著名な老農、林遠里の門人で明治18年(1885)以来米麦改良技師として多くの県に招かれていた入舟重太郎で、道庁の嘱託に応して単身渡通した。彼は試験場を担当しながら附近各地に出張して米麦改良の仕事をしていたが、この試験場も明治27年(1894)七重官園の廃止と同時に廃止された。入舟重大郎は翌28年道庁の嘱託を解かれたが土地にとどまつ、後に七重村の札幌農学校第7農場内の土地を借り受け永住の決心をし、郷里から家族を呼び寄せ開墾耕種に着手し、地方の農業振興に貫献した。彼は籾の塩水選、短冊苗代、馬耕、害虫駆除などを指導奨励している。
このように道南には立派な農業指導者が居たが明治31年(1895)は水稲の反収83kg、35年5kg、38年56kg、39年26kgという凶作に遭い、どこの支庁よりも収量が少なかったことなどから、当時既に上川、白石に稲作試験場があったことからも、遣南にも是非農事試験場を誘致したいという気運が持ち上ってきた。
明治32年(1899)北海道農会幹事長の佐藤昌介から園田北海道庁長官に「農林に関する建議書」が提出されているが、その中で、北海道を6農区に分け各区毎に試験場を設け農事に関する諸般の計を施すべきであるとし、札幌地方には本場を他の5地区には支場を置き、渡島地方については「該地方は古来米作を以て専らとし全道中米作地の称ありこれ気候の然らしむる所なり故に此の天然の要素を利用し主として米作に就て試験を行ぶべし」と述べている。また、明治40年(1907)大野村で農事試験場を設置する建議書が村会議員から大野村会議長宛に出きれた。その原本は現在町の書庫の中に埋もれ残念ながら発見できなかったが、大野町史から転写すると、次のようなものである。
建議書
農業ノ進歩発達ヲ図ラント欲セハ必ス之ヲ指導シ之力模範トナルモノノ存在ナカルへカラス本道中央部其設備アリト雖モ遠隔ニシテ能ク普及スへクモアラス今ヤ戦後ノ農業経営ハ益々殖産ノ発展ヲ期セサルへカラサル時二於テ悲シムへキ哉三十八九年ノ惨状ヲ見ルニ至リタリ(中略)
農事試験場ノ設立ハ住民多年ノ宿題タリシモ今ヤー層其設立ヲ翹望シテ止マサル者ナリ聞ク北海道農会亦其必要ヲ認メ渡島半島二農事試験場ヲ設立スル建議書ヲ提出セリトー(中略)一機将二至ルコノ機ヲ逸センカ好機ハ再ヒ来ラサルへシ渡島半島ノ気候温暖ニシテ地味把沃且(中略)
北海道農業経営ノー端トシテ速ヤカニ濃島半島即ナ其最モ至便ノ大野村二試験場ヲ設立シ(中 略)村長貴下願ハクハー村ノ村福ヲ進ムルタメニ此ノ拳ヲ賛シ之力実行アランコトヲ望ム
右及建議候也
明治四十年二月十一日
建議者 松田泰治郎
松代徳太郎
藤田市五郎
賛成者 村会議員一同
このような情勢の中で、試験場の設置については色々な条件が整なわなければならなかったとは思うが、大野村の立地条件、あるいは歴史的実績、更にまた地元住民の熱意、有力者の強い働きかけなどにより、ついに明治42年(1909)7月4日、北港道庁立渡島農事試験場が誕生することになった。
農事試験場開設以前の道南の農業は、要するに、漁業との兼業から始まり、天の恵みと地の利を持ち本道の先駆地、先進地として発展して来た。もちろん、本州に比べるとはるかに厳しい寒気があり、稲作などは試作の繰返しでなかなか定着できなかったが、ある意味では明日の食糧をかかえながらの農業であったともいえる。更に、松前藩、幕府による農業政策にはかなり違いがあったとしても、時代によっては強力な指導と援助があり、開港、ガルトネルなどによる新しい作物、外国の技術のいち速い導入、ひいては、七重官園による指導と普及は、それまでの根強い努力の結集によって培われた基盤とあいまって多くの優れた農事指導者と不屈の農民魂を持った農民の輩出もあって道南の農業は確立きれたかに見えた。しかし、明治に入ってからの開拓政策は、道南を扉の陰に隠してしまい、目は専ら内陸に向けられ、漸次農業の中心は石狩、空知、上川に移り、渡島地方の農業はむしろ停滞気味となった。
(2)明治、大正時代(1909~1926)
試験場の開庁は明治42年(1909)7月4日であるが、庁舎の竣工したのは8月17日で22日に無事引渡しが完了した。試験実施のための畑、水田の造成に当っては地元青年団の積極的な応援があり、特に水田造成には道庁から外賀事業手がわざわぎ派遣されている。この年11月6日、函館支庁管内の戸長町村長会議が開かれているが、そのときの支庁長の指示事項の中に「農事試験場二関スルコト」として「渡島地方多年ノ宿望タリシ農事試験場ハ本年ヨリ亀田郡大野村二設置セラレ本年秋作ヨリー部着手ノ事トナレリ思フニ農事試験場ヲ特二渡島二置カレタルモノハ渡島地方ノ農作ノ多ク旧慣ヲ墨守シ其進歩遅緩他ノ後進地方卜共二駢馳セサルノ結果タラズンバアラス而モ試験ノ成績ハー般当業者二於テ之ヲ実地二応用セザレバ遂二共功ナカラン故二其成績二付テハ能ク周知ノ方法ヲ講ジ其普及二努ムベク又当業者ハ論ナク青年団体二勧説シ作付期間中各試作物ノ実況ヲ視察セシメ以テ斯業ノ進歩ヲ期セシメラルペシ」と記されている。道南の農業をその停滞から脱却きせ躍進させるためにいかに農事試験場に寄せる期待が大きかったかがうかがわれる。
黒沢場長は試験場建設の大任を果し、翌43年去り、試験場も国費に移管きれ北海道農事試験場渡島支場と改称し、安孫子孝次支場長が4月に着任し本格的に試験研究に着手することになった。試験課題、主要成果、それらの背景については各部門毎に記述されるので省略するが、事業の目的には「渡島支場は渡島、檜山支庁管内および函館市を事業上の担当区域とし、地方に適応せる試験および調査を分担施行し、主として該区域内に於ける農業発達に資せんとするにあり」とあり、大正7年(1918)の北海道農事試験場一覧には支場の事務分掌として、地方重要農作物の試験、品種の改良育成、模範作、農事調査、種苗の配付、実習生に関する事項などが記されているにすぎないが、大正15年(1926)の事業の概要には、「園芸並に稲熱病抵抗性水稲に関する試験および調査に重きをおき、以て本場に於ける同試験および調査の一部を分担すると共に渡島地方重要農作物に関する試験および調査をも施行するものとす」と変り、その内容も、「農作物適否、農作物品種、果樹そ菜、品種改良耕種肥培、収穫乾燥、飼料作物および病害虫に関する試験、調査、豊凶考照試験、模範作、種苗配付、実習生養成、講習講話、質疑応答」と具体的になってきている。
試験場設立当初は一般農家に試験場というものが十分認識きれていなかったため、特に農家の子弟とのつながりを持つための努力がなきれた。大正2年(1913)は明治35年(1902)以上の大凶作であり翌年は水田耕作も減少したが、既に基整ができ上っていた渡島では昔のように稗田に変ることもなく、北海道全体では12%も減反になったが、わずか5%以内の減少にとどまった。
大正4年(1915)安孫子支場長に続いて窪円森太郎が支場長となったが、この時代には庁舎の増築、実習生の養成、陳列館の新築、温室の設置、模範果樹園の創設などがあり、試験場の基磯が確立した時代でもあった。窪田支場長は、毎年のように函館市内の名士、農業関係者を招いて農事研究会と試食会を催し、試験場の認識と試験研究の普及に努めた。特に、温室の設置に当っては、函館の篤志家渡辺熊四郎氏の寄附によるもので、その火入式には三宅本場長も出席し盛大に挙行されたが、その日は大野一円の有志青年の自発的行動から発足した私設研究団体である研農会が品評会を開催し、来賓の送迎を行うなどし地元農民との強固なつながりを示している。
この時代の道南の農業は旧開地械といわれ、水田面積の増加は見られても遅々としたものであり、主要作物は大豆であり、馬鈴しよがこれに次いでいた。全道的にみると、水用は空知、上川、石狩に急増し、麦頬は網走、豆頬は十勝に拡がり主要産地として形成されていった。
(3)昭和時代(戦後まで)(1927~1945)
大正の終りから昭和6年(1931)の冷害凶作までの間は、造田補助もあり水田の面積は増えていった。昭和5年(1930)には道産米300万石の祝賀会が開かれ、大正9年(1920)に100万石の祝賀会が行われて以来10年で3倍の収穫をみるに至ったことになる。昭和4年(1929)6月、駒ヶ岳が噴火し鹿部村は軽石に埋もれ壊滅状態に陥った。試験場では噴火後の緑化を試みる試験を現地で行った。この時代は戦争の時代であり満州事変、上海事変が日中戦争と拡大し、更に太平洋戦争につながっていった。そのため、漸次肥料不足、人手不尽、資材の不足が深刻化し、その反面食糧の増産が要求され、空地は畑となり、一般の人も家庭菜園を作り、農家の忙しい時期には学生などが援農に協力した。水田の面積も昭和7年(1932)をピークにして漸減していった。その間、試験場といえども例外でなく人手不足に悩まされながらも増産対応の試験肥料不足対策の試験などに重点が置かれて試験研究が続けられた。昭和19年(1944)、17年に試作場から分場と名称を変えた檜山、瀬棚、倶知安の各分場は渡島支場の所管となった。昭和20年(1945)終戦を迎えた。
(4)昭和時代(戦後~現在)(1946~1978)
戦後になっても食糧危機は続き、主食は欠配遅配を続け、食糧の買出しが農家に殺到し悲喜こもごもの風景が展開された。昭和25年(1950)農業関係試験研究機関の整備総合計画によって国立と道立農業試験場に分れることになったが、このときに支場所管の分場は廃止された。この整備計画に当って、渡島支場の存廃が取り上げられ、その性格から特色が無く、その位置から見て気象的に青森県と大差ないと判定され危うく廃止の浮き目をみるところであったが、関係者の努力によって、北海道農業と本州農業の一接点であり、品種、栽培技術のふるい分けの場として必要であることが強調され、ようやく命を取りとめることができた。
道南の農業は温暖な気象に恵まれながらも、ときには冷害凶作に、ときには台風災害にも遭遇しながら稲作保護政策が実を結び漸次水田面積は増加し、昭和44年(1969)には渡島支庁管内7380ha檜山支庁管内8700haを記録するに至った。しかし、それと併行して麦頬、大豆、てん菜などの畑作物は大巾に減少していった。全国的な水田の増加は、品種の改良、栽培技術の進歩、更に好天にも恵まれ豊作を続けたため、ついに国内産米過剰という結果を生し、昭和45年(1970)には稲作転換対策が実施され漸次水田面積を縮少しなければならない立場に追いこまれていった。それまで、道南の農業は稲作中心とはいいながらも酪農地域を有し、食用、種子馬鈴しよの生産地でもあり、函館市を対象とした露地野菜の供給地でもあり、何でもできる反面特色の無い地域とも称されていた。しかし、経営規模が小さいため平面的な規模の拡大は困難であり、その克服のため、天候の有利性を生かし土地の周年利用を図る施設周芸が発展していった。
この間、農業試験場でも水田の中心にあった果樹園を向野の傾斜地に移転させ新たな構想の下に果樹試験を発足させた。昭和39年(1969)道立農業試験場の機構改革が行われ、それまでの北海道立農業試験場渡島支場が北海道立道南農業試験場となり、試験研究の方向も施設園芸重点に指向され、場内の圃場にもビニールハウスが連立し、土壌肥料、病害虫の試験も園芸作物に重点が置かれるようになった。したがって、畑作物の試験はわずか大豆の系統適応性検定試験にとどまり、かっての馬鈴しよ、麦頬、てん菜などの試験は姿を消してしまった。ただ、果樹と稲作とは地域の主要作物であるだけにその対応として続けられている。
道南の農業も社会、農業情勢の維移と共に、積極性の少い農業地域でありながらも変貌して釆ており、酪農地帯、馬鈴しよ地帯に加えて、施設園蓑の地域が拡大され、かっては見られなかった肉牛の姿もあり、水稲の栽培方法も械械化の時代に変ってしまった。これに対応して、設立以来同じ土地で創立七十周年を迎えた道南農業試験場は、これまでの先輩の幾多の試験研究を回顧しながら新しい時代の意義ある試験研究に取りんでいる。
(小林書久夫)