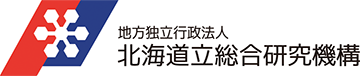研究通信第5号 研究成果
根釧農試 研究通信 第5号
(1995年3月発行)研究成果(図表省略)
酪農第一科、酪農第二科、土壌肥料科
乳製品の国際化を前にして、より足腰の強い酪農経営への変換が求められようとしている中、放牧酪農はゆとりの創出、糞尿処理量の低減、栄養価が高く生産費の安い粗飼料、貯蔵粗飼料の調製量が減ることによる労力とエネルギ-の低減、牛のストレス解消等、酪農経営が抱える“今”の課題を解決する多くの利点を持っています。しかし現状は放牧利用の減少傾向が続いており、北海道の風景から放牧牛の姿が減り始めてから久しくなります。これは近年の高泌乳化が進んで来た牛群に対応する放牧技術を提供できなかったことに一つの原因があります。
ここに示しました放牧技術では、現在の北海道の乳量水準(全道平均7,836kg、根釧地域の平均7,603kg)の牛群を放牧主体で飼養するべく、乳量9,000kgの経産牛について適応できる放牧技術の開発をめざし、そのための適用イネ科草種についても検討した成績です。
1.家畜と草地の両面から3つの試験を行いました
1) 放牧用イネ科草種・品種の利用法
2) 昼夜放牧における供給飼料の給与法
3) 放牧飼養における泌乳初期の飼養法
2. 根釧地域の放牧草は当面チモシ-「ホクシュウ」を草丈30cm利用
根釧地域における放牧草はチモシ-の晩成品種である「ホクシュウ」が適しており、草丈30cm程度の利用により良好な植生が維持されました。また兼用草地(1番草を採草した後、放牧に利用する)では早生~晩生品種の「ノサップ」、「キリタップ」あるいは「ホクシュウ」の利用が適当でした(図1)。しかし、メドウフェスクとの混播はチモシ-の維持という点から避けた方が良いと考えられました。オ-チャ-ドグラスは根釧地域では安定性に欠けますが、「ケイ」を主体とし草丈は30cm程度の利用が適当であり、メドウフェスクとの混播は可能と考えられます(図2)。
3.昼夜放牧で9,000kgを達成、乳脂肪率の維持にはNDF40%がめやす
昼夜放牧における放牧草の乾物摂取量は11kg程度と見込まれ、乳量9,000kg、乳脂肪率3.6%の牛群では泌乳前期に供給するTDN給与量は9.8kgとなりました。放牧草を含めた全飼料に占めるNDF含量が35%では乳脂肪率が3.5%以下となったことから、放牧主体飼養ではNDF含量が40%程度必要と考えられました。また、昼夜放牧時に牧草サイレ-ジを多給しますと、放牧草の摂取量が抑制されたことから、供給する牧草サイレ-ジの給与量は乾物2~3kgにとどめたほうがよいと考えられました。この試験により設定した放牧時の飼料構成と給与例を表1に示しました。
4. 生理的に特別な泌乳初期は当面昼夜放牧を避けます
昼夜放牧では泌乳初期のTDN充足率が80%を下回り、体重の急激な減少や血液成分(肝機能検査等)の異常がみられました。また、泌乳初期の時間制限(10時間)放牧では、乳量が40.4kg/日で泌乳持続性もよく、乳脂肪率は3.78%と安定していました(表2)。しかし、肝機能の低下や初回発情日数が53日と遅いなどいくつか問題点を残しており、引き続き検討を続けております。
以上のとおり、昼夜放牧により乳量9,000kgの牛群を飼養できることが明らかとなってきました。ただし、生理的に特別な泌乳初期についてはいくつかの問題点を残したことから、当面放牧時間を短縮するなどして肝機能や繁殖性の低下を防止することが必要でしょう。
酪農第一科、酪農第二科
農産物自由化の波は酪農にも及び、低コスト化と同時に消費者の高品質ニ-ズに応える高品質牛乳の生産技術が一層重要となっています。こうした背景のもと、牧草サイレ-ジ主体飼養において高乳成分を維持する飼養構成、給与方法、牛乳の品質、風味の評価等について検討しました。
1.供給試料のエネルギ-含量の違いと乳生産影響
トウモロコシ、フスマ、ビ-トパルプ、大豆粕を用いて供給飼料のTDN含量をH区90%、M区85%、L区80%とし、試験1では泌乳前期用に牧草サイレ-ジと50:50に、試験2では、泌乳中期用に65:35に混合して泌乳試験を実施しました。
試験1では、H区のTDN摂取量は16.1kgでM区およびL区より1.5kg多くなりました。この結果、H区の乳量は31kg以上でM区、L区に比べて2~3kg高く、各乳成分生産量もやや高い傾向がみられました。これに対して、泌乳中期の試験2では、摂取量、乳量、乳成分に差はありませんでした(表1)。これより、乳量30kg以上ではエネルギ-含量を高めることによる乳量、乳成分の向上効果が示唆されました。
2.魚粉給与と乳生産
経産牛26頭を分娩前4週から分娩後16週まで用い、対照区(牧草サイレ-ジ:トウモロコシ:大豆粕=50:38:12)に対して魚粉区は蛋白源の大豆粕の約半量を魚粉に置き換えて泌乳試験を実施しました。
乾物摂取量は魚粉区、対照区それぞれ20.4、21.2kg/日と差がなく、嗜好性の劣るとされる魚粉も乾物5%程度の混合飼料として用いる場合には、乾物摂取量への影響は少ないものと考えられました(表2)。 実乳量は魚粉区、対照区それぞれ37.8、36.8kg/日と差はみられませんでしたが、乳蛋白質率はそれぞれ3.08、2.91%と魚粉区が高く推移しました(表2)。このことは、メチオニンおよびリジン含量が高く、第一胃内分解率が低い魚粉の給与により、乳合成における制限アミノ酸の補給効果があったものと考えられました。
3.ル-サンペレット給与による泌乳前期の乾物摂取量向上効果
経産牛18頭を分娩前4週から分娩後16週まで用い、対照区(牧草サイレ-ジ:トウモロコシ:大豆粕=50:38:12)に対してLP区は牧草サイレ-ジの20%をル-サンペレット(LP)で置き換えて泌乳試験を実施しました。
乾物摂取量は代謝体重当たりでLP区が高く推移し、分娩後3~8週でLP区、対照区それぞれ178、157gでした(図1)。乳量は両区に差がみられませんでしたが、乳蛋白質率はLP区が高い傾向にありました。
LP区は対照区に比較して分娩後の体脂肪動員の指標である血清遊離脂肪酸濃度が低く、分娩後の体重は増加傾向にあり、泌乳持続性が高い傾向を示しました(図2)。このことはル-サンペレット給与により泌乳初期の乾物摂取量が向上した効果と考えられました。
4.飼料給与回数および給与順序の違いと乳生産
粗農比50:50および40:60に相当する濃厚飼料それぞれ12、15kg/日の給与回数、給与順序等について5回の試験を実施しました。
各試験とも高乳成分が維持され、設定の粗濃比範囲では給与方法の違いは乳成分に影響しませんでした。しかし、経時的に計測した採食量の結果から濃厚飼料の単独先行給与は避けるべきものと判断されました(表3)。また給与回数を少なくすることについてはより慎重な検討が必要のようです。
5.飼料構成および飼料給与法と牛乳風味
上記の各試験で得られた個体乳を用いて風味の官能検査を実施しました。その結果、飼料構成や給与方法の処理の違いと風味の評価に一致した傾向はみられませんでした。しかし、乳成分の低い個体や泌乳初期の牛乳の風味は劣る傾向がありました。
酪農第一科
1.はじめに
泌乳牛に給与する自給粗飼料は、根釧地方では牧草サイレ-ジ、十勝地方ではとうもろこしサイレ-ジが中心となっています。乳用育成牛に関しては、特に幼齢期にサイレ-ジ給与による摂取量の低下や反芻胃発達への悪影響が問題とされており、質の良否を問わず乾燥を給与している場合が多くみられます。しかし、育成期におけるサイレ-ジ給与は、粗飼料の調製・給与体系の簡素化が図られることや、良質で安定した栄養価の粗飼料の給与によって発育の向上が期待されますが、育成期にサイレ-ジを積極的に利用した報告は少なく、また給与指標も示されていませんでした。
そこで根釧農試では牧草サイレ-ジ、新得畜試ではとうもろこしサイレ-ジの給与が、育成牛の飼料摂取量および発育に及ぼす影響について検討しました。ここでは根釧農試で行った試験成績について紹介します。
2.試験方法
試験には、生後まもなくのホルスタイン種雌子牛8頭を牧草サイレ-ジ区(S区)と乾草区(H区)に分けて供試しました。6週齢離乳を行い、日本飼養標準の日増体量0.7kgのTDN要求量を満たすように濃厚飼料を両区に等量給与し、S区にはチモシ-主体1番刈牧草サイレ-ジを、H区にはチモシ-主体1番刈乾
草燥を自由摂取させました。粗飼料のTDNおよびCP含量は哺育期では牧草サイレ-ジが、それぞれ64、12%、乾草が62、11%、育成前中期では牧草サイレ-ジ、乾草ともに61、10%でした。9から 12ヵ月齢の間は、1日8時間の制限放牧を行いましたが、粗飼料の主体は牧草サイレ-ジまたは乾草でした。
3.試験結果
1)生時から受胎までの飼料摂取量と発育
哺育期(0~3ヵ月齢)の乾物摂取量は両区とも週齢に従って増加しましたが、離乳後の粗飼料摂取量はS区がH区よりやや高く、哺育期全体の累計ではS区、H区でそれぞれ26.2、19.2kgとなりました。各週齢における個体間のばらつきもS区とH区に差はみられず、哺育期に最も問題と考えられていた牧草サイレ-ジの摂取量は乾草に比べて劣らないことが明らかになりました。
哺育期から育成中期までの1日あたりの乾物摂取量を図1-a,bに示しました。哺育期と同様、S区の粗飼料摂取量がやや多く、総摂取量もS区がH区を上回る傾向がみられました。TDN摂取量は両区とも日本飼養標準の日増体量0.7kgの要求量をほぼ満たして推移し(図2)、充足率はほぼ100%でした。これに対して、粗蛋白質(CP)の摂取量は7ヵ月齢までは日本飼養標準の日増体量0.7kgの要求量をほぼ満たして推移し、放牧草を給与した9ヵ月齢以降で両区とも要求量を上回り(図3)、充足率はS区、H区でそれぞれ132、124%となりました。つまり、標準的な発育が要求する養分からみて、エネルギ-に対する蛋白の摂取量が多く、またS区はH区を上回る結果となりました。
体重は両区とも日本ホルスタイン登録協会の発育値(ホル協発育値)の平均を上回る増加を示しました(図4)。日増体量は、哺育期が両区とも0.75kg程度、育成中期までではS区、H区でそれぞれ0.88、0.84kgと、S区で高くなりました。体高などの骨格の発育もホル協発育値の平均を上回り、S区はH区を上回る傾向がみられました(図5)。
2)受胎から分娩までの飼料摂取量と発育
受胎から分娩までの育成後期(15~24ヵ月齢)については、S区のうち3頭の受胎した試験牛の飼料摂取量および発育についてまとめました。
発育後期の1日あたりの粗飼料乾物摂取量は6~8kgの範囲であり、平均で約7kg、総乾物摂取量は約8kgでした。育成中期までと同様に、TDN摂取量は要求量をほぼ充足し(充足率:95%)、CP摂取量は要求量を上回る(充足率:113%)結果になりました。発育も育成中期までと同様、体重はホル協発育値の上限近く、体高もホル協発育値の平均程度であり、この間の日増体量は0.78kgとなりました。
4.まとめ
育成牛への牧草サイレ-ジ給与で一番心配された摂取量の低下やばらつきは認められませんでした。第1以内溶液中のアンモニア態窒素濃度や血中の尿素窒素濃度に牧草サイレ-ジと乾草の蛋白の分解性の違いが現れましたが、正常の範囲内であり、牧草サイレ-ジの給与による反芻胃発達への悪影響は認められませんでした。
発育にも問題は生じず、むしろS区はH区を上回る体重や体格の増加がみられました。今回の条件ではS区、H区ともにTDNに対してCP摂取量が高くなり、それが良好な発育につながったと考えられます。
これらのことから、飼料の条件に制約はあるものの哺育期からの牧草サイレ-ジの利用は十分可能であり、乾草より良質な牧草サイレ-ジを給与できる条件では特に蛋白の給与源として有効であることが明らかになりました。
4.生乳検査時におけるペ-パ-ディスク法に対する乳固有の抗菌因子の影響
酪農第二科
1.背景とねらい
北海道では、生乳の抗生物質の日常検査に用いられるペ-パ-ディスク法が乳固有の抗菌因子の影響を受けるのを避けるために、検査試料に80℃5分の前処理を行っています。しかし、抗生物質汚染乳の原因調査などでは、抗生物質の使用記録がないにもかかわらず80℃5分の前処理を行なっても明瞭な阻止円ができる個体がみられ、汚染原因の究明が困難となることがあります。このような反応の原因は、80℃5分処理後も乳固有の抗菌因子の影響が残るためと言われてきましたが、仔細は不明でその消去法も明確ではありませんでした。
そこで、生乳に存在する乳固有の抗菌因子であるラクトフェリンとリゾチ-ムがペ-パ-ディスク法での阻止円の形成に与える影響を明らかにするとともに、乳固有の抗菌因子の影響を消去するための前処理法について検討しました。
2.乳固有の抗菌因子による影響
乳固有の抗菌因子の阻止円形成作用を検討したところ、ラクトフェリンは脱脂乳への添加では16mg/ml以上の濃度で阻止円を形成しました。しかし、この濃度は正常乳の平均値0.2mg/mlや初乳での数mg mlという値に比べかなり大きな値でした。
牛由来のリゾチ-ムは、脱脂乳への添加では8U/ml以上の濃度で阻止円を形成しました。この濃度は正常乳の数U/ml以下に比べると大きな値ですが、重度の乳房炎乳でみられる数十U/ml以上の濃度に比べると小さな値でした。
抗生物質汚染のない個体乳や分房乳等の生乳試料でも、試料によっては80℃5分処理後に阻止円が形成されました。この、生乳試料の80℃5分処理後の阻止円の直径と乳中の体細胞数の体数値、リゾチ-ム濃度の体数値およびラクトフェリン濃度との単相関系数は、それぞれ0.69、0.56および0.34でした。
このことから、この阻止円は乳房炎による乳中のリゾチ-ム等の乳固有の抗菌因子の増加が原因となっていることが示されました。
ペ-パ-ディスク法による抗生物質の残留検査で乳固有の抗菌因子による偽陽性を避けるためには、乳房炎乳の混入を防止することが大切です。
3.トリプシンを利用した前処理法
検査試料のトリプシン処理により、ペ-パ-ディスク法での高体細胞乳の阻止円が消失することが知られています。しかし、トリプシン添加のみでは不鮮明な阻止円が形成されたり、ペニシリン標準液の阻止円が大きくなる現象がみられました。これを回避するには、検査試料の前処理法をトリプシン作用時間の終了後に80℃5分の加熱処理を加える[トリプシン+80℃5分]とする必要がありました。
具体的な方法は、検査試料に試料の10%量のトリプシン液を添加して室温で10分間作用させたのちに80℃5分の処理をして、ペ-パ-ディスク法の試料とします。また、このときの添加トリプシン液の濃度は、結晶トリプシンの0.5%溶液(27 USP U/ml程度)が適当です(図1)。
4.「トリプシン+80℃5分」処理とその効果
ラクトフェリンを添加した脱脂乳の阻止円は80℃5分では消去できず、消去には100℃10分、または、「トリプシン+80℃5分」の処理が必要でした。また、牛由来のリゾチ-ムを添加した脱脂乳や重度の乳房炎乳がつくる阻止円は、100℃10分の処理でも消去できず、消去には「トリプシン+80℃5分」の処理が必要でした(図2)。
生乳の、乳房炎によって増加した乳固有の抗菌因子による阻止円は、「トリプシン+80℃5分」の処理によりほぼ完全に消失させることができました。また、この処理はベンジルペニシリン、セファゾリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、カナマイシン、さらには、ストレプトマイシンによる汚染乳の阻止円形成作用には大きな影響を与えませんでした。
5.「トリプシン+80℃5分」処理の利用法
生乳における出荷の良否判定は、あくまでも「80℃5分」処理した試料のペ-パ-ディスク法の結果で決まります。本方法は制度上認定されていないことや、すべての抗生物質に対してその影響度の検討が終わっていないので、「トリプシン+80℃5分」の処理で阻止円が消失したからといってその生乳を出荷することはできません。
この、「トリプシン+80℃5分」の前処理法は、抗生物質汚染牛乳の原因調査のとき,乳房炎に原因する乳固有の抗菌因子の影響を除外するために利用することができます。
「80℃5分」処理後の試料を用いたペ-パ-ディスク法では、乳房炎により乳固有の抗菌因子が増加している乳房炎乳試料と、市販のβラクタム検出キットで強陽性を示すことで抗生物質汚染が証明された試料を区別することはできません(図3)。
しかし、先に述べたようなトリプシン処理の影響を受けない抗生物質による汚染であれば、「トリプシン+80℃5分」処理後の試料を用いて検査を行なうことで乳房炎による乳固有の抗菌因子の影響を消去できるため、図中のβ-ラクタム強陽性を示すような抗生物質に汚染された試料の区別が容易になります(図4)。
酪農第二科
1.背景とねらい
分娩時の乳房炎はその発生が多く、経済的な損失も大きいことから、その防除は大きな課題となっています。経産牛での分娩時の乳房炎の発生原因は、産次を越えた持続性の感染、乾乳期間中に新たに発生した感染、さらには、分娩時の免疫機能低下などによって分娩前後に新たに発生した感染などです。
これらのうち乾乳期間中の新たな感染を予防し分娩時の乳房炎を低減するとされている、乾乳時の持続性抗生剤の乳房注入と分娩準備期の乳頭消毒の効果、さらには、急速乾乳など乾乳条件の影響について検討しました。
2.試験方法
①乾乳時の持続性抗生剤いわゆる乾乳期軟膏の注入効果については50頭の乳牛を用い、それぞれの個体の半分の分房を注入処理区、残りの半分の分房を無処理区として、乾乳後3週時の乳腺の細菌感染状況を比較しました。
②分娩準備期の乳頭消毒の効果については、あらかじめ18頭の乾乳牛の乳頭を使ってヨ-ド製剤とグルコン酸クロルヘキシジン製剤による乳頭付着細菌数の低減効果を比較して乾乳期の乳頭の消毒方法を検討しました。試験は50頭の乳牛を用い、相対的に付着細菌数の低減効果の大きかったグルコン酸クロルヘキシジン製剤を用いて、分娩前2週~分娩直前までの期間、右側乳区を1日2回噴霧消毒する処理区とし左側乳区を無処理区として、分娩直後の乳腺の細菌感染状況を比較しました。
③急速乾乳法など乾乳条件の影響については、乳酸期間中の乳腺分泌液の流動性と乳固有の抗菌因子であるラクトフェリンとリゾチ-ムの濃度を指標にして、乾乳時の乳量の多少や急速または漸減乾乳法などが乾乳期の乳腺に与える影響を検討しました。分泌液の採種は24頭から行ない、乾乳後3週時には全牛、その他の期間は一部の牛について分泌液の採取を行ないました。
3.試験結果
1)乾乳時の持続性抗生剤の注入効果 乾乳時の持続性抗生剤いわゆる乾乳期軟膏の注入効果を、乾乳直前から乾乳3週後までの期間の新たな感染の発生率で比較すると注入処理により新たな感染は26%から12%に半減しました。乾乳時にすべての乳区に持続性抗生剤を注入するいわゆる乾乳期軟膏の予防的使用には、明らかに乾乳直前の感染を予防する効果が認められ、分娩時の乳房炎を低減する効果が期待されました(表1)。
2)分娩準備期の乳頭消毒の効果 搾乳後のディッピングに用いられている二つの製剤の、乳頭消毒による乾乳期乳頭の付着細菌数の減少効果は小さく、比較的減少効果の大きかったグルコン酸クロルヘキシジン製剤でも付着細菌数が7分の1に減少した程度でした。ヨ-ド製剤では有機物との接触で殺菌効果が減少するため、付着細菌数の減少効果はより小さなものとなりました。二つの製剤は、いずれも搾乳後のディッピングでは乳房炎の予防効果が確認されていますが、このような効果となったのは搾乳後のディッピングではそれほど重要ではない消毒効果の持続性を評価することとなったためと思われます。
グルコン酸クロルヘキシジン製剤を使った分娩前2週からの乳頭消毒は、分娩前2週から分娩後2週までの新たな感染の発生率に無処理区との差がみられず、感染予防の効果を確認することは出来ませんでした(表2)。
この試験結果は、現場の指導者からの分娩準備期の乳頭消毒の実施により分娩時の乳房炎が減少したとの報告とは異なった結果となりました。これは、この試験がオガクズを少量敷いたフリ-スト-ル牛舎で行なわれ、牛の汚れが少し目につく状況であったことから、これらが影響したことも考えられます。このため、分娩準備期の乳頭消毒の効果を、この試験結果のみで断定することは出来ません。
3)乾乳条件による効果
乾乳期間中の乳腺分泌液は、乾乳直後の流動性の高い濃厚な牛乳様の分泌液から、流動性のかなり幅のある透明感のあるシロップ様分泌液をへて、流動性の小さいカスタ-ドクリ-ム様分泌液、さらに、分娩準備期のやや流動性の高い初乳様あるいは初乳へと変化しました。しかし、分泌液の見た目の状態や流動性には個体により大きなバラツキがみられ、同じ時期に同じ条件で乾乳しても乾乳後3週時の乳腺分泌液が、ある個体では濃厚牛乳様で他の個体ではカスタ-ドクリ-ム様であるということもみられました。 乳固有の抗菌因子であるラクトフェリンとリゾチ-ムの常乳での濃度がそれぞれ0.2㎎/mlと0.5μg/ml程度であるのに比べ、乾乳期中期にはラクトフェリンでは40㎎/mlと数百倍に、リゾチ-ムでは7~8μg/mlと数十倍の濃度に上昇しました。しかし、肉眼的性状や流動性にもみられたように、個体による大きなバラツキがみられました。
乳腺分泌液中のラクトフェリンとリゾチ-ムの濃度は、バラツキが非常に大きいものの乾乳時の乳量や乾乳方法などの乾乳条件による影響がみられました。乾乳条件別に新規感染が多いとされる乾乳後16
~30日の期間のラクトフェリンとリゾチ-ムの濃度をみると、ラクトフェリンについては急速乾乳に比べ漸減乾乳で、また乾乳時の乳量が多くなるほど分泌液中の濃度が低い傾向がみられました。また、リゾチ-ムでも、乾乳時の乳量が多く漸減乾乳法を取ったグル-プでは、他と比べて低い傾向がみられました(表3)。
乳量が多く漸減乾乳法を取ったグル-プで、両者の濃度が最も低くなることが注目される点です。乳量の多い場合でも、急速乾乳法を採用し乾乳期乳腺の乳に固有な抗菌物質の発現を高めることが、乾乳期の感染を予防するうえで有利となることが示唆されました。
6. 根釧地域における熟期別チモシ-品種とマメ科草の採草型組合せ
作物科
1.はじめに
チモシ-は耐寒性に優れ、家畜の嗜好性も良好であるため、根釧地域では欠くことのできない基幹牧草です。低コスト乳肉生産のためには、チモシ-を自給粗飼料としていかに栽培し、有効利用するかが重要となっています。しかし、チモシ-は再生が遅いため、混播されるマメ科草種が時として優占します。また、根釧地域のチモシ-は早生品種がおよそ7割を占めるために、収穫適期が集中し、良質粗飼料の確保は、天候不順も加わって困難となる場合が多い状況にあります。
このような状況の中、早晩性の異なるチモシ-品種育成に勢力が注がれ、極早生から晩生までの熟期別の品種が、続々と育成されています。これによりチモシ-品種の出補期の幅は、およそ1ヶ月に及びました。しかし、これらの品種は出穂期が異なるばかりでなく、各番草の再生速度、出穂程度などが異なるため、混播組合せなど基本的な栽培手法を明らかにする必要があります。
そこで、それぞれの熟期別にチモシ-の主体性を維持しつつ、混播の利点を生かせるようなマメ科牧草品種との組合せを、現行の優良品種を対象に検討しました。また、各熟期別チモシ-品種の刈取り時期による影響を加味し、安定した植生が維持できる刈取り適期幅についても検討しました。あわせて、チモシ-およびアカクロ-バの適正な播種量について検討し、得られた成績に基づき、熟期別チモシ-品種を利用した草地の年間刈取りスケジュ-ルを策定しました。
2.試験結果
1)チモシ-極早生および早生品種との混播組合せ
①混播するマメ科草種・品種は、「ホクセキ」(播種量0.2~0.4㎏/10a)のような草勢の穏やかなアカクロ-バ品種とラジノクロ-バ品種との組合せが妥当と考えられました。
②極早生品種では出穂始刈りによってアカクロ-バの衰退が早くなりますので、アカクロ-バの維持を考慮すると出穂期刈りが有効です。
③「レッドヘッド」のような草勢の旺盛なアカクロ-バ品種と混播する場合には草種構成の維持からアカクロ-バの播種量を0.2㎏/10a以下にする必要があります。
④「ソ-ニャ」のような草勢の穏やかなコモン型シロクロ-バと混播しますと、アカクロ-バおよびチモシ-に抑圧されて、シロクロ-バが衰退する傾向があります。
2)チモシ-中生および晩生品種との混播組合せ
①マメ科草種・品種の組合せは、現状のアカクロ-バ品種ではチモシ-への抑圧が大きいので、チモシ-の主体性の維持を考慮しますと、草勢の穏やかなコモン型シロクロ-バ品種との組合せが現段階では妥当と考えられました。
3)in vitro乾物消化率および可消化乾物収量
①同一生育ステ-ジであっても熟期の早いチモシ-品種区ほどin vitro乾物消化率は高く、可消化乾物収量は熟期の遅いチモシ-品種区ほど多収となる傾向がありました。
4)チモシ-の適正な播種量
①チモシ-の適正な播種量は条件によって定着数が異なりますが、1.2㎏/10aから1.8㎏/10aの範囲内であれば十分なチモシ-の定着が得られ、機械播種などの実用上の問題もないと考えられました。
以上の結果に基づき、表1には熟期別のチモシ-品種に対するマメ科草種・品種の混播組合せおよび播種量を、図1には熟期別のチモシ-品種の主体草地を利用した年間の刈取りスケジュ-ルを示しました。
3.成果の活用面と留意点
本成果は根釧地域のチモシ-主体草地に適用されます。また、それぞれの品種の特性を把握した上で混播組合せを決定し、ていねいな播種床造成と覆土・鎮圧に留意してください。