サハリンでサフニロとの第24回研究交流開催

写真1 研究交流のひとこま(サフニロ所長室での協議)
今回の主要な議題の一つは、2001年秋の北水試百周年記念行事の際に、サフニロと北水試の間で研究交流の基となる「合意文書」を新たに5年間延長したことに関連した、「貝毒プランクトン共同調査計画」の協議をすることでした。この課題は、サフニロにとっても大変興味があったようで、地元のテレビ局の取材が入り、所長室での研究交流の映像が6月11日にテレビ放映されたとのことでした。また、帰国後、北海道水産林務部からサハリン州での漁業関係記事として、第24回研究交流が紹介されていたとの情報提供を受けました。その概要は次のようでした。
『サハリンと日本の研究者の会議は、伝統的な会議となっている。そして今日、サフニロの研究者は会議で研究成果を交換し合うために、隣国の仲間と再会した。ロシアの研究者は、毒性の単細胞生物である植物プランクトンがサハリン沿岸に拡散するのを懸念している。日本の研究者はこの毒性のある植物プランクトンについて豊富な経験を持っている。サフニロのタラシュク副所長は、北海道の研究者の知識に頼れば、サハリン住民にとって脅威となっている胃腸感染を予防することができると、指摘する。この植物プランクトンは、危険な状態を引き起こすため、厳しく管理されなければならない。日本では、同じ様な単細胞生物の拡散を定期的に観察している専門機関が既に設立されている。毒性プランクトンの増殖時には、貝の漁獲を禁止してさえいる。サフニロの研究者も、将来的にこのような管理体制を整えるよう計画している。(6月13日付サハリンニュース)』
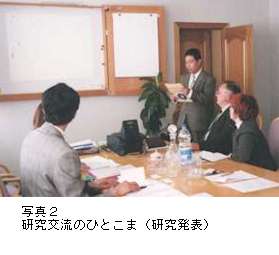
交流日程の中日にあたる6月12日はロシアの建国記念日(休日)でしたが、「ニシンの産卵する沿岸の藻場を視察したい。」という日本側の希望を受け入れてもらい、コルサコフからアニワ湾に沿って東へ8km程のところにあるプリゴロドノエの海岸で、ゴムボートとダイバーの用意までしてくれました(写真3、4)。
この付近は切り立った崖が所々にある、平坦な岩場が続く海岸で、北海道北部にも分布する海藻(ミル、フクロフノリ、フシスジモク、スジメなど)が見られましたが、ヒバマタやネブトモクなど道北には分布しない海藻も見られ、より寒冷種の卓越する海藻植生であることが窺われました。 なお、サフニロの職員とその家族20名程で開いてくれた、海岸近くの丘の上にある展望台での野外パーティーでは、ロシアの伝統的な料理をご馳走になり、大変楽しい時間を過ごすことができました(写真5、6)。
(中央水試海洋環境部吉田英雄・嶋田宏、稚内水試資源増殖部赤池章一)




