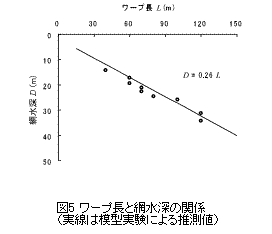漁具とは異なる採集具
はじめに
漁業では大型の魚を選択的に漁獲し漁場も限定されてしまうため、そこから得られる情報は実際の資源量を反映するとは断言できません。このため、近年では、卵、仔稚魚の分布調査や漁期前の調査から正確な資源の情報を得る試みが重要視されています。こういった調査に用いられる道具は、一般に採集漁具あるいは採集具と呼ばれます。ここでは、採集具のうちトロールのように綱で網を曳く曳網採集具について紹介します。
採集具に求められること
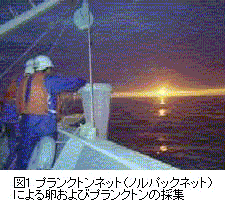
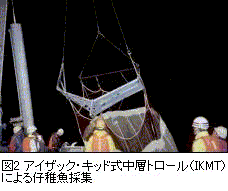
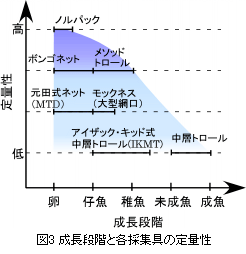
このように魚の成長段階にともない、網に対する回避能力が向上し定量性の保証が困難になることがわかります。各成長段階のうち、仔稚魚から未成魚のようなマイクロネクトンについては漁業において対象とすることがほとんどなかったことから、その生態的な情報がほとんど得られない状態でした。そして、その採集具も開発途上の段階でした。ここで,著者が昨年まで北大大学院で従事していた研究、マイクロネクトンを対象とした採集具フレームトロール(FMT:Framed Midwater Trawl、方形網口を有する中層トロール網)の開発研究について紹介します。
FMTの概要
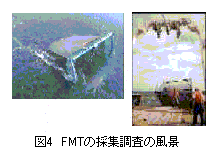
網口は一辺2~4 メートルの正方形、網長さ8~13 メートル、目合は稚魚を確実に網内に保持するためにすべて8 ミリメートルです。網には、曳網水深を船上で監視できる水深計、網の対水速度、網口の姿勢、水温等を計測する機器を設置することができます。
実際の調査では、稚魚や未成魚の採集のほかに、網の操作性に関する網の抵抗、網内流速といった物理的現象も調べました。その結果、FMTは、これまで同規模の曳網類を扱うことが出来る研究調査船ならば、ウインチの許容応力内で十分に使用が可能であること、水深40、50メートルまでの表中層の採集ではあらかじめ繰り出すワープの長さを図5の関係から推測できることがわかりました。また、採集調査では、これまで採集が非常に困難だったマイワシ、カタクチイワシ、サンマ、サバ類といった小型浮魚類の稚魚、未成魚の採集に成功しました(図6)。
FMTの特徴は定型網口、同一目合ということで、濾水量を算出でき、採集効率が分かれば、採集された稚魚の個体密度を推定することができます。FMTの目合は稚魚に対して十分に小さいので、FMTの採集効率を求めるには、入網率を把握すればよいのです。そこで、網の規模(網口面積)が異なる3つのFMTを用いて、曳網速度を3段階に設定した比較採集実験を行いました。その結果、曳網条件(面積、速度)、魚体長により、入網率が大きく異なることが明らかとなりました。そして、この入網率を定量化し採集効率を考慮することで、得られた採集物から実際にその調査海域に存在していた魚の分布密度を推定するという定量採集法を示すことができました。この定量採集法については、次回の機会にしたいと思います。
(中央水試 資源管理部 板谷和彦)