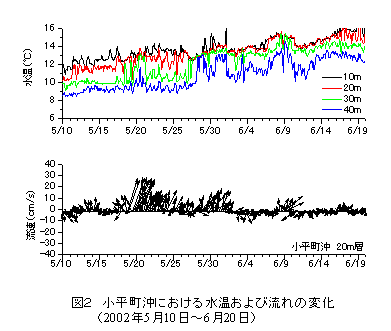ホタテガイ養殖漁場における水温と流れの変化 ~留萌沿岸ホタテガイ養殖漁場環境調査~
はじめに
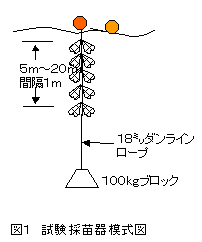
調査内容
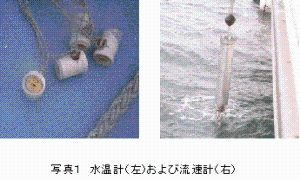
写真1 ヒトデ:正式な和名はキヒトデ
水温や流れの変動を引き起こす原因はいくつかあります。一般的なものとしては、まず潮汐による変動が考えられます。これは、主に半日や1日程度の周期で海面が上下動することによって起こるものですが、太平洋に比べて日本海の潮汐はそれほど大きくありません。次に、低気圧の通過や台風による風の影響があげられます。数日周期で変動するような水温や流れの変化は、風の変動によって引き起こされている可能性があります。また、沖側の流れの変化が沿岸域に影響を与えることも考えられます。このような観点に基づいて、今回の調査で得られた小平町沖のデータの一部を以下に紹介したいと思います。
小平町沖における調査結果(2002年5月10日~6月20日)
図2は、水温と流れの変化を1時間平均値を用いて表したものです。上の図は、10メートル層から40メートル層までの水温の変動を表しています。下の図は、流速ベクトル図と呼ばれるもので、矢印の向きが流れの方向を、矢印の長さが流れの大きさを示しています。ここでは上向きが北を表しており、3時間ごとにデータを抜きだして示しています。水温の変化を見ると、1日以下の短い周期の変動と、それとは異なった数日周期の変動が重なっていることがわかると思います。例えば、5月18日から5月21日に注目すると、20メートル層と30メートル層の水温が10メートル層と同じ約13℃まで上昇し、40メートル層の水温も11℃位まで上がっているのがわかります。このときの流れがどうなっているかを見ると、その前後の期間に比べて北北東へ向かう流れが強くなっている傾向が見らます。
今後は、上述の水温や流れの変動を引き起こす要因を解析した上で、ホタテガイの浮遊幼生数や試験採苗器で得られた採苗数の変動との関係を明らかにしていきたいと思います。
(中央水産試験場 水産工学室 中山威尉)
(中央水産試験場 水産工学室 中山威尉)