ホッケは未成魚期から漁獲の対象になっており、魚体の大きさや成長に伴う生態の変化に合わせ、様々な漁法により漁獲されています。
沖合底びき網漁業
底生生活へ移行した直後の秋から、沖合底びき網漁業(以下、沖底)による漁獲が始まります。
1980年代後半までは、道北日本海~オホーツク海(以下、道北海域)における沖底による漁獲物は、0~1歳魚がほとんどでしたが、1990年代は2歳魚以上みられる大型魚も多く漁獲されていました。
2000年前後からまた0~1歳魚主体の漁獲に戻っています。
1990年代以降の道北海域の漁獲量に占める沖底の割合は、1992年を除き常に総漁獲量の7割を超えています。 沖底の漁獲量そのものは1998年には16.8万トンまで増加しましたが、その後減少し、2002年は約8.4万トン(ただし、暫定値)でした。
1990年代以降の道北海域の漁獲量に占める沖底の割合は、1992年を除き常に総漁獲量の7割を超えています。 沖底の漁獲量そのものは1998年には16.8万トンまで増加しましたが、その後減少し、2002年は約8.4万トン(ただし、暫定値)でした。
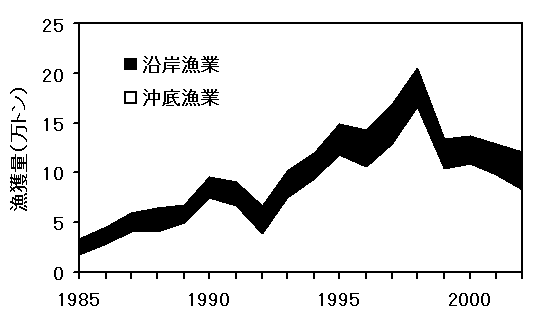
図 道北~オホーツク海域におけるホッケ漁獲量
刺し網漁業
利尻島・礼文島では、刺し網によるホッケの漁獲が盛んに行われています。
刺し網漁業の漁獲対象は、主に満2歳以上のホッケと考えられています。
漁獲量は、近年では年間6千トン前後に達しています。2002年の漁獲量は、6.8千トンでした。
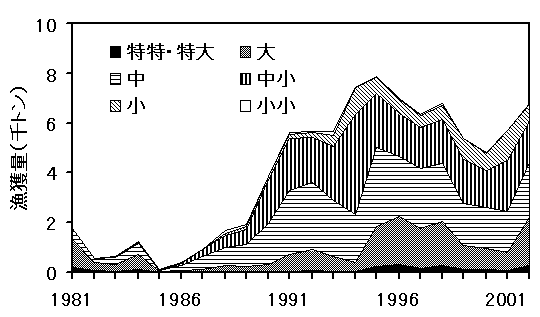
図 利尻・礼文地区における刺し網漁業によるホッケ漁獲量
底建網漁業
オホーツク海の沿岸漁業では、ホッケの大部分が底建網漁業(定置網漁業を含む)により漁獲されます。
6月をピークとする春漁では1歳魚を主体に、11月がピークの秋漁では0歳魚が主に漁獲され、年間漁獲量は1万トン前後に達します。
利尻島・礼文島でも底建網漁業によりホッケが漁獲されており、1980年代後半から1990年代にかけて年間2千トン前後が漁獲されていましたが、2000年前後から約1千トン前後の水揚げにとどまっています。
2002年の利尻・礼文地区における漁獲量は、570トンでした。
利尻島・礼文島でも底建網漁業によりホッケが漁獲されており、1980年代後半から1990年代にかけて年間2千トン前後が漁獲されていましたが、2000年前後から約1千トン前後の水揚げにとどまっています。
2002年の利尻・礼文地区における漁獲量は、570トンでした。
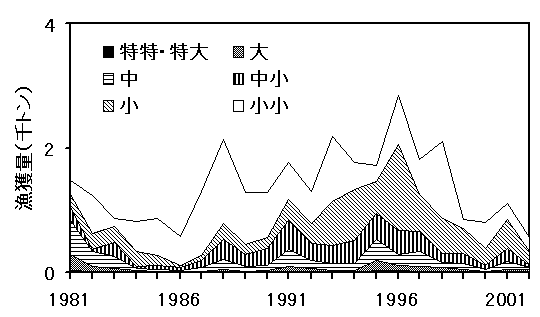
図 利尻・礼文地区における底建網漁業によるホッケ漁獲量
まき網漁業
満1歳のホッケは、春に餌の動物プランクトンを求めて表層近くまで群をなして浮上する性質があります。
このホッケの群を「ダマ」といいますが、利尻島沿岸ではこのダマを狙って、まき網漁業が行われています。
まき網漁業の漁模様はダマの出来・不出来に左右されますが、餌の動物プランクトンの量や分布も海況に依存することから、まき網漁業の漁獲量も年変動が大きいことが特徴です。
2001年には4年ぶりに「小」~「中」の銘柄も水揚げされましたが、2002年では再び「小小」ばかりが、約1.1千トン水揚げされました。
利尻・礼文地区では近年まき網漁業の着業隻数が減少しており(2003年5月現在で仙法志・沓形地区のみ3隻:稚内水試調べ)、1990年代後半からの漁獲量の減少は、資源変動よりも漁獲努力量の減少の影響を受けたものと考えられます。
2001年には4年ぶりに「小」~「中」の銘柄も水揚げされましたが、2002年では再び「小小」ばかりが、約1.1千トン水揚げされました。
利尻・礼文地区では近年まき網漁業の着業隻数が減少しており(2003年5月現在で仙法志・沓形地区のみ3隻:稚内水試調べ)、1990年代後半からの漁獲量の減少は、資源変動よりも漁獲努力量の減少の影響を受けたものと考えられます。
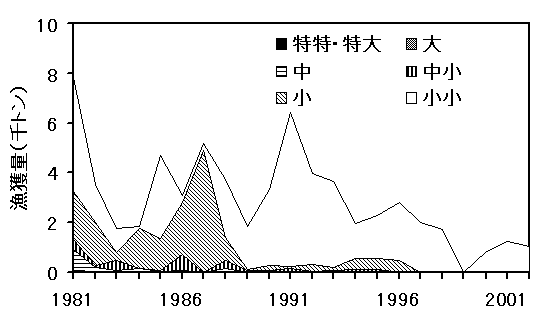
図 利尻・礼文地区におけるまき網漁業によるホッケ漁獲量
そのほか
漁業としてはわずかながら、ホッケは釣りや延縄によっても漁獲されています。
遊漁による釣獲物は、その大きさや釣れる場所から考えて、ほとんどが2歳漁以上と考えられます。
遊漁による釣獲物は、その大きさや釣れる場所から考えて、ほとんどが2歳漁以上と考えられます。

写真 礼文島で釣獲された”ジャンボ”ホッケ(1998,8)
お問い合わせ先
調査研究部 管理増殖グループ
- 住所:〒097-0001 稚内市末広4丁目5番15号
- 電話番号:調査研究部(直通):0162-32-7166
- ファックス番号:0162-32-7171
