二シンの体外標識比較試験について
今年は北海道の日本海中部以北の海域に約40万尾のニシン人工種苗が放流されました。これらのニシンは、放流魚であることを示すためにALCという薬品で耳石に標識しています。ALCは大量の種苗を外傷なしに標識できるため、ニシンのように弱い魚種にも有効です。しかし、体内標識であるため外見的には天然魚と区別がつかず、漁業者や遊漁者からの再捕報告は期待できません。放流魚を発見するためには大量のニシンから耳石を取り出す必要があるうえに、標識を確認するには、ALCの蛍光を励起し、検出できる蛍光顕微鏡を用いなければなりません。
稚内水産試験場では、ALC標識に加えて、体外標識放流の技術開発に取り組むことにしました。そのためにはまず、標識装着時の外傷による死亡率と標識の脱落率を調べる必要があります。そこで平成8年に陸上水槽で試験を行いましたので、その結果について紹介します。
稚内水産試験場では、ALC標識に加えて、体外標識放流の技術開発に取り組むことにしました。そのためにはまず、標識装着時の外傷による死亡率と標識の脱落率を調べる必要があります。そこで平成8年に陸上水槽で試験を行いましたので、その結果について紹介します。
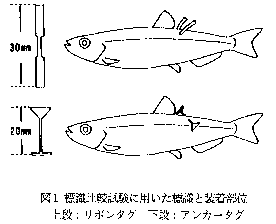
リボンタグの有効性
試験の結果を表1に示しました。飼育期間中の死亡は少なく、アンカータグ3尾、リボンタグ4尾、対照群2尾で、生残率はいずれも98パーセント以上でした。装着作業が生残に及ぼす影響は小さかったと考えられました。
標識脱落率はアンカータグが27.4パーセントと高かったのに対し、リボンタグではわずか2.1パーセントでした。アンカータグ装着魚は30日後でも傷が埋まっていないものが多くみられ、脱落の原因になったようです。試験終了時のニシンの平均全長は、アンカータグ魚13.8センチメートル、リボンタグ魚13.9センチメートル、対照群13.6センチメートルで、これらの間に有意な差は見られませんでした(危険率5パーセント)。少なくとも短期間には、標識装着や標識種類が成長に大きく影響することはないようです。
表1 標識比較試験における標識区分別生残率及び標識脱落状況
今回の試験で、30日間の標識脱落状況は把握できましたが、今後は半年や一年間といった長期の脱落率も試験する必要があります。また、早期に体外標識放流を行うために、さらに小型の種苗を用いて装着試験を行う必要もあります。
標識脱落率はアンカータグが27.4パーセントと高かったのに対し、リボンタグではわずか2.1パーセントでした。アンカータグ装着魚は30日後でも傷が埋まっていないものが多くみられ、脱落の原因になったようです。試験終了時のニシンの平均全長は、アンカータグ魚13.8センチメートル、リボンタグ魚13.9センチメートル、対照群13.6センチメートルで、これらの間に有意な差は見られませんでした(危険率5パーセント)。少なくとも短期間には、標識装着や標識種類が成長に大きく影響することはないようです。
表1 標識比較試験における標識区分別生残率及び標識脱落状況
| 9月17日 試験開始時尾数 |
期間中 斃死尾数 |
10月17日 標識保持尾数 |
標識 脱落尾数 |
生残率 | 標識 脱落尾数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカータグ装着群 | 204 | 3 | 146 | 55 | 98.5% | 27.4% |
| リボンタグ装着群 | 199 | 4 | 191 | 4 | 98.0% | 2.1% |
| 対照群 | 160 | 2 | 158 | - | 98.8% | - |
| 合計 | 563 | 9 | 495 | 59 | 98.4% | 17.5% |
今回の試験で、30日間の標識脱落状況は把握できましたが、今後は半年や一年間といった長期の脱落率も試験する必要があります。また、早期に体外標識放流を行うために、さらに小型の種苗を用いて装着試験を行う必要もあります。
おわりに
以上の結果を受けて、平成9年3月に石狩地区水産技術普及指導所が中心となって黄色リボンタグ(97ハママス)を装着したニシン種苗1,000尾を浜益沖に放流しました。また水産試験場では、平成9年10月に羽幌海域で赤色リボンタグ3,000尾の標識放流を予定しています。これらの標識魚が数多く再捕されれば、放流後の移動傾向や分布について多くのことが分かります。標識魚を見つけた方は最寄りの水産技術普及指導所や水産試験所までお知らせ下さいますようお願いします。
(北海道立稚内水産試験場 資源増殖部 吉村圭三)
