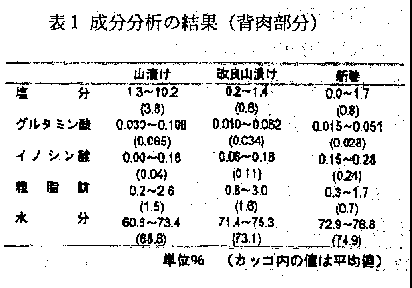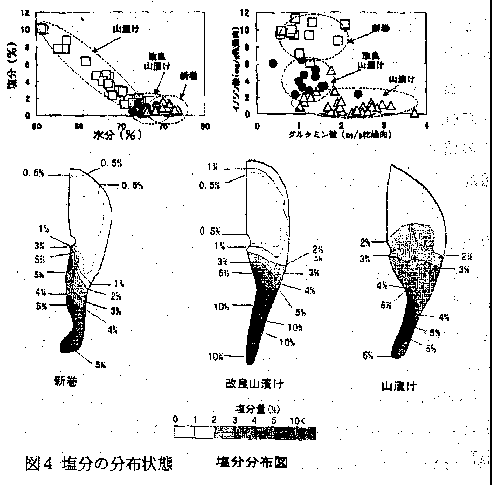おいしい秋サケ塩蔵品をめざして
はじめに
最近、みなさんは塩サケを食べましたか?総務庁の統計によると平成8年の塩さけの消費量は年間で一人平均約700グラム。切り身では7~8切れほどです。
これは10年前の半分程度ですから、塩サケが消費低迷を招いた原因には、「食の多様化」とか、「グルメ指向」などが考えられます。こうした消費者ニーズにこたえるため、釧路水産試験場では今年度から「塩サケのおいしさを増進することで消費拡大を図る」ことを目的に、従来の塩蔵法を再検討し、低コストでしかも食べておいしい、新しい塩蔵法の開発試験に取り組み始めました。
今回はこの研究の手始めとして市販の秋サケ塩蔵品を対象に、成分特性と塩分分布について分析したので紹介します。
これは10年前の半分程度ですから、塩サケが消費低迷を招いた原因には、「食の多様化」とか、「グルメ指向」などが考えられます。こうした消費者ニーズにこたえるため、釧路水産試験場では今年度から「塩サケのおいしさを増進することで消費拡大を図る」ことを目的に、従来の塩蔵法を再検討し、低コストでしかも食べておいしい、新しい塩蔵法の開発試験に取り組み始めました。
今回はこの研究の手始めとして市販の秋サケ塩蔵品を対象に、成分特性と塩分分布について分析したので紹介します。
秋サケの主な塩蔵方法と特徴
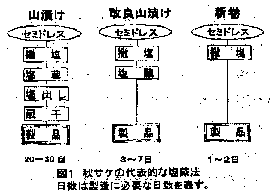
このうち、山漬けは「塩引き」とも言われ、1000年以上の歴史をもつ伝統的な製法です。その製造方法も各地各様で、塩出しの工程を2回繰り返したりと、様々なバリエーションがあります。
分析した塩蔵秋サケ製品
分析には平成8年9月から12月にかけて製造され、-30度で凍結保管された山漬け5種、改良山漬け2種、新巻2種を用いました。
塩蔵秋サケ製品の成分特性
表1に成分特性の分析結果をまとめました。また、これらの結果をグラフにすると興味深い結果が得られました。すなわち、水分と塩分の間には(1)水分が多く塩分が少ない新巻グループ、(2)その逆の山漬けグループ、そして(3)改良山漬けグループと、製法ごとに3つのグループに分かれました。
さらに山漬けグループでは高水分の製品ほど塩分が少なくなる関係がみられました(図2)。
こうしたグループ分けはグルタミン酸とイノシン酸の間にも見つかりました。
すなわち(1)グルタミン酸が少なくイノシン酸が多い新巻グループ、(2)その逆の山漬けグループ、そして(3)改良山漬けグループと、ここでも3つのグループに分かれました(図3)。
さらに山漬けグループでは高水分の製品ほど塩分が少なくなる関係がみられました(図2)。
こうしたグループ分けはグルタミン酸とイノシン酸の間にも見つかりました。
すなわち(1)グルタミン酸が少なくイノシン酸が多い新巻グループ、(2)その逆の山漬けグループ、そして(3)改良山漬けグループと、ここでも3つのグループに分かれました(図3)。
塩蔵秋サケ製品の塩分分布
みなさんの中にも塩サケの切り身を食べたとき、腹肉は塩辛いのに背肉は塩が利いていない、という経験をされた方も多いのではないでしょうか。こうした切り身の塩分の分布状態を視覚的に表したものが図4です。これによると、腹肉部分ではどの製品も5パーセント以上の高塩分でしたが、背肉部分では山漬けと他の製品とでハッキリと違いがあらわれました。
すなわち、山漬けは2~3パーセントの塩分が一様に浸透していましたが、他の製品ではほとんど浸透していませんでした。
山漬けの背肉部分はちょうど良い「塩梅」であることがわかりました。
すなわち、山漬けは2~3パーセントの塩分が一様に浸透していましたが、他の製品ではほとんど浸透していませんでした。
山漬けの背肉部分はちょうど良い「塩梅」であることがわかりました。
おわりに
山漬けは手間と時間がかかり、大量生産には不向きな製法ですが、うま味成分の含有量や塩分分布などの点では、他の製法に比べ優れているといえそうです。
今後はこの山漬けの製法を参考にしながら、手間がかからず、しかもうま味が豊かな塩蔵法の開発に取り組んでいく予定です。
今後はこの山漬けの製法を参考にしながら、手間がかからず、しかもうま味が豊かな塩蔵法の開発に取り組んでいく予定です。
(釧路水産試験場 利用部 千原 裕之)