函館水試加工相談室情報 その2
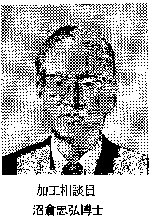
ここで、2代目相談員.の沼倉 忠弘博士を紹介します。博士は元北海道大学水産学部食品学科水産食品製造実習工場の助教授(水産学博士)で食品製造学が専門分野です。
相談内容の中から我々が普段目にする身近な疑問を4つほど載せてみました。
ウニが凍結貯蔵によって、黒ずみ、解凍によって生鮮時の状態に戻るのはなぜか?
ウニを凍結貯蔵すると、ウニ生殖巣に含まれる主な色素であるカロチノイド系色素が酸化や光によって退色する。一方、ウニ脂質に含まれる高度不飽和脂肪酸の酸化による褐変とウニ糖質のDーグルコースやD-リボースなどの還元糖が遊離のアミノ酸、ペプチド、タンパク質などのアミノ基と反応して起こる褐変が進行し、ウニ生殖巣が黒ずむ。
ウニ生殖巣は凍結・解凍すると「くずれ現象」が起こるがこれは生殖巣の表層膜が真水に対して弱く、凍結によって膨張して薄くなり、解凍時に氷の融解によって生じた低塩分の水とドリップ(解凍時に流出する液)によって破れるためである。この「くずれ現象」で内部の小細胞が流出する。また、膜の外側の上皮細胞と内部小細胞とがかたまりつき、これらの細胞の一部も破壊されて流出し、ウニ生殖巣の表面を覆う。
このため、ウニ生殖巣が外観的には生鮮時の色調に戻ったように見えるものと考えられる。退色したカロチノイド系色素や脂質の酸化ならびに精一アミノ反応で発生した褐変が凍結・解凍によって元の状態に戻ることはない。
【用語説明】
ウニ生殖巣は凍結・解凍すると「くずれ現象」が起こるがこれは生殖巣の表層膜が真水に対して弱く、凍結によって膨張して薄くなり、解凍時に氷の融解によって生じた低塩分の水とドリップ(解凍時に流出する液)によって破れるためである。この「くずれ現象」で内部の小細胞が流出する。また、膜の外側の上皮細胞と内部小細胞とがかたまりつき、これらの細胞の一部も破壊されて流出し、ウニ生殖巣の表面を覆う。
このため、ウニ生殖巣が外観的には生鮮時の色調に戻ったように見えるものと考えられる。退色したカロチノイド系色素や脂質の酸化ならびに精一アミノ反応で発生した褐変が凍結・解凍によって元の状態に戻ることはない。
【用語説明】
- カロチノイド系色素とは自然界に広く分布する水に不溶の黄色ないし赤色系統の色素で、代表的なカロチノイドとして橦色のβ一カロチンがある。
- 高度不飽和脂肪酸とは炭素鎖が長く(炭素数18以上)、不飽和度の高い(二重結合致2個以上)の脂肪酸で空気中の酸素を吸収して酸化しやすい。
- 還元糖とはグルコース、フラクトース、麦芽糖などアルデヒドあるいはケトン基を持つ糖をいう。
イカ乾燥珍味に混在する灰白色の粒子の正体はなにか?
イカ珍味に混在する灰白色の粒子は口の中に入れて噛むとざらつき、ほとんど溶解せず無味であることから主成分は無機質と考えられる。従って、調味料として使用した庶糖、アミノ酸類またはイカ肉中に多く含まれるタウリンなどが析出したものではない。原料のマイカに小魚や小型の貝殻が混入し、洗浄によっても完全に除去出来ない場合もあるとのことなので、恐らく、残存した小魚の骨や貝殻が製造の過程で砕けて製品の中に混入したものと考えられる。
【用語説明】
【用語説明】
- 無機質とは生体を構成する元素のうち炭素、水素、酸素、窒素以外のナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、リン、イオウなどの元素を無機質という。
子持ちシシャモを焼いたら卵の下部が緑変した。原因物質はなにか?
小型魚のシシャモは内蔵を除去せずに乾燥するので、製造過程で胆嚢が破れ流出した胆汁がシシャモの卵巣に付着したためと考えられる。脊椎動物の胆汁には緑色のビリベルジンと黄褐色のビリルビン(酸化されると緑色のビリベルジン複合体となる)を主要色素として含む。このため、魚卵などに胆汁が付着すると緑色に変色する。ハゼやカジカ類では卵巣が青色を帯びているものがあるが、これはビリベルジンータンパク質複合体によるものである。これらの魚卵は食用に供して問題はない。
また、マグロやサンマで骨が青いものが希に見いだされるがビリベルジンがガルシューム塩となって骨に沈着したものであることがわかっている。
また、マグロやサンマで骨が青いものが希に見いだされるがビリベルジンがガルシューム塩となって骨に沈着したものであることがわかっている。
料理の素材として生鮮サケを利用するが、サケの栄養成分として特に強調すべき点はなにか?
赤身魚の赤色はミオグロビン(鉄分とタンパク質が結合したヘムタンパク質の一種)の色によるが、サケ肉のピンク色はアスタキサンチン(カロチノイドの一種)を含むためである。これはビタミンA効力を有するだけでなく、免疫機能強化、ある種のガン細胞の抑制効果もあることが解っている。また、サケ肉の脂質に比較的豊富に含まれるDHAやEPAには学習能力向上作用、制ガン作用、血中コレステロール低下作用、抗血栓作用、抗アレルギー作用その他優れた生理活性機能を有することが示されている。
(函館水試 企画総務部 主査 阿部 剛)
