食べる習慣のない食用貝の話
1.はじめに
食用にされない理由は、歴史的、経済的理由等いろいろあると思われますが、日本の食習慣という文化的な理由、単に「食べなれていない」というのが一番大きいように思われます。ここでは、そんな貝類のうちで、北海道に生息している幾つかの二枚貝類を、図をまじえて、紹介したいと思います。
2.ホトトギスガイ(写真1)
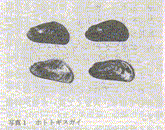
北海道ではオホーツク海側のサロマ湖、能取湖、藻琴湖のような汽水湖に分布しています。泥底に足糸と呼ばれる、糸状の分泌物で付着し、群生する長さ2センチメートルほどの小型のイガイ科の二枚貝です。北海道でも食用にされる大型のイガイやエゾイガイの親類ですが、まったく見向きもされない存在です。実は熱帯にあるタイでは非常に重要な食用貝類であり、やや古いそすが、FAOの統計では、1986年に7,500トンの漁獲量が報告されています。
この小さな二枚貝を多数漁獲して、食用にする手間を考えると、日本では漁業として成り立ちにくいかもしれません。
3.ビノスガイ類(写真2)
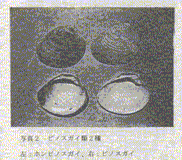
北海道周辺の浅海の砂泥域に分布する10センチメートル程に達する、大型の白い二枚貝で、マルスダレガイ科に属し、アサリやハマグリの親戚です。この貝の名前のピノスはヴィナスからとられたもので、「美之主」と当て字されています。外見上は名前負けですが。
ビノスガイはホッキ漁場の混獲物によく見られますが、北海道では食用とはされていません。アメリカやカナダには、近縁種のホンビノスガイ(写真2左)が分布しており、数万トン規模で漁獲される重要水産種です。FAOの統計では、1995年に45,933トンの漁獲量がありました。
現地では、培養殖に関してかなり研究されており、人気のある食用二枚貝です。種は違いますが、日本のビノスガイも近い種類ですから、漁業成立の可能性もあるのかもしれません。
4.オオノガイ類(写真3)

北海道周辺の浅海の砂泥域、特にサロマ湖、能取湖、風連湖、厚岸湖のような干潟の発達した汽水湖に多産する大型の二枚貝類です。本州では有明海のような干潟に多産します。オオノガイ(写真3下右)、キタノオオノガイ(写真3上右)、エゾオオノガイ(写真3上左)の3種類分布しており、いずれも砂泥底に深く潜って生活しており、大きくて長い水管が特徴です。
ヨーロッパ、アメリカ、カナダに分布する、近縁種のセイコウオオノガイ(写真3下左)が漁獲されており、FAOの統計では、1995年に8,510トンの漁獲量がありました。
日本で食用にされるミルクイガイやナミガイと同様に発達した大きな水管が食用となり、現地では好まれているようです。
ちなみにエゾオオノガイは北極海にも分布しており、大型海産ほ乳類のセイウチのエサとしても有名です。
(網走水試 資源増殖部 桑原康裕)
