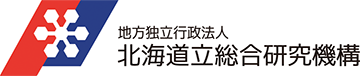イトウの保護も一支流から(イトウだって母川回帰)
サケ科魚類の多くが生まれた川に産卵のため戻ってくることは、皆さんすでにご承知のことと思います。幾多の苦難を乗り越えてようやく生まれた川にたどり着き、産卵を終えて死んでゆく姿は、私たちに生きることの不思議さと感動を与えずにはおきません。生まれ育った古里に戻ると言った響きを持つこの「母川回帰性」に、私たちは特別な感情を抱いてしまうようです。
昨年公表された「北海道の絶滅のおそれのある野生生物リスト」で、近い将来極めて高い確率で野生種の絶滅が懸念される種「絶滅危機種」にランクされたイトウも、そんなサケ科の仲間です。1メートルを越えることも珍しくないこの淡水魚は、かつてはよく海まで出て、北海道沿岸各地のサケ定置網で漁獲されていたようですが、今では海で漁獲されるのは道北の一部のみと言っても良いでしょう。しかしイトウもサケ科の魚ですので、産卵はやはり支流や本流の上流域で行われます。春の雪解けが終わる頃、彼らは一斉に上流に遡上し、細流に入り込んで産卵するのです。産卵生態が似かよっていることから、イトウにも母川回帰性があるかもしれないと言うことは以前から考えられていました。しかし、イトウの場合卵から孵化して稚魚として河川生活を始めるとすぐ、多くの個体が生まれた支流から本流へ移出して、カバーのある本流の脇や小さな細流に入り込んで生活し、永く生まれた支流に留まって生活する個体はほとんどいません。したがって生まれた川の記憶と言う点からは、イトウの母川回帰性に疑問が持たれていたのです。最近になってようやく北海道大学と水産孵化場の共同研究を通じ、イトウにも各支流ごとの母川回帰性があることが明らかになってきました。
昨年公表された「北海道の絶滅のおそれのある野生生物リスト」で、近い将来極めて高い確率で野生種の絶滅が懸念される種「絶滅危機種」にランクされたイトウも、そんなサケ科の仲間です。1メートルを越えることも珍しくないこの淡水魚は、かつてはよく海まで出て、北海道沿岸各地のサケ定置網で漁獲されていたようですが、今では海で漁獲されるのは道北の一部のみと言っても良いでしょう。しかしイトウもサケ科の魚ですので、産卵はやはり支流や本流の上流域で行われます。春の雪解けが終わる頃、彼らは一斉に上流に遡上し、細流に入り込んで産卵するのです。産卵生態が似かよっていることから、イトウにも母川回帰性があるかもしれないと言うことは以前から考えられていました。しかし、イトウの場合卵から孵化して稚魚として河川生活を始めるとすぐ、多くの個体が生まれた支流から本流へ移出して、カバーのある本流の脇や小さな細流に入り込んで生活し、永く生まれた支流に留まって生活する個体はほとんどいません。したがって生まれた川の記憶と言う点からは、イトウの母川回帰性に疑問が持たれていたのです。最近になってようやく北海道大学と水産孵化場の共同研究を通じ、イトウにも各支流ごとの母川回帰性があることが明らかになってきました。
イトウの母川回帰
1997年春。金山人工湖上流、空知川のある支流での産卵はとてもにぎやかでした。1週間ほどの産卵期になんと13尾もの雌が遡上産卵したのです。一尾の雌があちこちで産卵するので、限られた人数ではとても総ての産卵行動が観察できず、予定したデータが取れませんでした。そこでその13尾の雌の総てに個体識別可能な標識を施して再放流したのです。イトウはサケと違って1度の産卵では死なずに何年も産卵するので、また同じ魚が産卵のためこの川に上ってくるかもしれません。ところが翌1998年は対照的に、この支流には雌が1尾も遡上しないという残念な結果になってしまいました。でも、このようなことは過去にも何度かあったことなのです。そして1999年。この年は3尾の雌がこの支流に遡上してきました。そしてその総てが標識魚だったのです。さらに2000年には雌は全部で10尾この支流に遡上してきましたが、そのうち6尾が標識魚でした。さらにこの中には2年続けて遡上した雌も1尾いたのです。これだけでも母川回帰性があると言えそうですが、他の総ての河川への標識魚の遡上状況について調査していませんので、これだけでは母川回帰性があるとは言えません。偶然に遡上魚の多くが標識魚だったのかもしれないのです。偶然にそのようなことが起こる確率を調べる必要があります。それには年度ごとに人工湖上流域で遡上産卵した雌の総数を知る必要があります。幸いにも本水系では総ての産卵床を数えて、産卵雌親魚数を推定する技術がすでに15年ほど前に確立されています。そこで1999年と2000年に水系内の総ての産卵床を徒歩で数え上げて雌の親魚数を推定しました。結果は1999年37尾、2000年44尾と推定されました。
偶然に多くの標識魚が遡上する確率
確率の計算は以下のように考えました。全部で37尾の雌親魚がいてその中に13尾の標識魚が混じっていたとします(1999年)。その37尾の中から勝手に3尾の魚を取りだした時、3尾とも総て標識魚である確率(1999年)。ないし13尾の標識魚を含む44尾の中から勝手に10尾取りだしたとき、その中に6尾以上標識魚が混じっている確率(2000年)。これが偶然に起こる確率です。
計算の結果このような確率は1999年は3.7パーセント、2000年は2.5パーセントと計算されました。両年とも極めて低い確率です。つまり偶然こんなに多くの標識魚が混じることはほとんど無いと言うことになります。したがって偶然ではなく、彼らは選んで上ってきたと言うことになるでしょう。さらにこの計算にはいくつかの前提があります。一つは1997年に標識した13尾の魚はすべて2000年まで生き残っていたと言う前提。今一つはこの13尾が両年とも総て成熟して産卵遡上したと言う前提です。現実には13尾のうちの何匹かは死んでいるでしょうし、成熟しなかった魚もいると考えられるので、この確率はもっと低い可能性が高いのです。本水系には物理的障害が無いにも関わらず、絶滅して資源が回復しない支流が複数存在することを考え合わせると、イトウの雌は母川回帰性が強いと判断されるのです。
計算の結果このような確率は1999年は3.7パーセント、2000年は2.5パーセントと計算されました。両年とも極めて低い確率です。つまり偶然こんなに多くの標識魚が混じることはほとんど無いと言うことになります。したがって偶然ではなく、彼らは選んで上ってきたと言うことになるでしょう。さらにこの計算にはいくつかの前提があります。一つは1997年に標識した13尾の魚はすべて2000年まで生き残っていたと言う前提。今一つはこの13尾が両年とも総て成熟して産卵遡上したと言う前提です。現実には13尾のうちの何匹かは死んでいるでしょうし、成熟しなかった魚もいると考えられるので、この確率はもっと低い可能性が高いのです。本水系には物理的障害が無いにも関わらず、絶滅して資源が回復しない支流が複数存在することを考え合わせると、イトウの雌は母川回帰性が強いと判断されるのです。
イトウ保護の考え方
イトウにも支流ごとの母川回帰性があるという事実は本種の保護を考える際に決定的に重要です。通常は金山人工湖の中で一緒に暮らしてはいますが、本当は支流ごとに別々の繁殖集団を形成していて、おのおの独立に子孫を残していることになるのです。しかも子供が育つ課程では河川生活を始めて間もない時期から、みんなが一緒になって生活します。他の降海性を持ったさけますの仲間と同様、イトウはこの2重構造をそれも比較的狭い水域の中で持っているのです。産卵河川での生活があまり長くない稚魚期の生態から考えると、一本の小支流でのイトウ資源の消滅は、見かけ上資源の大きな減少をもたらさないかもしれません。しかし個体群の内部ではもはや回復不能な遺伝的多様性の減少をまねき、本来環境変動の大きい淡水域での生態的な適応性を狭めることになります。こうした支流単位での個体群の消滅をも絶滅と表現するならば、今でも着々とイトウの絶滅は続いていると言ってもいいでしょう。この支流一本ぐらいと言う考え方が次々と支流の個体群を絶滅に追いやり、長い生活史と母川回帰性のため短期間での回復は極めて困難で、気が付いたときにはもはや水系全体が「風前の灯火」となってしまっているケースが道内あちこちで見られています。
イトウの保護を考える際、その水系の全生息数の変動を問題にするのは当然ですが、同時に水系内での繁殖集団の数と質を問題にする必要があります。1~2の主要な産卵場所とそれに連なる広い範囲の稚魚の生息場所の保護によって、当面の生息数の維持は可能かもしれませんし、場合によっては一時的増加をもたらすことすらあるかもしれません。しかしそのような個体群は突発的な事件、例えば病気の蔓延や長期にわたる環境の悪化などによって簡単に絶滅してしまう可能性を持っています。イトウは細く長く生きるタイプの魚として進化し、生き残って来ました。数を犠牲にしてでも多様性を選んだのです。一本の支流のイトウを保護することが、その水系全体のイトウを保護することに繋がるのです。
イトウの保護を考える際、その水系の全生息数の変動を問題にするのは当然ですが、同時に水系内での繁殖集団の数と質を問題にする必要があります。1~2の主要な産卵場所とそれに連なる広い範囲の稚魚の生息場所の保護によって、当面の生息数の維持は可能かもしれませんし、場合によっては一時的増加をもたらすことすらあるかもしれません。しかしそのような個体群は突発的な事件、例えば病気の蔓延や長期にわたる環境の悪化などによって簡単に絶滅してしまう可能性を持っています。イトウは細く長く生きるタイプの魚として進化し、生き残って来ました。数を犠牲にしてでも多様性を選んだのです。一本の支流のイトウを保護することが、その水系全体のイトウを保護することに繋がるのです。
(水産孵化場・病理環境部・主任研究員 川村洋司)
-
-

イトウの親魚
-
-
-

イトウの産卵河川
-