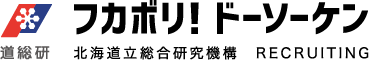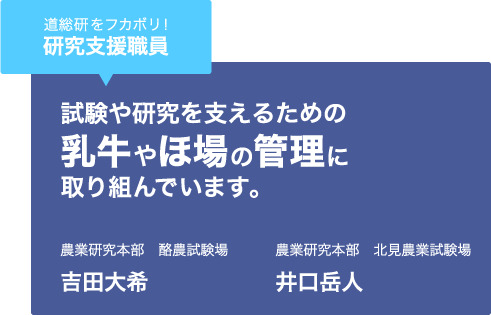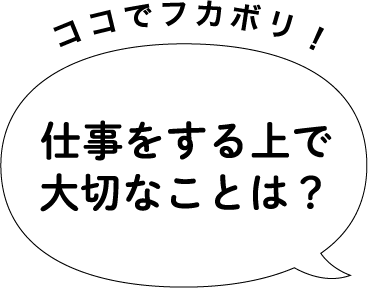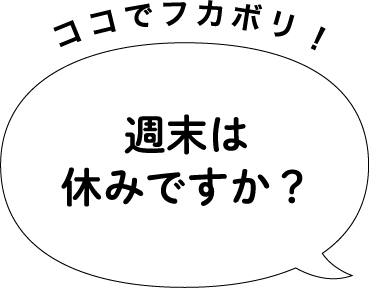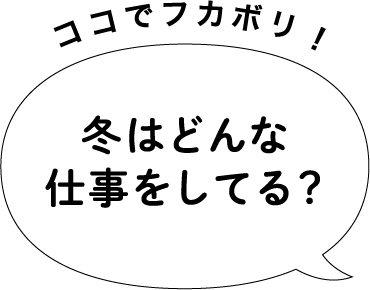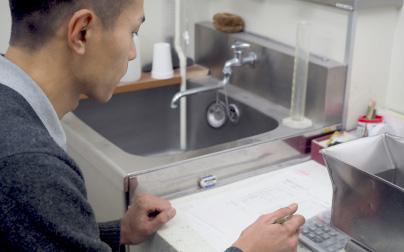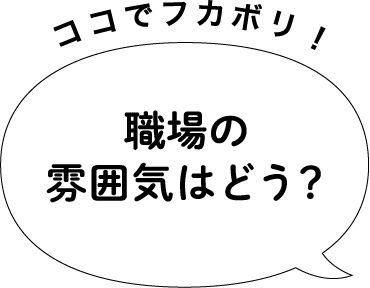現時点では変更となっている場合があります。
吉田さんが語る「支援職員」家畜管理のシゴト
飼料配合のほか搾乳さらにデータ収集まで。
高品質な牛乳の生産を支える縁の下の力持ちです。
酪農試験場は、酪農に関する総合的な試験研究を行い、環境に配慮した低コストで安全・高品質な牛乳の生産技術の開発を進めています。
この試験場には現在18名の支援員が所属し、各々担当や役割を分担しながら効率のよい業務体系を作り上げています。私は乳牛グループに所属する支援員。 乳牛の健やかな生育を支えるために飼料調整をメインに担当していますが、定期的な搾乳作業にも取り組みます。また研究のバックデータとなる乳量や体重の測定、健康状態のチェックさらに機械設備のメンテナンスなども大切な仕事です。
もともと動物が好きなこともあり、仕事はとても楽しいです。特に仔牛を見てると心がほっこりしますよ。縁の下の力持ち的な立場ですが、自分たちの日々の業務の積み重ねが北海道の安全でおいしい牛乳を支えていると思うとやりがいも感じますし、誇らしい気持ちにもなります。
飼料の調合に関しても乳量の測定に関しても、すべて研究者の指示やマニュアルに則り、正確に行うということ。そこで得られた数値や結果が、試験や研究結果を大きく左右するケースもありますから。僕らの仕事は酪農ではなく、あくまでも研究の支援なんです。
私の「例えばの」一日
一日の大半を牛舎で過ごします。
- 8:20
- マイカーにて出勤
- 8:45
- 朝礼
- 9:00
- 支援員のミーティング
- 9:30
- 飼料調整、給餌
- 12:00
- お昼ごはん
- 13:00
- 機械のメンテナンス
- 15:00
- 休憩
- 15:30
- 牛舎内の清掃/乳牛体重測定
- 17:00
- 研究員との打ち合わせ
- 17:30
- 退所
乳牛は生き物。一日でも給餌や清掃を欠かすことができませんし、しばらく目を離している隙に体調を崩すかもしれません。なので、支援員の仕事は基本的には365日なんです。とはいっても自分たちにも休みは必要。交替で休日や休暇を取るようにしています。もちろん休みの日数は公務員と同程度あります。
上司からエール!
道総研の研究は、研究者と支援員の共同作業。
北海道の牛乳がおいしいのは、
彼のような仕事熱心な支援員がいるから。
この試験場では、研究用に150頭の乳牛と10頭の綿羊を飼育しているのですが、その管理はほぼ支援員の方に委ねられています。研究員の指示や要望に的確に応えていただくことが支援員の役割ではありますが、逆に支援員の方々がいなければ自分たちの研究は進みません。一言で表すなら「必要不可欠なパートナー」ですね。
酪農試験場の支援員の業務は、搾乳、繁殖、飼料、保育に大別され、それぞれ担当制で取り組まれています。吉田さんには飼料調整を担当していただいています。仕事ぶりは非常に真面目。作業手順や機械の操作などを覚えるのも早く、さらに研究員との対話力も高いなど、支援員としての基本的な資質を充分備えていると感じます。また支援員は22歳から55歳と年齢層が幅広いのですが、彼はその中間の年齢。ベテランと新人とのパイプ役として職場を盛り上げてくれる頼もしい存在ともなっています。
北海道の牛乳がおいしいのは、彼のような仕事熱心な支援員がいるからこそ。ますますの活躍を期待しています。
井口さんが語る「支援職員」ほ場管理のシゴト
北見農試のほ場を管理するという
責任の大きな仕事。
研究員の感謝の言葉に
よろこびとやりがいを感じています。
ここでお世話になる前は、新得町の畜産試験場で契約職員として勤務していました。そこで道総研の試験場での仕事の楽しさや待遇面のよさ、将来の安定性にも魅力を感じ、2013年9月に道総研の採用試験を受けさせていただきました。
北見農業試験場は、麦類、馬鈴薯、てん菜などの畑作物と牧草に関する試験研究のほか、オホーツク地域の農業に対応した試験研究などにも取り組んでいます。
私の所属は、研究部麦類グループです。トラクターなどを駆使し、春の畑おこしから肥料の散布、畝づくり、播種さらに秋の収穫までの農作業に取り組んでいます。農家の方との違いは、畝の作り方や肥料の量、薬剤散布の方法まで、研究員の指示に沿って行うということ。さらに多彩の研究のために、ほ場環境や農業機械の整備を常にベストの状態に整えておくことも大切な仕事です。
支援員は現在4名。このメンバーで北見農試の広大なほ場を管理しているため、一人ひとりの存在や役割はとても大きいと感じています。また「いつもありがとう」「頼りにしています」といった研究員の方々からの感謝の言葉もやりがいやモチベーションにつながっています。
ほ場の除雪、機械や道具のメンテナンス、春にまく肥料の調整、秋に収穫した麦の製粉やその小麦をパンや麺に仕上げるという作業も。もちろんこれらも研究の一環なので研究員との共同作業になるケースもあります。冬だからヒマ…ということは残念ながらないのです。
私の「例えばの」一日
大切なのは経験を重ねることです。
- 8:00
- マイカーにて出勤
- 8:30
- 朝礼
- 8:40
- 研究員・支援員の会議
- 9:30
- 薬剤散布
- 12:00
- お昼ごはん
- 13:00
- ほ場管理
- 15:00
- 休憩
- 15:30
- 機械メンテナンス
- 17:00
- 研究員とのスケジュール共有
- 17:45
- 退所
ここで働き始めた一年後に結婚したのですが、北見農試の全職員でお祝いの宴を開催してくれたんです。新人の自分のためにわざわざ…と、胸が熱くなりました。研究員と支援員、さらに部署の壁も全く感じないアットホームな職場。この雰囲気のよさが働きやすさを生み出しているのだと思います。
上司からエール!
この試験場に欠かせないキーパーソン。
新人支援員や我々研究員に
アドバイスしてくれることも。
現在北見農試には4人の支援員が所属し、試験や研究のための畑の管理や整備などに取り組んでいただいています。それらは特殊機械で行う場合もあれば、肥料散布や種蒔きなどの細かな配慮が必要となるものは手作業になるケースも。なので支援員として成長していくために欠かせないものは先輩からの指導と毎年の経験ということになります。
通常は5〜10年程度の歳月をかけて、ほ場管理のノウハウや機械の操作法を覚えていくのですが、井口さんの場合は、勤務してまもなくベテランの方が引退してしまったため、わずか3年で“独り立ち”ということに。相当苦労されたはずですが、持ち前の明るさと熱心さで、あっという間に頼れる中堅支援員に成長してくれました。さらに最近入所した新人支援員の指導者としても、辣腕を振るっていただいています。
私たち研究員も、彼からアドバイスや提案を受けることも日常茶飯事。この試験場に欠かせないキーパーソンだと感じています。
なんでもQ&A
その質問、センパイが教えます。
- 働いて一番
うれしかったことは? - 吉田さん:息子が「僕も大きくなったら農業試験場で働く」と言ってくれた時ですね。それは多分、私が支援員の仕事は楽しいよといつも口にしているからでしょう。「仔牛が生まれた」とか「いい飼料ができた」ってね。息子もそんな楽しいところなら働きたいって思ったのかも。もちろん応援するつもりです!
- どんな人が
支援員に向いてる? - 吉田さん:ベテラン支援員の指導に耳を傾け、さらに研究員の方の要望に一つひとつ応えていくような、地道で実直なタイプが向いていると思います。逆に「自分勝手」「面倒くさがり」な方は、残念ながら不向きかも。もちろん農業や酪農に関心がある、野外ので働くのが好きというのは大前提だと思います。
- 農家や酪農家
との違いは? - 井口さん:農家や酪農家の場合はコストや効率を見据えながら、質が高く安全でおいしい農産物や牛乳をできるだけ多く生産し、利益を上げていくことが重要です。一方支援員の場合は、作業こそ農家や酪農家と似ていますが、研究員の指示通りのほ場をつくり、肥料や飼料を調整し、正確なデータを得られるようサポートしていくことが重要になります。
- 支援員として
欠かせない資質は? - 井口さん:コミュニケーション能力だと思います。ほ場や牛舎での仕事が多いため、体力や行動力が重視されそうですが、研究員の方との会話や打ち合わせ、あるいは支援員同士での連携や情報交換は、仕事を円滑に進める上で不可欠な要素。どなたともしっかりコミュニケーションを図れるということが一番大切なんです。
道総研のココがいい!
資格取得のバックアップや
家賃補助さらに
充実の休日休暇など
とても働きやすい職場です。
支援員の仕事はトラクターや除雪車などを扱うことも多いのですが、道総研の費用負担のもと「クレーン」「玉掛け」などの講習会への参加も支援してくれます。もちろん操作になれるまでベテラン支援員に指導していただけます。
決まった休日に加え、GW・年末年始・お盆時期の長期休暇、さらに有給の年休が20日間あったり、住居手当があったりと待遇には本当に満足しています。オンとオフを切り換えやすいので、家族がいる方などは特に働きやすいと思います。