3. 北海道の湖沼の水質特性
塩分環境から見た湖沼型
サロマ湖(汽水)
網走湖(汽水)
厚岸湖(汽水)
十勝海岸の長節湖(汽水)
北海道には海岸付近に存在する湖沼が多くあり、地形的な要因などによって海水が湖内に進入し、湖水の塩分濃度が高くなっているものも少なくない。陸水(淡水)と海水が混ざり合っている水域を「汽水域」といい、湖の場合は「汽水湖」という。汽水湖は流域の最下流に位置することから陸地や河川から流れてくる様々な物質が集積する一方、潮汐の影響で海との物質交換が行われるため[1]、「淡水湖」とは異なった物質循環を有する。また、汽水湖では淡水と海水の密度差によって上下で異なった水の層(「成層」という)が形成されることがある[1]。汽水湖に生息する生物は塩分濃度によって変わる[2]ことから、塩分環境から見た湖沼型は、とくに生物多様性や漁業の面で重要である。汽水湖の定義が塩分0.5~30とされている[3]ことを踏まえ、本Webサイトでは、塩分0.5(塩化物イオン濃度として277 mg/L相当 [1])を閾値とし、それ以上の湖沼を「汽水湖」と区分した。なお、塩分が海水の塩分(北海道付近ではおよそ32~34 [4])に近く、汽水湖の定義から外れる湖沼についても、他の文献 [1]にならい汽水湖として扱った。なお、支笏・洞爺エリアの大湯沼について、過去の資料[5] [6]では淡水・汽水の区分が「不明」となっているが、汽水湖の定義(淡水と海水とが入り混じった塩水[3])や表層水の塩化物イオン濃度(120 mg/L前後[7])などから、本サイトでは「淡水湖」とした。本サイトでは、それぞれの湖沼の塩分環境がわかるように、各湖沼の解説ページに塩化物イオン濃度(Cl−)のデータを記載している。
| 塩分による湖沼型 | 本Webサイトでの定義 |
|---|---|
| 淡水湖 | 湖水の塩化物イオン(Cl-)濃度が277 mg/L未満の湖沼 |
| 汽水湖 | 湖水の塩化物イオン(Cl-)濃度が277 mg/L以上の湖沼 |
北海道の主要な天然湖沼(138湖沼;知床五湖の各湖沼をそれぞれカウント)のうち、淡水湖は112湖沼(全体の約81%)、汽水湖は26湖沼(約19%)である。汽水湖は、北海道の北部の日本海沿いから東部のオホーツク海沿い、また、根室半島周辺から釧路・十勝にかけての太平洋沿いに分布しており、エリア別に見ると「南オホーツク・知床」で9湖沼と最も多い。
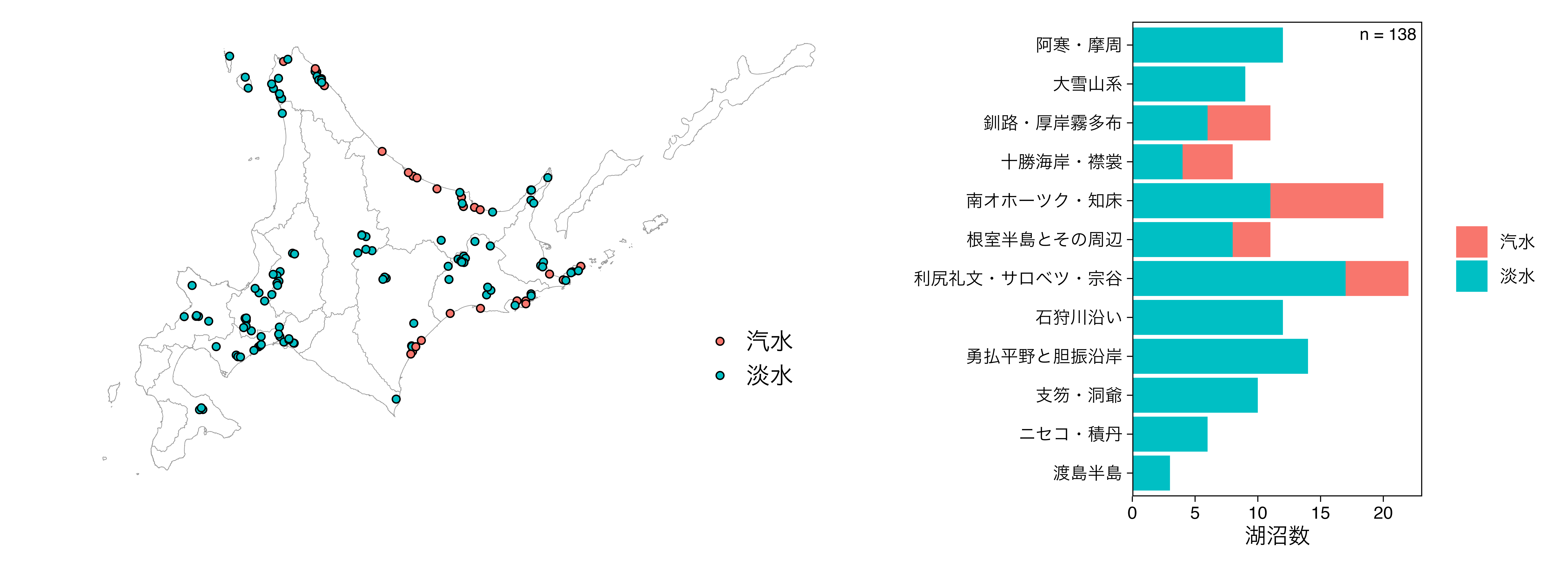
< 淡水湖・汽水湖の分布 >
栄養度から見た湖沼型
支笏湖(貧栄養)
阿寒湖(貧〜中栄養)
春採湖(中〜富栄養)
兜沼(過栄養)
湖沼は、河川などに比べて閉鎖性が強く、水が滞りやすいため、流入する物質を貯留する性質をもっている。一般に、窒素(N)やリン(P)といった栄養物質(「栄養塩」という)が流入し、湖水中でのそれらの濃度が高くなると、それらを栄養源とする植物プランクトンの増殖が活発化し、食物連鎖を通じて、動物プランクトンや魚などの生物生産も増加する。これらの生物は死滅すると有機物として湖底に堆積するとともに、微生物によって分解され、やがて栄養塩として再び湖水中に戻っていく。こうして、湖水はしだいに栄養度が高くなり、やがて浅くなって沼沢や湿原へと変わっていくと考えられている。このように、湖水の栄養度が上がっていく現象を「富栄養化」とよぶ[3]。
富栄養化は自然のプロセスとして進行するが、水質汚濁として問題になるのは、人間活動によって湖沼の環境が急激に変化し、富栄養化することで起こるものが多い。その例として、透明度の減少、深い層での酸素濃度の低下(貧酸素化)、アオコや赤潮などが挙げられ、時として景観の悪化や漁業被害、水源の汚染などにつながる。そのため、湖沼の水質保全を考える上で、それぞれの湖沼のもつ富栄養化の段階(栄養度)を把握することは、非常に重要なことである。
貧栄養と富栄養の境界は明確ではなく、原則的には栄養度の区分を数値で示すことはできないが[3]、本サイトでは、各湖沼の栄養度を評価するため、「北海道の湖沼」(1990)[8]及び「北海道の湖沼 改訂版」(2005)[9]に倣い、次表に示す栄養度区分を便宜的に用いた。
| 栄養度による湖沼型 | 全窒素濃度 [mg/L] | 全リン濃度 [mg/L] |
|---|---|---|
| 貧栄養湖 | < 0.20 | < 0.010 |
| 中栄養湖 | 0.20 ~ 0.40 | 0.010 ~ 0.030 |
| 富栄養湖 | 0.40 ~ 1.00 | 0.030 ~ 0.100 |
| 過栄養湖 | > 1.00 | > 0.100 |
各湖沼の最新の調査データに基づいて、全窒素(TN)濃度と全リン(TP)濃度の散布図を作成した(糠平ダム湖やデータの無い湖沼は除く)。各湖沼を表す点から矢印が出ているのは、報告下限値未満であることを意味する。また、「N:P = 7.2」の線は、植物プランクトンの平均的な窒素とリンの組成比(「レッドフィールド比」という)[10]を表している。植物プランクトンの増殖において、この線より左上に行くほど窒素が制限因子になりやすく、この線より右下に行くほどリンが制限因子になりやすいというように、湖水中の窒素とリンのバランスを把握する指標のひとつとして用いられる。北海道の天然湖沼はレッドフィールド比の線より右下にあるものが多く、リン制限の傾向がうかがえる。
北海道の天然湖沼の栄養度は貧栄養から過栄養まで幅広い。エリア別に見ると、低地が多い「石狩川沿い」や「利尻礼文・サロベツ・宗谷」などで高く、山地が多い「支笏・洞爺」「大雪山系」「阿寒・摩周」などで低い傾向がある。また、「南オホーツク・知床」の湖沼は貧栄養から過栄養までバラエティに富んでいる。
成因別に見ると、河跡湖では富栄養から過栄養と高く、カルデラ湖で貧栄養から中栄養と低い。また、堰止湖や火山湖は北海道全体から見ると低い栄養度となっている。海跡湖は貧栄養から過栄養までバラエティに富んでいる。
なお、湖沼の栄養塩濃度は、季節あるいは気象条件などによって変動するのが一般的である。ここに示したデータの多くは、6月~11月の間の1回の調査によるものであり、変動までは考慮されていないことに留意する必要がある。
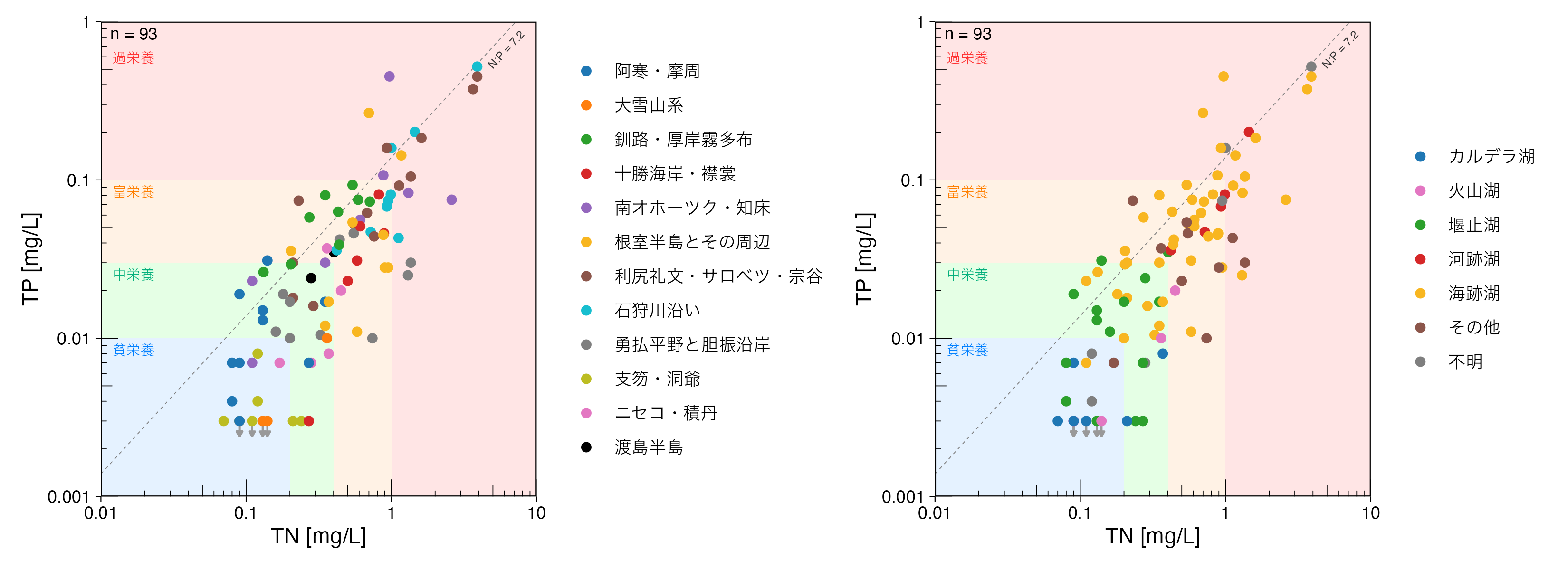
< 全窒素(TN)濃度と全リン(TP)濃度の散布図 >
非調和型湖沼の湖沼型
メグマ沼(腐植栄養)
メグマ沼の湖水の色
屈斜路湖(1980年代まで酸栄養)
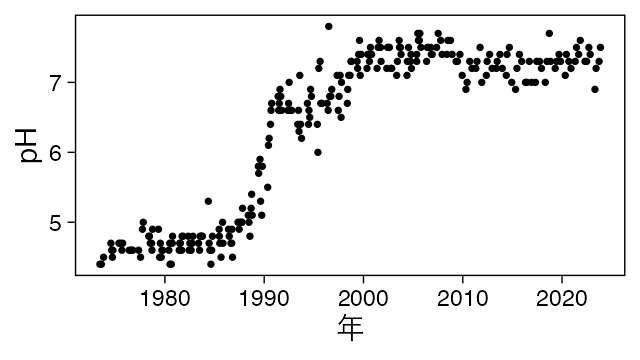
屈斜路湖のpH(ST-2 表層)
湖沼は、一般に、湖内での生物生産の立場から「調和型湖沼」と「非調和型湖沼」に分けられる[3]。調和型湖沼とは、湖水中の生物生産に関係する栄養物質に調和がとれていて、生物生産を阻害する物質がほとんど含まれていないものをいう[3]。窒素やリンに基づく上記の栄養度区分は、調和型湖沼を対象にしたものである。これに対し、非調和型湖沼とは、生物が要求する化学成分と湖水中の成分とが一致せず、生産を阻害する物質が含まれることがあるものをいう[3]。
非調和型湖沼には「腐植栄養湖」「酸栄養湖」「アルカリ栄養湖」「鉄栄養湖」などがあるが、北海道には腐植栄養湖が多くある。北海道には、木、草やコケ類の遺体が嫌気性微生物によって不完全分解または一部が分解して腐植化した「泥炭」[11]と呼ばれる土壌が湿原を中心に広く分布している[12]。泥炭など有機物を多く含んだ土壌に涵養された水は、「腐植物質」という生物によって分解されにくい有機物(「難分解性有機物」という)を多く含み、褐色を帯びている特徴がある[13]。これら難分解性有機物は、自然由来にも関わらず、有機汚濁の指標である化学的酸素要求量(COD)の濃度を高くしてしまい、水質汚濁していると誤解されやすい。そのため、北海道の湖沼の水質保全において、腐植栄養湖かどうかを検討することは重要である。本サイトでは、各湖沼の解説ページにおいて、周囲の環境や湖水の色、CODや全有機炭素(TOC)の濃度などから、腐植物質の影響を受けているかどうかについて記載している。
一方、「酸栄養湖」は、硫酸や塩酸などの火山起源の無機酸の影響などによって湖水のpHがかなり低い(強い酸性の)ものを指し[3]、その傾向を示す湖沼が、北海道にもいくつか存在している。通常の湖沼では生息可能な生物でも、pHが低下すると生息できなくなるものが多くいる。そのため、湖水のpHは重要な指標である。また、水の酸中和(緩衝)能の指標である「アルカリ度」[3]は、湖沼の酸性化を見る上で重要である。そこで、pHとアルカリ度についても各湖沼の解説ページにデータを記載した。屈斜路湖やオンネトーのように、かつては酸性(酸栄養湖)であったが現在はpHが中性付近(調和型湖沼)にあるなど、湖水のpHが長期的に変化する湖沼も見られる。
reference
[1] 環境省, 2014, 日本の汽水湖, URL: https://www.env.go.jp/water/kosyou/brackish_lake/index.html(2025年4月23日時点)
[2] 園田武, 2016, 汽水域の生態学, アクアバイオ学概論, 松原創・塩本明弘[編著]: 82–94, 生物研究社, 東京.
[3] 日本陸水学会(編集), 2006, 陸水の事典, 講談社, 東京, 590p.
[4] 国土交通省国土地理院, 1990, 新版日本国勢地図, 7 自然, 海流・海水温度・塩分濃度(冬期)(夏期), ナショナルアトラス閲覧サービスURL: https://www.gsi.go.jp/atlas/archive/j-atlas-d_2j_07.pdf (2024年4月23日時点)
[5] 北海道, 1989, 北海道湖沼環境保全基本指針, 北海道, 札幌, 44p.
[6] 環境庁, 1993, 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 北海道版(北海道), 636p.
[7] 室住正世・安孫子勤・中村精次, 1966, 登別大湯沼火口湖の地球化学的研究, 火山. 第2集, 11: 1-16. https://doi.org/10.18940/kazanc.11.1_1
[8] 北海道公害防止研究所, 1990, 北海道の湖沼, 北海道公害防止研究所, 札幌, 445p.
[9] 北海道環境科学研究センター, 2005, 北海道の湖沼 改訂版, 北海道環境科学研究センター, 札幌, 314p.
[10] Brönmark C. & L.-A. Hansson[著]・占部城太郎[監訳], 2007, 湖と池の生物学―生物の適応から群集理論・保全まで―, 共立出版, 東京, 339p.
[11] 矢部和夫, 2017, 泥炭形成と植物, 湿地の科学と暮らし―北のウェットランド大全, 矢部和夫・山田浩之・牛山克巳[監修]: 3–17, 北海道大学出版会, 札幌.
[12] 小疇尚・福田正己・石城謙吉・酒井昭・佐久間敏雄・菊地勝弘[編集], 1994, シリーズ 日本の自然 地域編 1 北海道, 岩波書店, 東京, 192p.
[13] 長尾誠也, 2003, 我が国の腐植物質研究とその展望 4. 環境中での腐植物質の存在意義とその機能, 日本土壌肥料学雑誌, 74: 371–376. https://doi.org/10.20710/dojo.74.3_371
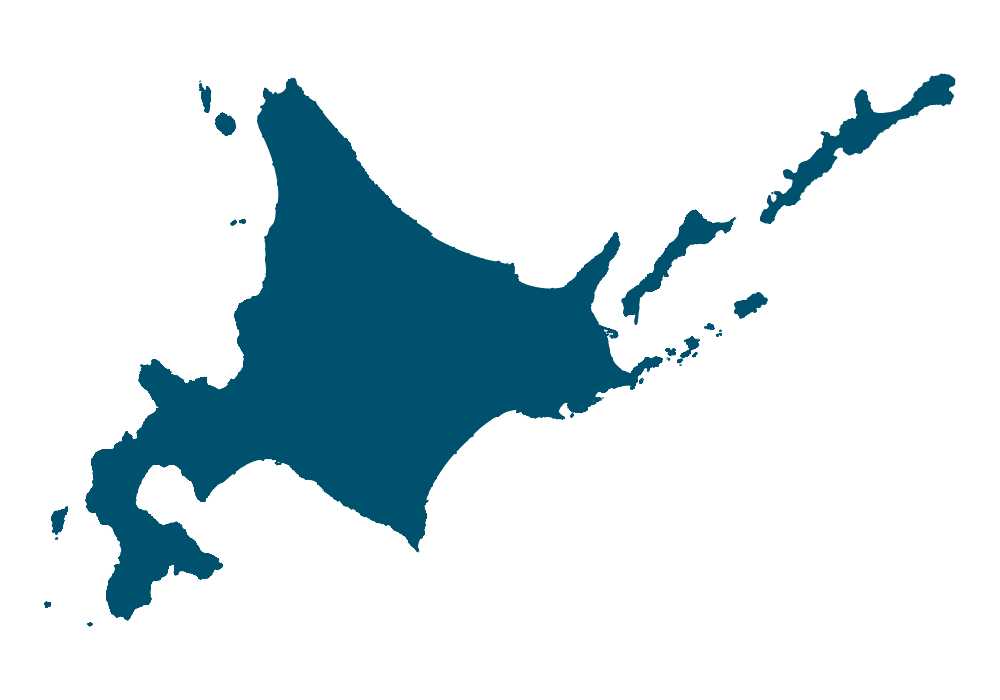 Lakes in Hokkaido
Lakes in Hokkaido