4. データの出典と調査方法など
諸元データの出典
本Webサイトに掲載している湖沼の諸元データは次の資料等による。北海道の湖沼[1]、北海道の湖沼 改訂版[2]に掲載の情報をベースに、他の機関が調査・公表するデータ等を参照し、整理した。なお、最大水深など、なかには調査年が古い情報も含まれており、底泥の堆積や湖岸の改変などによって、現在では値が変わっている可能性があることに留意されたい。
| 項目 | 資料等 |
|---|---|
| 湖沼名 | 北海道[3]、国土地理院[4] |
| 語源 | 北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課[5]、「角川日本地名大辞典」編纂委員会[編纂][6]、山田[7]、北海道新聞社[8] [9] |
| 成因 | 北海道環境科学研究センター[2]、北海道[3] 、5万分の1地質図幅説明書 |
| 湖面標高 | 国土地理院[10]、北海道環境科学研究センター[2] |
| 湖面積 | 国土地理院[4] [11]、北海道環境科学研究センター[2]、北海道公害防止研究所[1]、北海道[3]、一般財団法人日本ダム協会[12] |
| 最大水深 | 国土地理院[11]、北海道環境科学研究センター[2]、北海道公害防止研究所[1]、環境庁[13] |
| 容積 | 北海道環境科学研究センター[2]、北海道公害防止研究所[1]、北海道[3]、一般財団法人日本ダム協会[12] |
| 集水域面積 | 国土交通省[14]及び国土地理院[4] [10]を基に当所で作成したもの、北海道環境科学研究センター[2]、北海道公害防止研究所[1]、北海道[3] |
水質調査・分析方法
本サイトに掲載する水質データは、主として、当所が旧北海道公害防止研究所、旧北海道環境科学研究センター時代から実施してきた公共用水域調査、類型指定調査、湖沼等環境保全基礎調査、湖沼等環境保全対策調査、流域対策基礎調査および環境省委託透明度調査などに加え、2005年に刊行した「北海道の湖沼 改訂版」以降に当所が行った現地調査によって得られたものである。
水質調査および分析は、原則として次の方法により行った。調査は融雪および大雨等による出水の影響を避けるため、夏を中心とする非積雪期の平水時を基本とした。ただし、1年に複数回の詳細な調査を行った湖沼については、水質データ表に降雨等による出水時や結氷期のデータが含まれている場合があることに留意されたい。湖水の採水は各湖沼の湖心(湖面の中央部)あるいは最深部で行った。ポリエチレン製ビーカー、バンドーン採水器またはリゴーB号採水器を用いて、表層水(表層または0.5 m層)を採水した。あわせて採水地点の水深と透明度を観測した。2021年~2023年の調査では、さらに、多項目水質計(RINKO-Profiler ASTD102)を用いた水温、溶存酸素(DO)、電気伝導度(EC)及び塩分の鉛直プロファイルの観測も行った。
採水した試料は、必要に応じてガラス繊維濾紙で濾過処理をし、冷蔵あるいは冷凍状態で当所に持ち帰った。当所の実験室内で、持ち帰った試料の水質分析を行った。なお、調査年代によって観測・分析方法が異なる場合があることに留意されたい。
| 項目 | 測定・分析方法 |
|---|---|
| 水深 | 超音波測深器など |
| 透明度 | 白色セッキ板 |
| 水温 | 多項目水質計(サーミスター) |
| 溶存酸素(DO) | 多項目水質計(燐光式)、よう素滴定法(旧名称:ウィンクラー-アジ化ナトリウム変法) |
| 電気伝導度(EC) | 多項目水質計(7電極式) |
| 塩分 | 多項目水質計(実用塩分式) |
| pH | ガラス電極法 |
| 塩化物イオン(Cl-) | チオシアン酸水銀(Ⅱ)法、硝酸銀滴定法、イオンクロマトグラフ法 |
| アルカリ度 | 0.01N硫酸によるpH4.8滴定法 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量 |
| 全有機炭素(TOC) | 燃焼酸化-赤外吸収法 |
| 全窒素(TN) | アルカリ性過硫酸カリウム分解-銅・カドミウム還元法など |
| 全リン(TP) | 過硫酸カリウム分解-モリブデン酸ブルー法など |
| クロロフィルa(Chl-a) | 蛍光光度法 |
各湖沼の解説ページに示す水質データ表の数値については、分析の繰返し精度や定量下限値などを考慮し、原則として次のとおり整理した。
| 項目 | 単位 | 有効数字桁数 | 有効数字最小の位 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|
| 水深 | m | - | 小数点以下1桁 | - |
| 透明度 | m | - | 小数点以下1桁 | - |
| pH | - | - | 小数点以下1桁 | - |
| Cl- | mg/L | 3桁 | 小数点以下2桁 | - |
| アルカリ度 | meq/L | 3桁 | 小数点以下3桁 | - |
| DO | mg/L | - | 小数点以下1桁 | - |
| COD | mg/L | - | 小数点以下1桁 | 0.5 |
| TOC | mg/L | - | 小数点以下1桁 | 0.5 |
| TN | mg/L | 3桁 | 小数点以下2桁 | 0.05 |
| TP | mg/L | 3桁 | 小数点以下3桁 | 0.003 |
| Chl-a | μg/L | 2桁 | 小数点以下2桁 | 0.01 |
なお、環境基準が類型指定されている湖沼等については、上記の水質データに加え、北海道庁による公共用水域の水質モニタリングデータ[15]のうち、透明度、pH、COD、TN、TP及びChl-aの経年変化グラフを掲載した。
集水域の面積及び土地利用割合の解析方法
湖沼の水質は、集水域の土地利用の影響を強く受ける。「集水域」とは一つの水系に降った降水が集まる範囲のことをいい[16]、「流域」も同じ意味で使われることが多い。各湖沼の解説ページには、集水域の土地利用図を掲載している。
国土数値情報「流域メッシュデータ」[14]から、各湖沼を内包する流域とその上流域に属するメッシュを特定し、各湖沼の集水域として設定した。その際、地理院地図[4]に描写される水路等も参考にした。なお、流域メッシュデータでは特定できないような、小さい集水域面積の湖沼については、基盤地図情報「数値標高モデル5mメッシュ」または「数値標高モデル10mメッシュ」[10]を基に、GISソフトウェア(ArcGIS Pro 3.2.2)の水文解析ツールを用いて各集水域を作成した。土地利用は国土数値情報「土地利用細分メッシュデータ」[17]を用いて、各湖沼の集水域面積(湖面を含む)に対する各土地利用面積の割合を集計した。面積計算はUTM(ユニバーサル横メルカトル)図法に従った。
reference
[1] 北海道公害防止研究所, 1990, 北海道の湖沼, 北海道公害防止研究所, 札幌, 445p.
[2] 北海道環境科学研究センター, 2005, 北海道の湖沼 改訂版, 北海道環境科学研究センター, 札幌, 314p.
[3] 北海道, 1989, 北海道湖沼環境保全基本指針, 北海道, 札幌, 44p.
[4] 国土地理院, 地理院地図, URL: https://maps.gsi.go.jp/(2025年4月24日時点)
[5] 北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課, 2021, アイヌ語地名リスト. URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.html(2025年4月25日時点)
[6] 「角川日本地名大辞典」編纂委員会[編纂], 1987, 角川日本地名大辞典 1 北海道 上巻 地名編, 角川書店, 東京, 1654p.
[7] 山田秀三, 1984, 北海道の地名, 北海道新聞社, 札幌, 586p.
[8] 北海道新聞社[編集],1981.北海道大百科事典 上巻, 北海道新聞社, 札幌, 1145p.
[9] 北海道新聞社[編集],1981.北海道大百科事典 下巻, 北海道新聞社, 札幌, 1122p.
[10] 国土地理院, 基盤地図情報「数値標高モデル5mメッシュ」「数値標高モデル10mメッシュ」, URL: https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/#digital_elevation_model(2025年4月24日時点)
[11] 国土地理院, 湖沼調査, URL: https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/koshouchousa-list.html(2025年4月24日時点)
[12] 一般財団法人日本ダム協会, ダム便覧2024, URL: http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/All.cgi?db4=0047(2025年4月24日時点)
[13] 環境庁, 1993, 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 北海道版(北海道), 636p.
[14] 国土交通省, 国土数値情報「流域メッシュデータ(第2.1版)」. URL: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W07.html(2025年4月25日時点)
[15] 北海道, 北海道水質関連データ集. URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/99058.html (2025年4月26日時点)
[16] 日本陸水学会(編集), 2006, 陸水の事典, 講談社, 東京, 590p.
[17] 国土交通省, 国土数値情報「土地利用細分メッシュデータ(第3.1版)」. URL: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html(2025年4月25日時点)
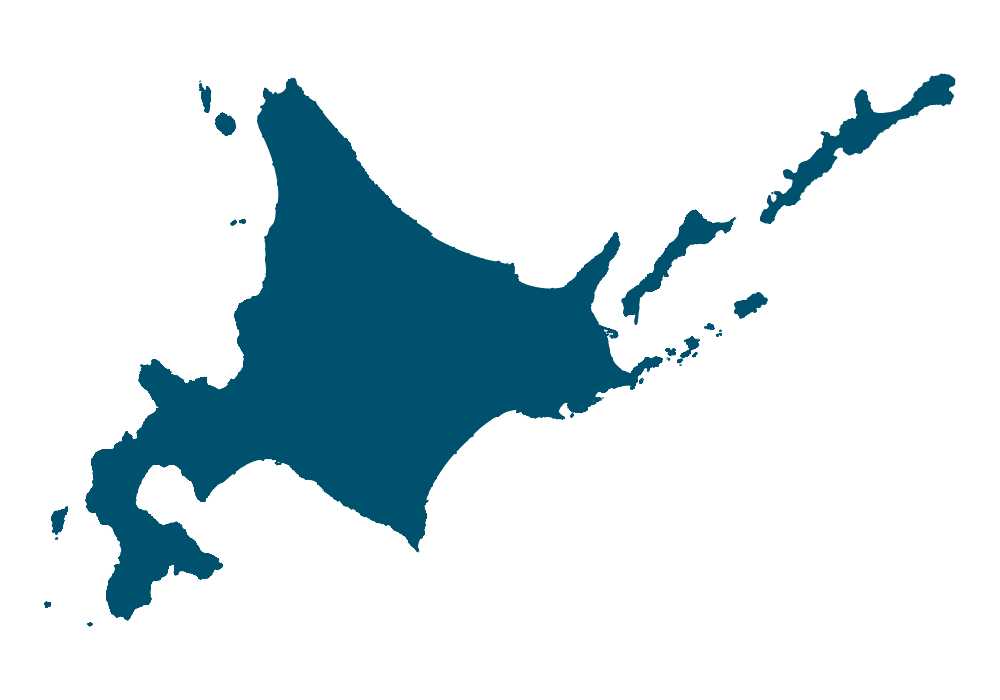 Lakes in Hokkaido
Lakes in Hokkaido