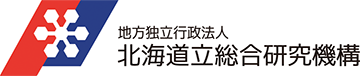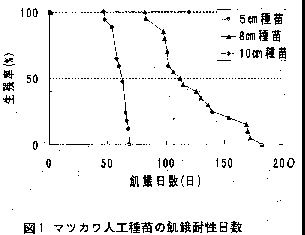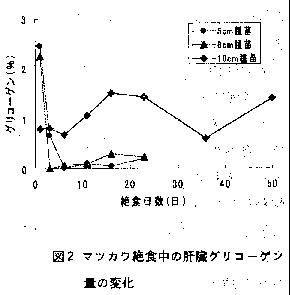マツカワの飢餓耐性
沿岸資源の減少が著しいなかで、全国各地で有用魚種の栽培漁業が盛んに行われています。なかでもマツカワは、天然資源がほとんどなく商品価値が高いこと、また生息に適した水温からみても、本道の太平洋沿岸にはうってつけの種類であり、各地で種苗放流が行なわれています。
人工種苗はある程度の大きさまで陸上で飼育され、その後自然の海に放流されます。それまで、波もない平穏な水槽で飼われていた魚が、突然自然の荒波の中に放り出されるわけですから、放流魚の戸惑いは相当なものでしょう。特に、それまで動かない配合飼料という名の餌を毎日もらっていたのが、放流されたとたん自分で餌を探さなくてはなりません。
ましてや餌となる小さなエビ類や小魚だって食べられまいと必死で逃げるわけですから捕まえるのは容易なことではないでしょう。当然のことから、放流された魚は、最初はうまく餌を捕らえることができず、飢餓状態になります。せっかく放流した種苗が餌をとれずに死んでしまっては困ります。
そこで、実際に何日くらい餌がとれないと餓死するのか知るために、栽培センターと共同で水槽実験を行ないました。
実験の方法はいたって簡単で、水槽内にマツカワの人工種苗を収容し、餌はいっさい与えないで飼育し、毎日何匹が餓死するのかを観察するというものです。また、種苗の大きさを全長5センチメートル、8センチメートル、10センチメートルの3段階とし、放流時の大きさが影響を与えるかどうかも調べてみました。
結果を図1に示しました。5センチメートル種苗では絶食後48日目から死亡する魚がみられ、63日目には飼育していた個体の半数が死にました。そして、69日目にはすべて魚が死んでしまいました。同様に、8センチメートル種苗では83日目から死亡する魚がみられ、112日で半数が、182日ですべて死にました。一方、10センチメートル種苗になると120日間の実験期間内に死亡する魚はみられませんでした。このことから、マツカワの人工種苗は絶食条件下でも50日以上生きていることがわかり、また、体が大きくなるにしたがって飢餓耐性が強くなることもわかりました。放流した魚が、自然界で餌を食べるようになるまでの日数は、ヒラメでは1週間から10日程度であることがわかっています。マツカワでも、函館水試の調査結果から放流1週間後には自然の餌を食べていることがわかってきています。これらのことから、放流された種苗も10日間程度で自然の環境に慣れ、餌を盛んに食べるようになれば餓死する危険性はないと思われます。
人工種苗はある程度の大きさまで陸上で飼育され、その後自然の海に放流されます。それまで、波もない平穏な水槽で飼われていた魚が、突然自然の荒波の中に放り出されるわけですから、放流魚の戸惑いは相当なものでしょう。特に、それまで動かない配合飼料という名の餌を毎日もらっていたのが、放流されたとたん自分で餌を探さなくてはなりません。
ましてや餌となる小さなエビ類や小魚だって食べられまいと必死で逃げるわけですから捕まえるのは容易なことではないでしょう。当然のことから、放流された魚は、最初はうまく餌を捕らえることができず、飢餓状態になります。せっかく放流した種苗が餌をとれずに死んでしまっては困ります。
そこで、実際に何日くらい餌がとれないと餓死するのか知るために、栽培センターと共同で水槽実験を行ないました。
実験の方法はいたって簡単で、水槽内にマツカワの人工種苗を収容し、餌はいっさい与えないで飼育し、毎日何匹が餓死するのかを観察するというものです。また、種苗の大きさを全長5センチメートル、8センチメートル、10センチメートルの3段階とし、放流時の大きさが影響を与えるかどうかも調べてみました。
結果を図1に示しました。5センチメートル種苗では絶食後48日目から死亡する魚がみられ、63日目には飼育していた個体の半数が死にました。そして、69日目にはすべて魚が死んでしまいました。同様に、8センチメートル種苗では83日目から死亡する魚がみられ、112日で半数が、182日ですべて死にました。一方、10センチメートル種苗になると120日間の実験期間内に死亡する魚はみられませんでした。このことから、マツカワの人工種苗は絶食条件下でも50日以上生きていることがわかり、また、体が大きくなるにしたがって飢餓耐性が強くなることもわかりました。放流した魚が、自然界で餌を食べるようになるまでの日数は、ヒラメでは1週間から10日程度であることがわかっています。マツカワでも、函館水試の調査結果から放流1週間後には自然の餌を食べていることがわかってきています。これらのことから、放流された種苗も10日間程度で自然の環境に慣れ、餌を盛んに食べるようになれば餓死する危険性はないと思われます。
ところが、最近になって、ヒラメでは放流直後の一時的な飢餓状態が「種苗の行動」に影響を与え、捕食者に狙われやすくなることもわかってきました。マツカワは、天然魚が極端に少ないため、稚魚が自然の海の中でどのような行動をしているのかはわかっていません。もしかしたら、マツカワでもヒラメど同じように放流直後の一時的な飢餓状態が種苗の生き残りに何らかの影響を与えているかもしれません。詳しいことは、今後の研究成果に期待しなければなりませんが、今回の実験結果から一つのヒントのようなものが得られました。
今回の実験では、水槽内で餓死した個体を観察すると同時に、定期的に水槽内から魚を取り上げ、体の大きさや成分を分析しています。絶食中は、体の中に蓄えて栄養分をエネルギーとして生きていくのですが、その際、最初に使われるものは肝臓中のグリコーゲンという成分です。この成分は、5センチメートルと8センチメートルの種苗で絶食3日間に大きく減少し、ほとんど使い尽くされてしまいました。これに対して、10センチメートル種苗になると絶食後50日以上を経過しても、絶食前と同じくらいのグリコーゲンが残っていることがわかりました(図2)。他の成分や肝臓の大きさなども5、8センチメートル種苗とし10センチメートル種苗で変化のしかたに違いがみられました。
今回の実験では、水槽内で餓死した個体を観察すると同時に、定期的に水槽内から魚を取り上げ、体の大きさや成分を分析しています。絶食中は、体の中に蓄えて栄養分をエネルギーとして生きていくのですが、その際、最初に使われるものは肝臓中のグリコーゲンという成分です。この成分は、5センチメートルと8センチメートルの種苗で絶食3日間に大きく減少し、ほとんど使い尽くされてしまいました。これに対して、10センチメートル種苗になると絶食後50日以上を経過しても、絶食前と同じくらいのグリコーゲンが残っていることがわかりました(図2)。他の成分や肝臓の大きさなども5、8センチメートル種苗とし10センチメートル種苗で変化のしかたに違いがみられました。
以上のように、50日以上も絶食に耐えるマツカワも体の成分はわずか3日の絶食で大きな変化が起きていて、しかも種苗のサイズにより、変化のパターンが異なってきました。放流サイズが大きいほど種苗の生き残りがいいことから、飢餓が何らかの影響を与えていると思われますが、詳しいことはまだわかっていません。種苗放流を成功させるためには、放流から漁獲までの間、放流魚に起こるいろいろな「できごと」を少しずつ解明していくことが必要だと考えています。
(函館水試室蘭支場 高谷義幸)