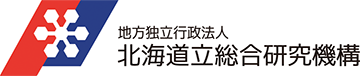北海道林業試験場研究報告-第31号-
PDFファイルで閲覧ができます
バックナンバー
第31号(平成6年3月発行)
目次ごとにダウンロード
落葉広葉樹の定着に及ぼす種子サイズと稚苗のフェノロジ-の影響(PDF:1.59MB)
清和研二
P1~68
落葉広葉樹林の林内,ギャップ,裸地などに生育する稚苗の利用可能な資源量は季節的に変化する。したがって,それぞれの地表で稚苗が更新に成功するか否かは,出現場所の環境の季節的変化に稚苗のフェノロジー(季節的伸長様式,葉の生存様式,発芽タイミング等)が適応的かどうかが大きな要点となることが考えられる。そこで種子の散布から稚苗の定着までの樹木の生活史の中で最も死亡確率の高い時期において,種子のサイズや当年生稚苗のフェノロジーが樹木の死亡要因や死亡回避戦略にどうかかわっているのかを明らかにすることを試みた。さらに,これらの関係が落葉広葉樹の最適な定着湯所選択にどう影響するかを考察した。
まず,落葉広葉樹高木31種の種子を苗畑(開放下,被陰下)に播き,種子サイズと稚苗のフェノロジーの基本的な関係について探った。実験に用いた31種の種子重は最大のクリの10900mgから最小のエゾノバッコヤナギの0.162mgまでほぼ105倍の開きがあった。開放下,被陰下ともに,種子サイズと稚苗の初期伸長量,本葉の寿命とは正の有意な相関が,子葉が展開してから本葉が開くまでの期間,伸長速度が最大となる発芽後の日数,展葉期間(伸長期間),落葉期間,着実期間,本葉の回転率,展葉数とは負の有意な相関がみられた。種子サイズの大きな種は被陰の有無にかかわらず種子の貯蔵養分で発芽直後に急伸長した。同時に大きな葉を一斉に開き短期間で当年の伸長や葉の展開を終了した。一方,種子サイズの小さな種は,開放下では成長期の終わりには種子サイズの大きな種とほぼ同じ苗高を獲得した。種子サイズの小さな種は,資源の制約により当初小さな子葉しか展開できないが,成長初期に葉へ重点的に資源を配分し,葉の回転率を上げて長い期間にわたって展葉を続けることによって,初期のハンデキャップを補償していることが明らかになった。ただし,このような補償作用は被陰下ではみられなかった。 このような種子サイズと稚苗のフェノロジーの間にみられた関係が自然環境下で稚苗が定着する際どのような影響を持つのかを山地播種試験によって検討した。
材料は,異なる種子サイズをもつ落葉広葉樹5種(ミズナラ・イタヤカエデ・ケヤマハンノキ・カツラ・シラカンバ)である。これらの種子を落葉広葉樹の林内,小ギャップ,大ギャップの3箇所それぞれに設けた落葉層区,土壌裸出区に播種した。それぞれの場所で,光,土壌水分,落葉量,草本類の繁茂などの環境条件の季節的変化,および当年生稚苗のフェノロジーを調べた。また種子の散布から稚苗出現後2年間の生存,成長過程を比較し,種子サイズや稚苗のフェノロジーが稚苗の生存,成長にどう反映したかを考察した。苗畑試験と同様に山地試験でも当年生稚苗のフェノロジーが種子サイズに大きく規定されていることが明らかになった。発芽当年の稚苗のフェノロジーは出現場所における資源(光,水分,温度など)が季節的に変動する山地でも通年的に変動の少ない苗畑でも,種子サイズによってほぼ決定されていることが明らかになった。さらに,発芽当年における稚苗の定着の成功度は,「出現した場所の環境の季節変化と稚苗のフェノロジーとが同調していること」に依存していることが明らかになった。
大きな種子サイズをもつミズナラ・イタヤカエデのフェノロジーは基本的には種子サイズに規定されつつも,出現場所の環境の変化に可塑的かつ適応的に反応し,いずれの出現場所でも高い生存率を示した。これら大きな種子サイズをもつ種は,落葉広葉樹林内では,大きな葉を春先に一斉に展開し,秋に一斉に脱落させた。このような展葉様式は,林冠木の開葉前の明るい林床で有効に光合成を行うことを可能にした。すなわち,フェノロジカルに被陰を回避することによって,その後の生存を確実にしようとする戦略をもつものと考えられた。さらに林内では葉の寿命を伸しSLMを減らし被陰による光合成能率の低下を補おうとする適応的な反応を示した。樹木の稚苗が落葉広葉樹林内など被陰ストレスの大きなところで生存できることの説明として,弱光下における光合成能率の高さや光補償点の低さ,また効率的なサンフレックの利用などの葉の生理的特性,および,種子の貯蔵養分の大きさによる栄養補給などが挙げられてきたが,さらに“フェノロジカルな被陰の回避”も効果的に作用していることが示された。
土場,集材路,林内におけるプロセッサ作業の比較(PDF:942KB)
木幡靖夫・浅井達弘・由田茂一・対馬俊之
P69~76
29年生トドマツ人工林において,プロセッサが土場で作業する土場処理型,集村路上を移動しながら作業する集材路処理型,林内に進入して作業する林内処理型の三通りの方法で,プロセッサによる間伐木の処理(枝払い,玉切り,巻立て)作業を行った。プロセッサの作業功程が最大となったのは土場処理型で,1時間当たりの功程は本数で28.7本,材積では約3.0m3となった。また,集材路処理型では全木材の再集積という副作業が発生したことに加え,挟い集材路上での作業となったためプロセッサの動きは強く制約された。その結果,功程は17.2本,1.5m3となり,林内処理型の27.3本,2.9m3を下回った。各タイプの作業上の特徴として以下のことがわかった。①土場処理型はプロセッサの能力を最大に発揮できるが,作業量に応じた広さの土場を確保する必要がある。また,土場で枝条が大量に発生するのでそれらの処理が可能でなければならない。②集材路処理型は広い土場を必要とせず枝条を集材路沿いの林内に還元できるが,挟い集材路上を移動しながらの作業となるのでプロセッサの能率が低下する。③林内処理型はプロセッサの作業空間が制限されるためその能率は土場処理型に比べて若干低下するが,枝条を処分する手間が省ける。
茎頂培養法によるエゾヤマザクラの大量増殖(PDF:415KB)
佐藤孝夫
P77~86
茎頂培養法を用いたエゾヤマザクラ成木からの大量増殖技術を確立するため,初代培養で得られたシュートを用いて継代培養を試み,シュートの大量増殖に適した成長調節物質の濃度を検討した。材料には約30年生の1個体を用い,2月に採取した休眠芽から茎頂を無菌的に摘出し,寒天培地に置床した。初代培養でのシュート増殖率が最も高かった処理は,3種類の成長調節物質(IBA,BAP,GA3をそれぞれ0.1,4,4mg/l)を同時に添加したWPM培地(ショ糖20g/l)で1ヵ月間培養した後,BAP濃度のみを0.5mg/lまたは1mg/lに減じた培地で培養した場合で,シュート増殖率は約4培であった。次に初代培養で得られたシュートの腋芽を2,3個含む節部切片に切り分けて継代培養を行った。継代を重ねてもシュート増殖率が比較的高かった処理は,BAPを0.5,1mg/l,GA3を4,8mg/lとしたWPM培地(ショ糖20g/l)で2週間培養した後,BAP濃度のみを半分に減じた培地でさらに2週間培養した場合で,腋芽から効率的にシュートを増殖することができた。この方法で継代培養を10代続けた結果から試算すると,1個の茎頂から1年間に数百億本のシュートが培養できることになる。また,継代3,4および10代目のシュートの発根率はいずれも高い値を示しており,エゾヤマザクラの大量増殖が技術的には可能になった。
施業・環境因子のエゾヤチネズミ数への影響力(PDF:501KB)
中田圭亮・今野正彰
P87~93
造林地における4年間の発生予察調査資料を利用して,エゾヤチネズミの生息数に対する施業・環境条件の寄与率を調べた。取り扱った10因子のそれぞれの偏相関係数は,地域区分(0.151*~0.466**:最小~最大,*p<0.05,**p<0.01),林床植生(0.163*~0.302**),樹種(0.155,~0.234**),林齢(0.156*~0.217**),傾斜方位(0.095~0.269**),粗朶枝条(0.090~0.264**),地形(0.066~0.220**),傾斜度(0.052~0.168*),面積(0.055~0.209**),地拵え(0.038~0.167**)であった。各因子の寄与率,因子間の内部相関値,因子内の区分ごとの反応も年ごとに変化していた。造林地のネズミ数に対する10因子全体の重相関係数は0.471**~0.598**であった。