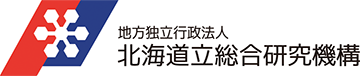北海道林業試験場報告-第6号-
PDFファイルで閲覧ができます
バックナンバー
第6号(昭和43年5月発行)
目次ごとにダウンロード
日高アポイ岳およびピンネシリ岳山麓地域所産銹菌類(PDF:6.31MB)
平塚直秀
P1~13
各種の銹病が,樹木の苗畑あるいは造林地に大発生して相当の被害を与えていることは衆知の事実である。 これらの銹病の病原菌の分類学的考察を行なってその種名を明らかにするとともにその生活史を調べることによって同病の第1次発生源を究明することは同病の防除上からもきわめて肝腰であると思う。
たとえば,ポプラ類のMelampsora larici-populina の夏胞子・冬胞子両世代による葉銹病の被害は激甚であるが,同病菌は異種寄生性を有し,その銹胞子世代をカラマツ類の針葉上で経過するので,ポプラ類の造林地に近接してカラマツ林が存在するような場合には同病はとくに大発生する。また,ヒヨドリパナ類の自生の多い地域にストローブマツの植林を行なってColeosporium eupatorii の銹胞子世代によるストロープマツの葉銹病の大発生を見た例もある。ヒヨドリパナ類はColeosporium eupatoriiの夏胞子・冬胞子寄主である。
なお,苗畑あるいは造林地に発生する銹菌は他から移植された苗木に寄生あるいは付着して入ったいわゆる外来の種類である場合と,従来からその地域の山野に発生していた,いわゆる在来の種類である場合とに分けることができる。
たとえば,アポイ岳山麓でミズナラの葉上にCronartium quercuum(マツ類の瘤病菌)の夏胞子・冬胞子両世代を発見したが,同菌は恐らく本州から移植されたアカマツの枝幹上に形成された同菌の銹胞子から感染したものと思推される。
ミズナラ上の同菌を発見した場所の近くには同地域では珍しく可成りの大木になった数本のアカマツがあったので,恐らく第1次発生源はこれらのアカマツ上に形成される銹胞子であろうと思われる。
しかし,著者は今回の調査ではアカマツ上に同菌を発見することができなかった。
苗畑あるいは造林地に発生する銹菌が在来種で,山野に自生している植物上の菌が第1次発生源となり得るものの例もきわめて多い。
たとえば,同地域の調査でもトドマツ類の針葉上で銹砲子世代を経過することの確認されている種類は,Uredinopsis 属菌4種,Hyalopsora 属菌1種,Melampsorella 属菌1種,Pucciniastrum 属菌5種,計4属11種に及んでいる。
本報文において著者は,アポイ岳およぴピンネシリ岳山麓一帯の地域の銹菌フロラを明らかにし,とくに樹木に寄生する種類について検討し,同地域における苗畑ならぴに造林地に発生の予想される銹病の第1次発源を明らかにする目的で本研究調査を行なった。
なお,本研究調査の現地における銹菌類の採集調査ならびに生態観察は,主として著者ならびに佐藤昭二博士によって, 昭和42年8月24日~8月26日の3日間(アポイ岳およびピンネシリ岳山麓地域一帯)および著者によって昭和40年7月 2, 3 日両日 (主としてアポイ岳)行なった。
本報分において列挙したアポイ岳およびピンネシリ岳山麓一帯の地域所産の銹菌類は,メランプソラサビキン科(Fam. Melampsoraceae) に属する Uredinpsis 属-4種,Hyalopsora 属-1種,Melampsoridium 属-3種 Melampsorella 属-1種,Pucciniastrum 属-7種,Thekopsora 属-1種,Melampsora 属-2種, Chrysomyxa 属-4種,Cronartium 属-1種,Coleosporium 属-8種,Ochropsora 属-1種,計11属,33種,サビキン科 (Fam. Pucciniaceae) に属する Pileolaria 属一2種,Xenodochus 属-1種,Phragmidium 属--4種,Triphragmium 属-1種,Gvmnosporangium 属-1種,Uromyces 属-11種,Puccinia 属-32種,Miyagia 属-1種,計8属53種,不完全銹菌に属する Aecidium 属-2種,総計20属88種である。
森林調査と幾何確率(PDF:2.27MB)
林知己夫
P14~18
森林調査において,ピッターリッヒ法やそれと関連のある諸方法が用いられ,また電子計算機の普及につれてシミュレーションがさかんになりつつあるとき,昔問題にされていた幾何確率のパラドックスをあらためて想起する必要があると私は感じてきた。これは,確率のフイールドをどうとるか,に関連している問題である。幾何の様に「図」をもとにしたものに対して確率論的な推論を加えようとするときには,いろいろな確率の与え方があり,その与え方によって計算される確率が変ってくるのでバラドックスと言われているのである。その確率の与え方は,どれも,もっともらしいものであるところに注目すべき点がある。
ビッターリッヒ法に関連したものは,土地の上の幾何学に根ざすものであるから,これに確率論をもちこむとき当然幾何確率に対する配慮が必要になる。シミュレーションは,私が解決しようとする問題に対して,確率を導入し,これにもとづいて計算を行なうものであるから,確率モデルをどうつくり,どれにどう確率を与えるかが,問狸の核心となり、この与え方によって解答の異なることも当然考えられるのである。現象に対して確率をどう与えて行くかという点て幾何確率に関連した思考上の注意を必要とするものである。
以上の様に考えてきたので,ここで幾何確率の古典的問題を述べ,あらためて注意を喚起したいと思って筆をとるわけである。いかなる確立の与え方が我々の現実の問題解決に対して最も妥当性があるか――妥当性ある確率モデルを如何に構成するか――は,単に理論的には解決できない(いずれももっともらしいのが普通であり,机上ではその優劣を定め難い)ものが多いので,こうした場合実際の調査データとその分折との対応づけが必須のものであると思う。
山腹崩壊の前兆と異常年輪(PDF:9.82MB)
東 三郎
P19~39
山腹崩壊の機構に関する素因的研究,すなわち,地質・地形・土質力学的研究は多いが,崩壊に達する経過を時間的に分析したものは少ない。これは崩壊の位置・時・規模を予知することがむずかしく,適当な測定方法がみあたらないからである。たとえば,現在用いられている地すべり移動計は,大移動後の局地的な余波を記録するうえに有効であるが,広い区域にわたって,長期間,事前の微候をとらえることはできない。その目的を達するためには,長期記録装置を備えた大型器機を数多く動員しなければならないことになる。大きな被災対象のある地域の山腹だけに限っても,その面債は相当に広く,とうてい満足な数量の器械を配置することはできないだろう。
しかし,山地災害をなるべく少なくするためこは,危険地帯の認識を高める必要があり,そのためには,山地の個性,地表変動の履歴に対して,まず,定性的な検討が加えられなければならない。筆者は,そのひとつの試みとして,植物指標による「時間」の導入について研究しつつある。この方法の基本的な立場はつぎのとおりである。すなわち,長い年月の間に,地質条件は地形に具現され,地表の変化は植物群に表現されているという考え方にたって,とくに,木本植物の年輪構成にみいだされる年単位の「時間情報」を解析し,地表変動の時間的閲係を求めようとするものである。この考え方は,森林の崩壊防止機能をうわまわった表土層の動きをすなおに認め,ある狭い区域においては,植物に影響する環境因子のなかで,地文因子(Physiographic factors)が他の気象因子(Climatic factors),土性因子(Edaphic factors),生物因子(Biotic factors)よりも重要であることを強張するものである。
本論文にとりあげた試料は,地表変動と植物指標の関係を研究しはじめた1964年に採取したものである。当時は解析法も未熟であったために,十分に検討することができなかった。その後,確かな記録をもつ北海道内の地すべり地や,天然林内の地すべり地において,地表変動と樹木年輪の関係を明らかにすることができたので,ひとつの年代的解析法を組み立て,その方法によって,あらためて当初の試料に考察を加え,崩壊機構の解明に役立てようとした。
本論文の試料は,再三にわたり,苫小牧林務署に提供してもらった。
前署長大谷克己氏,署長小池正氏,前土木課長中易与一郎氏,同横堀信一郎氏,土木課長田熊武司氏,前造林課長山口五男氏,治山係長小関宇太氏,技師小野寺宗昭氏,本間富夫氏,高橋建蔵氏,前穂別駐在所主任吉田暉義氏,主任谷口定雄氏,河崎道也氏,笹木産業古川誠氏に対し感謝の意を表する。また,アテの鑑定には,故矢沢亀吉博士,北海道大学農学部木材理学研究室石田茂雄教授,同木材加工学研究室宮島寛助教授の手をわずらわした。さらに,本研究に関して,かねがね貴重な助言を賜っている北海道大学農学部砂防工学研究室村井延雄教授,同若林隆三教官,同新谷融教官,同演習林藤原滉一郎教官,同工藤哲也教官と,卒業論文のテーマとして共に考究してきた葛西公尚君(1965),山上忠君(1966),吉田健君(1967)の諸氏に対し,本研究の発展しつつある現況を報告しお礼としたい。
なお,本論文は,北海道立林業試験場創立10周年記念論文集に掲載される幸運にめぐまれたものである。
一言付記して関係各位に謝意をのべる。
アカマツ休眠芽の光周性に関する研究 7.形成期の1年生アカマツ冬芽の低温感応性(PDF:3.52MB)
永田 洋
P41~49
アカマツ休眠芽の光周性に関する研究のシリーズの結果をまとめてみると,1年生以上のアカマツは表-1のような,サイクルをくりかえし生長している。アカマツには,10ヵ月近い冬芽期(生長停止期)があるが,それは,頂端分裂組織の活動が最大になる“形成期”,そして,短日効果によって分化形成が抑制されていく“休眠入期”,そして“休眠期”,低温効果によっておこる“休眠打破期”,そして,休眠状態はまったくさめているが温度条件が生長に適していないため生長できない“休止期”とにわけられる。これは,他の植物の休眠と比較検討できるように,さらに,本質的には,ペコニヤのムカゴ,ジャガイモの塊茎などの休眠と,同じ性質のものであるとの考えに由来している。
そこで,休眠は「外囲環境やAging等によって,植物体内に生化学的変化がおこり,その結果できた,または量的に変化した物質によって,ひきおこされる生長別化の停止」であると定義した。
そこで,その休眠をもたらす要因は,短日でも長日でも,Agingでも,また低温でも高温でも,乾燥でもよいわけである。ただし,それが直接生長を抑制しているとき,たとえば生長に不適な春先の低温や,夏の高温や乾燥による生長抑制や停止は,休眠ではなく強制された生長抑制(停止)であり,これは休止状態で,休眠ではない。その点Summer dormancy(夏休眠)という表現が,夏のあいだみられる生長停止や,ムカゴの形成につけられているが,その本質を混同させる危険をもっているので,ここではとらなかった。夏,単に水分不足それにともなう養分吸収不足,高温などによる生長抑制(停止)は夏休眠というようなものでなく“夏休止”ともいうべきものであろう。
次に,休眠打破に低温が必要であるとか,長日で打破されるとかで休眠の深さや本賃がちがうとは考えられない。すなわち,樹木の芽が休眠にはいったとき,薬や芽が,どのようなかたちで存在し,光をどのように感じるかというちがいが,休眠打破の条件に関係してくるのである。 たとえば,ポプラは休眠にはいったあと,光を感じる葉は落ちているし芽は光を感じなくなっているので休眠打破に低温が必要であるが,アカマツは休眠にはいっても葉も芽も光を感じるので長日で休眠は打被される。休眠に本質的なちがいがあるとは考えられず,他樹種と休眠の深さを比較するのは無意味であろう。
アカマツの生長に適した日長は16時間日長以上であるが,東京附近での最高日長は16時聞以下であるので,生長に適した日長は存在しない。このような環境で充分生育が可能で良い生長を示し得るのは,まず,形成期がり(これは自然日長が適している),次年の生長の“原型”が完成していて,休眠にはいり,低温効果(chilling)で打破されて,生長がまったく日長に関係なくおこり得るようになるので,生長よりも形成に適する日長のもとで,正常な生長が可能なのである。
すなわち,生長に適した日長の存在しない環境のもとではアカマツの休眠は越冬性(耐寒,耐凍性)と同時に,休駅にはいり,低温で打被され,生長が温度依存の反応になることが正常な生長を可能にすることで意味があるわけである。
ここでは,前に形成期から休眠期にかけて冬芽の低温感応性をみたのにつづいて,休眠に導入する短日効果が比較的少なく,分化形成には適した12時間日長と,休眠に導入する効果はもたないが,分化形成には適した16時間日長とで,前処理をおこなったうえで,低温処理(5℃)なおこない,その効果を比較検討した。
林木の光周性 9.ウダイカンバ種子発芽におよぼす低温処理と温周処理の影響(PDF:396KB)
永田 洋・花房 尚・林勇治郎・佐藤大七郎
P50~55
ウダイカンバ種子の発芽には,光が必要であり,それも周期的に短時間照射すると,1回照射よりも短い照射時間で高い発芽率を示す。次に,この種子の特徴は低温処理(prechilling)のあとでも,発芽には光が必要で暗黒では発芽しない。また,低温処理は光に完全にかわりうることはないが,ジベレリンは光にかわりうることもわかっている。
ここでは低温処理とジベレリンに温周処理を加えて,ウダイカンバの発芽の様子を調べた。
北海道林業における野鼠害防除の社会的問題点(PDF:7.05MB)
太田嘉四夫
P56~68
筆者の属する北海道野ネズミ研究グループは,1965年に北海道の林木の害獣であるエゾヤチネズミ Clethrio-nomys rufocanus bedfordiae THOMAS の生物学的研究と防除の研究を総括して,「エゾヤチネズミ研究史」(上田その他1966)を編集した。その総括において,筆者らは,“現在のような森林所有形態と林業施業法(森林施業法が正しい…‥筆者)があるかぎり,民間小所有者のカラマツ林の被害は絶えないのではあるまいか。このように考えれば,今後のそ害防除の研究課題としては,いかにしてそ害のすくない林業を行なうか,ということを自然的社会的条件から検討することが必要ではないかと思われる”。とのべ,また自分たちの反省として,“われわれの研究は必ず害の防除の実践によって検証されるのであるから,林業について一そう知識を深めなければならないし,林業人とくに第一線を担当する人たちとますます強く結びついていくことが必要であろうと思われる”とのべた。この反省として筆者は,自然的条件については別に考察した(太田1968a)。また林業についての勉強として,「林業生産の特質について」(太田1968b)を考察したが,ここでは社会的条件について考祭し,林業関係の諸賢の御批判と御教示を得たい。
ヤチネズミ2型の生長と発育 1.外部形質、体重、性成熟および行動(PDF:9.59MB)
阿部 永
P69~89
北海道に住むヤチネズミには本島産のエゾヤチネズミ Clethrionomys rufocanus bedfordiae (THOMAS)と属島の厚岸大黒島および利尻島に住むアッケシムクゲネズミ C.sikotanensis (TOKUDA)という2型があるといわれている(今泉1960)。後者は前者にくらべてやや大形で,黒毛が多く,臼歯咬面の紋がやや異なっていることによって区別されている。しかし属島のヤチネズミを独立種とすることには多くの問題があり,北海道本島のもののシノニムにすぎないとする意見もある(太田1956)。しかし現在までのところこれらについてはまだ十分な検討が行なわれていないため,鼠害防除における加害種の確定という意味においてもその再検討の必要性のあることが指摘されている(上田ら1966)。
これまでのこの類の分類学的研究では、動物の生長に伴う形態変化などを十分調査することなく,比較研究を行うことが多かった。したがって,これらの動物がその生長過程のどの部分において,どのように異なっているかという点が明らかでなかった。このような意味から,この研究の目的の一つはこれら2型の動物の生長・発育を比較することによって,それらの分類学的関係を明らかにしようとすることであった。また,生態学的研究の中の重要な部分の一つである個体群構成の研究には,正確な齢査定法を確立することが必要であり,この研究のもう一つ目的はそれをさぐるころであった。但し後者に関する考察は別の機会にゆずりたいと思う。
なお,この研究を進めるにあたり、種々ご援助をいただいた北大農学部応用動物学教室島倉亨次郎教授,貴重な標本を提供していただいた北海道立衛生研究所服部畦作氏,北海道森林防疫協会高安知彦氏に対し心から感謝の意を表したい。
マツ苗にたいするマツキボシゾウムシの寄生力に関する研究(PDF:6.03MB)
西口親雄
P90~102
この研究の目的はマツキポシゾウムシ(Pissodes nitidus ROELOFS)のマツ苗にたいする寄生力を明確にすることによって,松くい虫による立木被害の発現機構解明への一つの手がかりを得ようとするものである。
ところで, GÄUMANN (1950)は植物病原菌の寄主にたいする広義の病原性を(1) Aggressiveness すなわち寄主に侵入,“定着,進展する能力と(2) Pathogenicity すなわち寄主に病気を起こさせる能力にわけている。森林昆虫学の分野では,病原性に相当する言葉として,加害性あるいは攻撃力などあるが,いままでは明確な定義がされないままに使用されてきた。立花・西口(1968)は病原性の概念を森林昆虫学の分野に導入し、その内容を寄生力と発病力にわけた。すなわち昆虫の寄生力は病原菌の感染力にほぼ相当するものであり、松くい虫でしばしば問題になる一次性か二次性かという問題は,寄生力の問題として考えたいのである。
昆虫の寄生力を問題にする場合,寄主の健全度あるいは衰弱度にたいする表示がなければ意味をなさない。しかし,具体的には何をもって健全とするかは容易にきめることができない。そこで,さしあたってそれぞれの立場から健全性の定義づけをしておく必要があろう。二次性穿孔虫による立木被害の場合は,寄主の水分欠乏がそれに密接に関連していると考えられるので,この研究では,寄主の水分平衡に異常がみとめられた状態を衰弱として認識したい。
二次性穿虫の研究分野では,従来,針葉樹の水分生理状態を表わす方法として,浸透価,蒸散量,樹液流,動速度, 含水率,樹脂圧などが用いられている。この場合,寄主の生活機能(たとえば抵抗力)が正常である範囲では一定の値を示すものが指標として適している.と思われる。その意味で,筆者は寄主の水分生理状態の表示法として含水率を採用した。
林木の含水率と二次性穿孔虫の寄生との関係を求めた研究にはつぎ\のようなものがある。井上(1954)はキクイムシ類の寄生をうけたエゾマツの辺材含水率を測定し,ヤツパキクイムシ Ips typographus はやや乾燥状態を,エゾキクイムシ Polygraphus jezoensis はや湿性状態を好むと報告し, REID (1961)はキクイムシの一種 Dendroctonus monticolae の initial attackをうけたロジポールマツについて,その後の辺材含水率の変化をしらべ,キクイムシの寄生が不成功におわった木では含水率の低下はなく,寄生が成功した木では含水率の急激な低下があったと報告している。これらの報告は,Ips typographus や Dendroctonus monticolae の寄生が成功する前に,寄主の含水率がすでに低下をはじめているらしいことを暗示している。
一方,SCHWERDTFEGER(1955)はトウヒのヤツバキクイムシによる被害木と健全木の樹皮含水率は異ならなかったと報告し,ⅥTE(1961)は人工的処理を加えたボンデロサマツに寄生したキクイムシ Ips confusus が内樹皮含水率の高い場合でも正常に繁殖したと報告している。これらの報告は Ips typographus や Ips confusus が健全木にみちれるような高い含水率のもとでも正常に繁殖することを示している。
西ロ(1961)はマツ苗の水分状態を灌水でコントロールし,それにカンレイシャの袋をかけ,マツキボシゾウムシを放して産卵せしめ,苗の幹材含水率と樹皮下の幼虫孔の伸長度との関係をしらべた結果,苗の水分欠乏は幼虫孔の伸長をよくすることに関係があると報告している。
これらの報告から明らかなように,寄主の含水率の二次性穿孔虫にたいする意味は二つある。一つは,穿孔虫の繁殖に直接関与する因子としての含水率で,これは内樹皮の含水率であらわされる。SCHWERDTFEGERやVITEの報告から,Ips typographus や Ips confusus は健全木木がもっているような高い含水率のもとでも正常に繁殖することがわかる。しかし,このことは直ちに、これらのキクイムシが健全木そのものでも繁殖できることを意味しない。
もう一つは,林木の水分欠乏度すなわち衰弱度の指標としての含水率である。VITEは,含水率はキクイムシの寄生の成否判定の指標にはならないと考えているが,前述の報告が示すように.辺材含水率は指標として使える可能性がある。
筆者はこの研究において,マツ苗の含水率の動きを土壌水分との関連のもとに把握し,さらに苗の含水率と枯死との関係を明らかにした。 また,寄生実験によって,マツキポシゾウムシの寄生力を明らかにした。
この研究は東京大学北海道演習林森林動物実験室でおこなわれたが,同演習林に高橋延清教授からは絶大なご支援をいただいた。 ここに.心から感謝の意をささげたいと思う。
トドマツを加害するハマキガ類の薬剤防除試験(PDF:508KB)
上条一昭・鈴木重孝・川上功二
P103~108
北アメリカやヨーロッパでは,ハマキガはモミ類に大きな害をあたえているが,北海道のトドマツではハマキガが発生したという記録はこれまで全くなかった。ところが昭和初期に植栽されたトドマツ林に,1965年からハマキガ類とシャクガ類が発生しはじめ,年をおうごとに被害は増大している。被害はとくに北海道中央部で激しく,あと1~2年つづけて加害されれば枯死すると思われる林分が現われ,薬剤により早急に防除する必要が認められた。そこで1967年6月にヘリコプターを用いて薬剤の散布を行ない,その防除効果を調査した。散布後しばらくして激しい降雨があったことなどによって,はっきりした結果はえられなかったが,トドマツを加害するハマキガ類に対しては初めて行なわれた薬剤防除なので,ここに報告して御参考に供したい。
この報告にさいし,防除を実行されたかたわら,調査に種々御協力下さった旭川林務署造林課の諸氏,および北海道林務部の篠原均技師に厚く御礼中しあげる。
北海道地方におけるウダイカンバの変異 1.次代群の生長と産地環境との関係および林分のグループ分け(PDF:1.02MB)
畠山末吉・安達芳克
P109~135
天然分布のひろい樹種は,その地域によって個体や集団のいろいろな形質に差異がみられる。地域に関連した表現型の変異は集団のおかれた環境条件と集団の遺伝構成,およびこれら2要因の交互作用によってきまる。
環境変異は生育地域の個体にあたえられるいろいろな環境条件によってひきおこされ,地域に関連する遺伝変異は,集団にふくまれる遺伝子の種類と頻度の変化によっておきる。遺伝変異の原因は突然変異の圧力,各遺伝子型にたいする自然淘汰,他集団からの遺伝子の移入,遺伝子の機会的浮動の4つの要因とこれらの交互作用によるものと考えられる。
個体間の遺伝的な不均質は,突然変異や雑種などに起因する。このような個体間の遺伝変異が集団に保持され品種間変動の基礎になっている。もしそれぞれの地域なり集団が,ちがった環境条件のもとにおかれていて,それらの地域間に性的隔離があれば,それぞれの地域なり集団の間に遺伝的な変異がおきるであろう。あたえられた生育環境にたいし,遺伝的にもっとも適応的な植物は,不適応なものと比較し,数量的にも大量に生存し,よく繁殖する。しかし,自然淘汰がつよくはたらくためには,その種の分布範囲全域にわたって,個体間や集団間に無作為的な交配がおこらないような何らかの生理的隔離がなければならない。林木における隔離は,花粉や種子の飛散距離が制限因子となる。
自然淘汰は,地理的変異のもっとも大きな原因であるが,そのほか遺伝子の機会的浮動による無作為な遺伝子型の固定化も地理的変異の原因である。機会的浮動は,かならずしも生育地域間に環境的な差異がなくても,集団が小さく,しかも集団間に隔離が存在する場合におきる。
地理的変異は変異をおこさせている原因によりそれぞれ特徴的な変異のパターンをしめす。一般に気象要因は自然淘汰圧の中でもっとも重要なものである。気象条件はその樹種の全分布域にわたって徐々に変化するから,大抵の場合,変異が連続的になるか,または地理的勾配をしめす。しかし相対的には均一でも,不連続的に変わる生育環境が変異の原因である場合には,地理的に不連続な変異をしめす集団や生態系がつくられるだろう。同様に,過去に隔離があっても,現在隔離がなかったり,その逆の場合,あるいは両者が結びついて作用しあっていれば,地理的勾配や生態系的な変異の両者がおきよう。
林木集団の地理的変異に関する研究は数多い。地理的変異の性質,つまり変異の構成要素が環境的か遺伝的かは,実際の林業にとって重要である。もし林業上の重要形質の変異が遺伝的要因に支配されていれば,造林の実行上,種子の産地は極めて重要になってくる。同様に育種家は,よりすぐれた系統をつくりだすため,そのような変異を利用することになる。
北海道に分布する植物の地理的変異に関する研究は数多く,アカトドマツ(Abies scalinensis FR.SCHM.)とアオトドマツ(Abies sachalinensis FR.SCHM.var.mayriana MIYABE et KUDO)の地理的分布について原田・柳沢(1946),柳沢(1965)の研究が報告された。そのほかトドマツの重要形質の地理的変異について久保田(1965),柳沢・岡田(1966),玉利(1965),岡田(1966),向出ら,(1966)の報告がある。またエンレイソウの自然集団の変異について倉林ら(1956),鮫島(和)(1958)の研究が報告されている。
邦産のウダイカンバ(Betula maximowicziana REGEL.)の地理的変異についてSTERN(1964)が西ドイツのシュマレンベックでおこなった報告がある。
私たちの研究では,本道に天然分布しもっとも重要な道産広葉樹材の1つであるウダイカンバの重要形質についてつぎの事項を報告する。1)地理的な分布に起因する地域,林分間の変動と林分内の母樹間の変動の大きさを比較する。2)地理的変異について類型化を試みる。3)地理的変異がある場合その原因が何かを考える。
北海道の土壌型の理学的性質(PDF:559KB)
寺田喜助
P136~148
著者は,さきの報告(1967)で,土壌型による化学的性質の差異については,あるていど明らかにしたが,土壌型と理化学的性質の関係は,A層の厚さ,採取時含水量についてのみで,その他の性質は,地域的に考察したに過ぎなかった。
土壌型による理化学的性質の差異については大政(1951)が,BA,BB,BC型のような乾性土壌は他の土壌に比べて水分が比較的少なく,空気の量が多いと述べたのが最初である。
そのご,山谷(1956)も土壌型の水分関係について大政と同じ報告を行い,また,粘土の含量と土壌型との関係にもふれ,真下・久保(1956)も採取時含水量,最小容気量、透水性をとりあげ,土壌型によって異なることを報告した。
しかし,藤川・谷口・柏木(1956)は,最大容水量,採取時含水量および機械的組成と土壌型とは一定の傾向をみいだし難いと述べた。
また,茨木ら(1956)も,自然状態の容積重,孔隙量,最大容水量,採取時含水量,湿潤度、最小容気量,機械的組成などと土壌型との関係について報告し,大政・真下(1957)は吸水性について,また,真下(1956)および真下・橋本・宮川(1958)は透水性と土壌型,さらに,真下(1960)は飽水度と土壌型との関係を論じた。
北海道で森林の土壌型による理化学的性質の差異については,著者(1961,1967)が最小容気量,孔隙量,採取時含水量,A層の厚さなどについて報告したものと、林業試験場北海道支場(1965,1966)が土性,土壌3相について述べたものがあるに過ぎない。
今回,著者は,これらの理化学的性質の他に,2,3の因子を加え,土壌型ごと,地域ごとにそれぞれ平均値を求めて比較検討した結果,土壌型によって明らかな差異が認められ,さらに,著者らはこれまでBC型をBC(d),BC,BC(w)型に区分し,BD型の系列と異なるものと想定していたことが立証されたので,ここに報告する。
森林土壌水分の季節変化と斜面方位による差異(PDF:822KB)
薄井五郎・杉浦 勲
P149~156
森林土壌の水分条件が林木の生育の支配的因子となることについては,水分系列による土壌区分である土壌型と林木の生長との相関性に関する多くの研究でほぼ明らかである。
土壌の水分量は,降水による供給量と,蒸発散などによる損失量とのバランスによって定まるが,降水量は季節変化を示すから,土壌水分もそれに伴って変化すると考えられる。
また,降水量が一定とみなしうる小地域に限定しても,山地では斜面方位によって日射,風速などが異なり,蒸発散量が影響を受けて土壌の水分条件に差を生じ,これが北海道北部で一般に観察される林木の斜面方位による生長差をもたらす要因の一つと考えられる。以上のことを確かめるため,斜面方位によって明らかに生長の差が認められる成林したトドマツ人工林地内に固定調査地を設け,土壌水分の季節変化と斜面方位によるその変化の差異について測定を行なった。同時に,その差をもたらす環境機構を明らかにするために,林内の気象観測を行ない,これらの水分変化に与える影響について検討を加えた。
この調査に多大な御協力を頂いた雄武林務署の各位に厚く謝意を表する。
小面積林分の地位樹高層の定義とその推定法(PDF:882KB)
小林正吾
P157~171
筆者は前報(1967)で林地の地位評価の尺度として用いられる樹高は,偶然変動の範囲内に位置しているものであるべきことを指摘し,2つのプロットについて直観的にその樹高層を示した。今回さらに,ある年齢の樹高はそれまでの連年生長量の累積和であるという点に着目して,小プロット林分における,上で指摘した樹高層の定量的定義と,その推定法について一見解をえたので報告をおこなう。
トドマツ寒害木にみられる病原菌(PDF:854KB)
小口健夫
P172~178
1966~1967年の冬から春にかけて北海道東部の厚岸,浦幌,池田の各林務署管内の苗畑,造林地におけるトドマツ,エゾマツ,また南部の浦河,函館両林務署管内のスギ,トドマツの造林地が寒さの害をうけその損害は莫大であった。
当場が厚岸林務署管内厚岸郡浜中町茶内西区に1965年に植栽したトドマツ精英樹次代検定林もこの寒さの害をうけたので,精英樹ごとに採集した種子による苗木の寒さの害に対する抵抗性の調査が1967年7月におこなわれた。この調査の際寒さの害をうけたトドマツが2次的にどのような病原菌によっておかされるかをしるために178本の枯死木について,野外調査をおこなうとともに実験室で菌の同定,分離,接種試験をおこなった。
この調査をおこなうにあたって,種々御便諠をいただいた厚岸林務署渡辺署長をはじめ造林課の方々に厚く御礼を申し上げる。