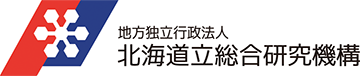北海道林業試験場報告-第19号-
PDFファイルで閲覧ができます
バックナンバー
第19号(昭和56年10月発行)
目次ごとにダウンロード
トドマツの産地間変異の地域性に関する遺伝育種学的研究(PDF:1.62MB)
畠山末吉
P1~91
トドマツ(Abies sachalinensis MAST.)の分類学上の変種に関する研究(宮部・工藤,1932;館脇・佐々木,1936;原田・柳沢,1941;佐藤・山口,1942)はトドマツの造林上の実用形質の変異に関する研究の先鞭をつけた。とくに,アカトドマツ(Abies sachalinensis MAST.)とアオトドマツ(Abies sachalinensis MAST. var. mayriana MIYABE et KUDO)の分類学上の根拠である球果の苞鱗の形状による球果型の区分(原田・柳沢,1964)は,各球果型の頻度分布の産地間変異や球果型の産地間変動と産地の環境要因との関連の研究に発展した。
柳沢(1965)は本道の各産地の球果型の頻度分布を調べ,球果型の水平的・垂直的分布は地理的環境にともない連続的に変化する勾配変異であるとし,各球果型に指数をあたえ数量化し,産地や林分の平均球果型指数がしめす等値線によるトドマツ種苗の需給地域の区分を提唱した。
これはアカトドマツとアオトドマツの産地や林分における混交度をあらわす平均球果型指数は遺伝形質の指標であり,それぞれの産地や林分の後代家系群の造林上の実用形質と何らかの相関があるだろうとの考えによっている。
その後,林木育種事業と平行した育種研究の推進によって,トドマツの産地や林分の平均球果型指数と種子形質は後代家系群の生長特性と関連性が高く,地域的変異であるとの報告(久保田,1965;玉利,1966;柳沢ら,1966;岡田ら,1966)が続いた。また,本道の中央脊梁山系を境に温暖な道西部と寒冷な道東部に分けた場合,それぞれのトドマツに顕著な差異があるとの報告もおこなわれた(久保田,1965;岡田,1966;岡田・向出,1969;岡田ら,1970;畠山,1970)。
しかし,上述の諸研究には,トドマツの平均球果型指数の等値線によって区分された地域内各林分の後代家系群の形質,たとえば,生長,樹形,適応性,諸害にたいする抵抗性などに共通性があるかどうかを検討したものが少ない。
それは,北海道のほぼ全域に自生しているトドマツの全遺伝変異を検討できるだけ十分な規模の標本数が抽出されていないこともあるだろう。また,林木の形質は産地の環境にたいし適応的な変異をしめすものが多い(LANGLET,1959;山崎,1959;ASTON and BRADSHOW,1966;GRIFFIN, 1978;堀田,1974;酒井,1976)が,全ての形質にたいし,淘汰圧の影響が同じでないからだろう。したがって,形質ごとに変動のパターンが異なり,一定の傾向を見出せないことがあげられる(GOTHO,1959 a,b;SQUILLACE,1966 a,b;MORGENSTERN,1969 a,b;GRIFFIN and CHING,1977)。たとえば,適応上中立な遺伝子は,適応と関連がある遺伝子と強い相関がないとすれば,自然淘汰ではなく機会的変動をしめすだろう(菊地,1979)。したがって,トドマツにおいても,生長形質の産地間変異が自然淘汰ではなく機会的変動と考えられる変動のパターンをしめすとの報告(岡田・向出,1973;OKADA et al.,1973)もみられる。
一般に,集団(産地)間の遺伝変異は集団の遺伝子頻度が変化することによってもたらされる。遺伝子頻度の変化は遺伝子の突然変異(遺伝子の組換え),自然淘汰,移住および機会的変動の作用によっておこる。産地間変動のパターンは作用した要因によってそれぞれ特徴的である(SQUILLACE,1966)。自然淘汰は,この中で,作用が最も大きな要因と考えられる。しかし,分布域が広い樹種の産地間変異には各要因が複合的に作用すると考えられる(MORGENSTERN,1969 b )。複合的に作用しあっている各要因は集団(産地),分集団(産地内林分),半姉妹家系(自然受粉家系)などのような枝分れ型の標本抽出によって育成した後代家系の調査解析から推定される。また,区分された各レベルの遺伝的分化の程度を知ることによって,造林用種子の種子源,育種材料の選択方法およびその産地区分なども明らかになるだろう。
もし,変異が自然淘汰の作用であるとすれば,自然淘汰は集団がおかれている環境条件の情報の一つと考えられるから,淘汰をうけた集団の特性から,産地や生育地の生態的環境区分が可能になるだろう(戸田,1979)。
種子の需給地域を区分するためには,先ず遺伝的特性が同一と考えられる産地の拡がりを明らかにし(LINDQUIST,1954),ついで,それらの適応範囲を明らかにしなければならない。適応範囲の区分は生育環境の等質性の区分であるから,概念的には育種区と同じものである。すなわち,うえにのべた生態的環境の区分である。
本論文はトドマツ種子の需給地域区分を目的とし,うえにのべた諸点を明らかにするため,トドマツの球果型,種子形質,幼齢期の生長や冬期に発生する諸被害にたいする抵抗性などの重要形質の産地間変異および変異と産地の環境要因との関係などについて,1964年から1979年までの16年間におこなった研究を取り纒めたものである。
本研究を遂行するにあたり,北海道立林業試験場渡辺啓吾前場長および久保田泰則副場長には終始有益な指導と助言をいただいた。また,本論文を草するに際して北海道大学農学部の武藤憲由教授をはじめ津田周弥教授および宇井格生教授には終始,懇切な御指導と御助言を賜った。以上の各位にたいしては心から深甚な感謝を申し上げる。さらに,本研究の進行に際し,国立遺伝学研究所,名誉所員酒井寛一博士には平素から懇切な御教示と御激励を賜った。心から御礼を申し上げる。一方,北海道立林業試験場においては,藤谷光紀元主任,江州克弘,梶 勝次,大島紹郎,石倉信介の各研究員に試験林の調査,データの整理等に直接協力を仰いだ。また,資料の整理やデータの作成には高橋悦子氏からお世話をいただいた。これら各位ほか協力をいただいた方々にお礼を申し上げる。
終りに,暗色雪腐病菌の培養に関して御指導をいただいた当場,秋本正信研究員,試験林の設定,管理に御協力をいただいた道有林管理室の関係各位にたいし謝意を表する。なお,本論文は「北海道大学審査学位論文」である。
シラカンバの葉の数の季節的変化-実験的研究-(PDF:555KB)
菊沢喜八郎
P93~104
私達は,道内の広葉樹二次林を保育し,優良材を生産する技術の確立を課題として,研究を行っている。この際,広葉樹林の林分構造や生長量をしらべ(菊沢・浅井,1979),実際に保育試験を行う(菊沢,1979)とともに,林分を構成する樹種の特性を知ることが,重要である。この目的のために私は,主な広葉樹の葉の展開のしかた,新条の伸びかたや落葉のしかたなどをしらべ,これを葉の数の季節的変化としてまとめるという方法をとっており,その結果の一部はすでに報告している(KIKUZAWA,1978;菊沢,1978)。その過程で,森林での葉の数の季節変化と,苗圃に植栽された苗木での観察結果が,かなり異なることに気付いた。
従来,落葉広葉樹の葉量の季節的な変化に関しては,苗圃に植栽されたアキニレ(只木・四手井,1960),カンレンボク(斎藤・四手井,1968),シラカンバ(荒木,1972)の苗木についての報告がある。これらの報告に共通していることは,生育期間の初期(5~7月)に葉量のピークがあることである。たとえば,只木・四手井(1960)による図式では,葉量は5月にピークに達した後に急減し,その後は一定値を保つものとされている。このように,生育期の比較的初期に葉量のピークが存在するものであるならば,逆にこれを落葉量の面からみれば,葉量のピーク直後と秋期との2回にピークが存在し,落葉量の季節分布は年二峰型となるはずである。
しかし,落葉広葉樹林において,落葉量の季節変化を調査した例を検討してみると,秋期一峰型の季節変化を示すものが多いのである。たとえば,日高地方の落葉広葉樹林の例では,ミズナラ,アサダ,エゾヤマザクラ,ヤマモミジ,イタヤカエデなど多くの種が,秋期に落葉量の集中する一峰型の季節変化を示した(菊沢・浅井,1979)。片桐・堤(1973)のブナ林での例や,佐藤・森田(1979)によるヤマナラシ,ミズナラ,シラカンバの例も,秋期一峰型の季節変化を示している。ヨーロッパでの報告を参照しても,ナラ,カンバなど秋期一峰型の季節変化を示す例が多い(BRAY & GORHAM,1964)。もっとも年二峰型の季節変化を示す例がないわけではなく,コバノヤマハンノキ(浅井・菊沢,1976;KIKUZAWA et.al.,1979),Alnus rubra(GESSEL & TURNER,1974),A. glutinosa(WITAKAMP & DRIFT,1961)など,ハンノキ属(Alnus)の種では,年二峰型の季節化が報告されている。
以上の報告を整理して私は,落葉量が年二峰型の季節変化を示すのは,ハンノキ属にみられる特性であって,他の多くの種は年一峰型であり,只木・四手井の報告している例は,苗圃での実験という制約下の特殊な現象ではないかと推定した(KIKUZAWA 1978;菊沢,1980a)。只木・四手井の描いたシエマは苗圃での特殊なものと考え,森林への適用については慎重な態度をとった例は二,三あるが(BRAY & GOHAM,1964;佐藤,1973),具体的に苗圃の条件下で実験的に再現したり,野外と比較した例はない。
苗圃における特殊な条件とは,かん水や施肥を別にすれば,若齢個体を用いることと,高密度で植栽されることの二点である。今回の研究では,シラカンバの苗木を,苗圃に密度を変えて植栽し,葉の数の季節変化を3年間継続してしらべた。また野外のシラカンバ林における葉の数と量の季節変化を,枝観察とリタートラップとによって求めた。これらを比較することにより,葉の数の季節的変化におよぼす,植栽密度と苗齢の影響を検討した。
コバノヤマハンノキ林分の落葉枝量の年変化および季節変化(PDF:550KB)
浅井達弘・菊沢喜八郎・福地 稔
P105~114
落葉枝量に関する文献はこれまでに数多く報告されており,BRAY & GORHAM(1964)によってすでに世界的な規模での整理がなされている。わが国においてもSAITO(1977),斎藤(1981)によっていろいろな森林タイプの落葉量やその季節変化が把握されている。しかしながら同じ林分で長期にわたって継続調査が行われたものは少なく,斎藤(1980)の壮齢ヒノキ林分で10年間,古野・山田(1974)のモミ・ツガ林分で6年間の報告がある程度である。これらはいずれも針葉樹林であり,落葉広葉樹林でのこうした報告は今のところないようである。
筆者らは1973年から1980年までの8年間にわたり,調査開始当時11年生のコバノヤマハンノキ林分において落葉枝量を調査してきた。この間落葉量の季節変化や,調査林分に大発生したナミスジフユナミシャクと被害量の関係などについてはすでに報告した(浅井・菊沢,1974,1976;菊沢ら,1977;KIKUZAWA et a1.,1979)。
この報告では最初に変動係数を用いて各落葉枝量の平均値の精度を確認し,つぎに各落葉枝量の年変化と季節変化の概略を述べる。
トドマツ人工林の施業法に関する研究(3)-53年生林分の現存量-(PDF:1.15MB)
阿部信行
P115~128
この研究の目的は,作業法別に生長量がどのように変わるかを調べ,これを基にどのような施業方法がそれぞれの地域で最も適しているかを決定することを目指している。前報(阿部,1980)では,一斉林を対象としたトドマツ人工林取穫予想表を作成した。トドマツは大面積の一斉造林だけでなく,保残木作業等種々な作業法がとられる。
収穫表に記載してある幹材積の生長量は林分葉量がもたらすものである。作業内容に応じた生長予測を論じるのには作業のとり方により林分葉量がどう変化し,それに応じて幹材積がどう変わるのかを究明しなければならない。そうした意味から今回はまず基準となるトドマツ一斉人工林の現存量を調査した。
わが国では既に各種の森林の現存量が調べられており,トドマツ林においても測定結果が報告されている(加藤,1961;SATOO,1974;四大学合同調査班,1960;四手井ら,1962;原田ら,1971;春木ら,1972;春木,1979)。しかし,トドマツ高齢人工林の現存量となると,今まで報告例がない。今回,道有林雄武経営区で高齢人工林の現存量を測定したので結果を報告する。また,前報(阿部,1980)で調整した収穫表の数値を,現存量調査で解析した現実の生長量等と比較検討する。
本調査では,現地の雄武林務署の各位に全面的なご協力を頂いた。また,大量の枝葉の絶乾重量を求める作業は道立林産試験場乾燥科で実行し,絶乾重の測定は材質科長山本 宏氏および科員の方々のご協力を得て行われた。
現存量の測定方法に関しては,当場造林科菊沢喜八郎氏,当場道北支場浅井達弘氏に数々の助言を受けた。
こうした方々に深く感謝する次第である。
カラマツ人工林の間伐試験(2)-8年間の林分構造の推移と林分生長量-(PDF:736KB)
佐々木信悦
P129~139
間伐は,林分の不健全化を防ぎ,主伐木の生長と形質向上により収益へのプラス効果をもち,かつ資源の有効活用を図ることであり,活力ある健全な林分の育成には欠かせないものである。
1971年新得町有林内に経営タイプ別に間伐方法を想定し,間伐試験林を設定した。1971年第1回間伐後5年間の生長経過については既に報告している(阿部ら,1980)。
ここでは1976年第2回間伐後3年間,試験林設定後8年間の林分構造および生長量の推移について報告する。
なお,試験地の提供,管理,調査にご協力頂いた新得町役場の関係各位に深く感謝する。
道北地方の針広混交林におけるトドマツ天然下種更新の実態(PDF:756KB)
水井憲雄
P141~149
道北地方の森林は過去における山火事や過伐によって林相が悪化し,人工造林が進められてきたものの気象条件がきびしいために成林しにくいところが多い(青柳,1976;菊地ら,1979)。このような地域の森林造成には現存する林分を有効に活用することが望ましい。後継樹を確保する一つの方法として天然下種更新が期待される。
トドマツ後継樹の確保を天然力に求める場合,まず,その林分にすでに生育している幼稚樹の実態を把握し,本数,分布状態,稚樹齢などが後継樹として十分であると判断されれば,それらの育成を考慮した施業が主体になる。しかし,不十分な場合は稚苗発生を促し,さらに発生した稚苗の定着をはからなければならない。
トドマツの天然下種更新については古くから多くの調査・研究があり,柳沢(1971)によってまとめられている。しかしながら,多くの林分では地表かき起しなどを行っても稚苗が発生しなかったり,発生したとしてもいつのまにか消失するなど,なかなか定着するにいたらない。天然下種更新は稚苗発生から定着までに未解決な点が多くいまだに技術として確立されていない。天然下種更新を技術化するための課題として,天然下種更新にかかわる諸因子を詳しく解析し,それを基礎として更新に有利な環境の造成があげられる。
ここでは,道北地方の天然生針広混交林二箇所において,すでに生育している稚樹の実態を調べ後継樹としての適否を検討した。また,天然下種更新の稚苗発生を左右する種子落下量と発芽床について検討した。
調査地の提供を快くお引受け下さった西尾木材株式会社,菊地直義社長に,また,調査にご協力をいただいた道有林美深林務署音威子府支署,宗谷支庁南部地区林業指導事務所の方々に深く感謝の意を表する,なお,当場道北支場ならびに造林科の方々には貴重なご助言をいただいた。深く感謝の意を表する。
北海道における山腹植生工法の研究(1)-道南・道央地域での既施工地の実態-(PDF:1.17MB)
新村義昭・伊藤重右ヱ門・成田俊司・清水 一
P151~177
北海道の民有林治山事業は1948年に開始され,その歴史はわずか30余年であって,1911年(明治44年)からの第1期治水事業以来継続されている本州のそれに比べると,非常に浅い。この間,北海道と気象条件が類似した東北地方では,1919年(大正9年)から1964年(昭和39年)までの45年間に実施された治山事業施工斜面に対して,技術的変遷,数量的実績,各施工地ごとの荒廃前の地林況,荒廃の素誘因,施工法,施工時施工後の処置などについて総合調査が行われ,歴史的な分析と技術指針が示されている(村井ら,1965)。しかし,北海道においては,これまでこれに類似した研究は行われておらず,見るべき成果はない。
筆者らは,1967年から山腹植生工に関する研究を展開してきた。これらは,木本導入の基礎研究である樹種の選定法,育苗法,植栽法そして植栽試験などからなっている(伊藤ら,1971;新村ら,1979;伊藤,1980)。これら一連の研究の結果から,筆者らは木本導入法それ自体については技術的にすでに解決済みであるという認識が可能となったと考えている。
本研究の第一の目的は,北海道の山腹植生工施工地を多面的な観点から調査し,山腹植生工施工地の実態を把握し,現状を分析することによって,これまでとられてきた工種,工法の適否,植栽樹種ごとの生長の良否,侵入植生の種と量,土壌化の必要年数などを明らかにすることにある。そして,終局的には,この調査結果を用いて,地理的,気象的,地質的などの因子からなる立地区分の組み合せに従って,よりきめの細い,各地域に見合った山腹植生工の技術指針を提案することを目的としている。
ここでは特に実態を詳細に述べることによって,山腹植生工の施工法を評価し,問題点を提示することに力点を置いた。また調査地の区分は,道南地域では特異な施工地である海岸段丘斜面のみ立地的に区分し,他は固有名称を用いた。一方,道央地域ではズリ斜面,渓岸などの立地的特徴が強くみられたため,分類方法もそのような特徴をあらわす方法を用いて論述することとした。
本論を述べるにあたり,現地調査に御協力下さった道治山課,関係支庁・林務署の治山係の各位に感謝の意を表します。
ナナカマドのレウコストマ胴枯病(PDF:470KB)
秋本正信
P179~185
ナナカマドは北海道における主要緑化樹木の一つとして,道内各地に広く植栽されているが,銅枯および枝枯症状を呈して衰弱,枯死するものも少なくない。これらの枯死枝幹上には,通常,Leucostoma massariana(DE NOT.)HOHN.あるいは Leucostoma persoonii(NIT.)HOHN.が認められる。また,これらの菌は,生きた枝幹上に明瞭な病斑を形成している場合がある。このことから,ナナカマドの胴枯および枝枯は,これらの Lecostoma 属菌に起因するものが多いと考えられる。
L. massariana は Sorbus 属樹木に生じ(KERN,1957),本邦では,ナナカマド上でのみ記載されている(KOBAYASHI,1970)。本菌は一般に病原菌とみなされていない。一方,L. persoonii は,モモ,スモモ,アンズ,ミザクラ類など多くの Prunus 属樹木に寄生する病原菌として知られている(日本植物病理学会,1965)。とくに,モモの胴枯病菌として著名で,その病原性についてはTOGASHI(1931)の詳細な報告がある。本菌はナナカマド,ハンノキ類およびアブラギリ上にも見いだされている(KOBAYASHI,1970)。
このように,ナナカマドに上記2種の Leucostoma 属菌が生じることはすでに知られている。また,小口(1975)は,ナナカマドにはこれらの Leucostoma 属菌による被害が多いとしてこれをレウコストマ胴枯病と仮称した。しかし,ナナカマドに対するこれらの病原性は,まだ確認されていない。
今回,接種試験により,L. massariana および L. persoonii のナナカマドに対する病原性が確かめられ,ナナカマドの胴枯および枝枯症状が,これらの Leucostoma 属菌による病害であることが明らかになった。ここでは,接種試験の結果,病原菌の2,3の生理的性質について述べる。
北海道におけるLachnellula属菌の種とその形態,生理,病原性に関する研究(英文)(PDF:1.51MB)
小口健夫
P187~246
戦後,森林の復興のために北海道では,人工林の造成にあたり,トドマツ,カラマツの植栽のほかに多くの外国樹種も導入植栽され,人工林面積,植栽樹種とも急増した。このため各種の病害もふえ,Lachnellula 属菌によるがんしゅ病の発生もまた増加した。本論文でとりあつかった Lachnellula 属菌はヨーロッパでは19世紀初頭から,とくにカラマツがんしゅ病菌として Lachnellula willkommii が注目されてきた。我が国では1957年に長野県八ケ岳山麓のカラマツ林でこの菌が発見された。その後の調査で富士山,浅間山,八ケ岳山麓のカラマツ人工林,天然林でこの病害による激害林分が発見された。北海道では Trichoscyphella calycina(Lachnellula calyciformis)によるがんしゅ病が各地で恒常的にトドマソ幼齢林を加害している。さらに近年になって,ストローブマツ,ハイマツにマツ類がんしゅ病が発見された。Lachnellula によるがんしゅ病は高緯度地方,高海抜地に発生が多いため,我が国の高緯度地域を占める北海道では,今後,人工林め奥地化にともない Lachnellula 属菌によるがんしゅ病の多発が憂慮される。
本論文は道内各地からえた Lachnellula 属菌の形態,生理的性質,病原性を明らかにしようとするものであり,あわせて現在多発しているマツ類がんしゅ病被害地の分布,発生について考察を加えたものである。