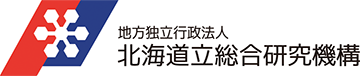北海道林業試験場研究報告-第46号-
PDFファイルで閲覧ができます
バックナンバー
第46号(平成21年3月発行)
目次ごとにダウンロード
防風林の防風防雪機能と気象害に関する研究(PDF:9.03MB)
鳥田宏行
P1~51
本論文では,防風林の防風防雪効果を定量的に把握し,森林の公益的機能の高度発揮と風害・雪氷害を軽減する森林整備技術の向上に資するため,森林と気象現象(風,雪氷)間の相互作用を解明することを目的とする。森林の公益的機能の高度発揮に関しては,主に防風林の防風防雪効果と林帯構造の関係を解明するため,樹林帯模型を用いたモデル風洞実験や野外観測を実施した。その結果,幹枝葉面積密度Adと林帯幅Wの積であるW・Adは,相対最小風速(防風効果による最小風速),最小風速の風下林縁からの距離,防風範囲と相関があり,W・Adは,防風林の防風効果を予測する重要な指標となりうることが示された。また,防雪効果としては,風洞吹雪実験(モデル)と野外観測(プロトタイプ)の結果を既存の相似則を用いて比較検討した結果,風速および吹雪時間に関する適合性の高い相似則が選定された。
強風害の軽減に関する研究では,防風林の気象害(風・雪氷)と森林の構造および樹形との関係を解明するため,2002年台風21号により北海道東部の十勝地方に発生した風害や2004年の北海道日高町に発生した雨氷害のデータに基づく被害要因解析(数量化Ⅰ類)や力学モデルを用いたシミュレーションを実施した。風害に関する要因解析結果からは,十勝地方の防風林における耐風性の高い樹種や被害を受けやすい配置などが明らかにされた。耐風性の高い樹種としてはカシワが,逆に耐風性が低い樹種としては,シラカンバ,チョウセンゴヨウマツ,ストローブマツが挙げられる。また,林分単位の被害予測として,数量化Ⅰ類(被害率)および数量化Ⅱ類(被害発生の有無)による被害予測式を構築した。雪氷害に関しては,被害要因の解析(数量化Ⅰ類)を行って,更に軽害林分と激害林分の林況を比較し,樹高成長段階毎に林分の限界形状比(被害が発生するか否かの境界を示す形状比(胸高直径/樹高))が求められた。力学モデルを用いたシミュレーションは,十勝地方において防風林造成面積全体の6割から7割を占めるカラマツ林を対象に実施し,樹高と形状比が耐風性に及ぼす影響が明らかとなった。また,シミュレーションの確度を検証するため,実際の被害データとシミュレーション結果を比較したところ,高い適合性が確かめられた。
結論として,防風効果と耐風性の両方を考慮した防風林の姿を,樹高成長段階毎に整理し,適正な本数密度を表に示した。
ブナにおけるマスティングの適応的意義とそのメカニズム(PDF:2.17MB)
今 博計
P53~83
多くの植物では,花や種子の生産数が空間的に同調しながら大きく年変動する。本研究では,マスティングとよばれるこの現象がなぜ生じるのかを明らかにするため,北海道南西部のブナ林で種子生産の年変動を調べ,マスティングの究極要因と至近要因を検討した。
種子散布前の段階の種子食性昆虫相を把握するため,ガルトネル・ブナ林において,ブナ種子の落下量と品質を2000年から2002年までの3年間にわたって調べた。4種類の鱗翅目昆虫と1種類の双翅目昆虫がブナ種子を摂食していることが確認された。そのうち主要な種子捕食者は,葉食性昆虫のナナスジナミシャクと種子食スペシャリストのブナヒメシンクイの2種であった。ナナスジナミシャクの食害は春先の短い時期に限られていた。一方,ブナヒメシンクイの食害を受けた種子の落下は6月に始まり11月まで続いていた。これら2種による食害の割合は,虫害全体の85%以上を占めていた。
ブナにおけるマスティングの究極要因の解明のため,5カ所のブナ天然林において調査された13年間のブナの開花・結実データに対して,受粉効率仮説と種子捕食者飽食仮説の検証を行うとともに,変動主要因分析とシミュレーションモデルという2つの異なる方法を用いて,受粉効率の向上と種子捕食者からの回避のメリットを統一的に評価し,選択圧の強さの比較検証を行った。当年の開花数と受粉失敗率との間,および,開花数の前年比(当年の開花量/前年の開花量)と種子散布前の虫害率との間には,それぞれ負の相関があり,受粉効率仮説と種子捕食者飽食仮説をともに支持する結果を得た。しかし,ブナの繁殖成功(開花した雌花が充実種子に至る生存率)の変動に対する受粉失敗と種子捕食の相対的重要性を検討した変動主要因分析では,繁殖成功の変動は受粉失敗よりも種子捕食による死亡により強い影響を受けていることを示していた。また,毎年一定量が開花した場合に比べ開花量が変動することにより,どのように種子の受粉失敗率,虫害率,結果率が変化するのかを調べた,シミュレーションモデルでは,現実のブナ林で生じている開花数の年変動の大きさが,散布前の種子捕食を回避し繁殖成功度を高めるのに最適な状態にあることを示していた。したがって,ブナにおけるマスティングは種子捕食を回避し繁殖成功度をあげるために進化した現象であると考えられた。
ブナにおけるマスティングの至近要因の解明のため,5カ所のブナ天然林において調査された13年間のブナの開花数データを,過去の繁殖量と気象条件に関連づけ解析した。マスティングへの資源動態の影響を検証した自己相関分析では,開花数と1年前の開花数との間に有意な負の相関があり,ブナの開花数の年変動が,体内の貯蔵資源量の変動によって引き起こされていることを示していた。開花数は開花前年の4月下旬~5月中旬の最低気温と高い負の相関があった。また,開花数と4月下旬~5月中旬の最低気温の関係からは,最低気温が平年値(1979~2000年の22年間の平均)より約1℃以上高いと開花が抑制されることを示していた。したがって,4月下旬~5月中旬の気温条件がブナの繁殖休止の合図になっていると考えられた。至近要因を検討した重回帰分析では,1年前の開花数と4月下旬から5月中旬の最低気温の2つの変数を組み込んだモデルが選択され,開花数の変動の57.1%~83.1%を説明した。したがって,体内の資源動態と気象の合図が,ブナのマスティングの至近要因であると考えられた。
4月下旬~5月中旬の最低気温がブナの花芽分化に及ぼす影響を検証するため,外気温より約2℃加温した袋を夜間だけブナの枝にかぶせる野外実験をおこなった。2001年の4月21日~5月20日(前半30日間),5月21日~6月19日(後半30日間),4月21日~6月19日(60日間)の夜間に加温処理をおこなった。雌花序の分化は前半30日間と後半30日間のいずれの処理によっても抑制された。しかし,ステップワイズのロジスティック回帰分析では,前半30日間の加温処理のオッズ比は後半30日間のオッズ比よりも非常に小さく,雌花序は前半30日間の加温処理に強い影響を受けていることを示していた。また,雄花序の分化も前半30日間の加温処理によって抑制されていた。したがって,ブナの花芽分化は開花前年の4月21日~5月20日の夜間の気温によって支配されていると考えられた。
高密度植栽されたエゾイタヤ,グイマツ,カシワの各保安林の密度管理方法に関する基礎的研究(PDF:5.11MB)
真坂一彦・佐藤 創・鳥田宏行・今 博計・明石信廣
P85~116
本研究では,エゾイタヤAcer pictum ssp. mono (Maxim.) Ohasi,グイマツLarix gmelinii var. japonica Pilger,そしてカシワQuercus dentata Thunb.の高密度植栽された若齢保安林を対象に間伐試験地を設定し,肥大成長や枝の枯上がりに対する間伐効果を検証した。間伐試験地は,エゾイタヤ林とグイマツ林については羽幌町天売に,カシワ林については釧路町音別に設定し,それぞれの林分に強度間伐区として本数伐採率にして50%~60%,弱度間伐区として25%~30%,そして間伐を施さない無間伐区を設けた。このとき,間伐方法は全層間伐を目標とした。いずれの林分も,強度間伐区は無間伐区に比べて間伐後6年間の肥大成長量(cm/6年)が有意に改善され,しかもBA増加率は弱度間伐区や無間伐区より高かった。また,調査期間中のBA合計(m2/ha)の推移や林冠閉鎖度(%)からは,間伐効果が今後も持続することが推察された。ところが弱度間伐区では,肥大成長の有意な改善や,高いBA増加率は認められなかったり,さらには期間中の死亡個体が多く,かつ,BA増加量(m2/ha)が無間伐区と同様に鈍化傾向にあったりと,強度間伐区と比較して間伐効果はきわめて小さかった。また,グイマツ林では枝の枯上がり高や形状比も調査を行ったが,弱度間伐区では無間伐区と有意な差は認められなかった。これらの結果は,既存の本数調整伐(25%~30%)では,たとえ全層間伐であったとしても間伐効果がほとんどないか,また認められたとしても持続期間が3年程度ときわめて短期間であることを強く示唆している。また,間伐に併せて採取した円板から年輪幅成長量の判読により,植栽後数年でサイズにはっきりとした優劣が表れていることが明らかになった。この結果から,生育環境の厳しさから植栽木が淘汰されて林冠が疎開している林分でなければ,比較的早い時期にサイズが小さい個体を中心にした強度間伐を提案できる可能性を示唆している。
自動撮影カメラで確認された北海道立林業試験場光珠内実験林における哺乳類相(PDF:1.66MB)
明石信廣・南野一博
P117~126
北海道立林業試験場光珠内実験林において,自動撮影カメラを用いて哺乳類相を調査した。2006年及び2007年の5月から11月の間に,2台のカメラを4箇所の調査地に交互に設置し,総撮影日数は536日であった。今回の調査方法では,エゾリス,エゾシマリス,キタキツネ,タヌキ,エゾヒグマ,クロテン,エゾシカの在来種7種及び外来種としてアライグマ1種の生息が確認された。ネズミ科及び翼手目も撮影されたが,写真による種の同定が困難であった。食痕や糞から,実験林内におけるエゾユキウサギの生息は確認されたが,撮影はされなかった。文献を基に北海道に生息するとされる哺乳類のリストを作成し,2006~2007年に実験林において確認された種を示した。
森林の多面的機能に関わる土壌・生物要因の林相間比較(Ⅰ)-表層土壌の理学性-(PDF:463KB)
中川昌彦・大野泰之・山田健四・八坂通泰・寺澤和彦
P127~136
森林の多面的機能に関わる土壌要因の林相間比較を行うため,同一の地質(第三紀砂岩・泥岩互層),気象条件,斜面方位に成立する林齢40~50年生の,ウダイカンバ二次林,ウダイカンバ人工林,カラマツ人工林,トドマツ人工林およびトウヒ類人工林の計5林分において,土壌断面の記載と表層土壌の理学性の調査を行った。
A0層の量は,ウダイカンバ人工林で少なく,カラマツ人工林とトウヒ類人工林で多かった。A層はカラマツ人工林とトウヒ類人工林で薄く,A層の構造は,トウヒ類人工林で粒状,それ以外では塊状となっていた。
最小容気量には,林相間での有意な違いはみられなかった。最大容水量,全孔隙率,粗孔隙率,細孔隙率,成長有効水分率,全有効水分率については,主としてトドマツ人工林で他の林分よりも有意に高かった以外には,林相による違いはほとんどみられなかった。
これらの結果から,第三紀砂岩・泥岩互層を母材とする土壌の広葉樹二次林で林相転換を行った場合,トウヒ類人工林で土壌構造が乾燥している林地でよく見られる粒状に変化し,トウヒ類人工林やカラマツ人工林でA層の発達が抑制され,またトドマツ人工林で最大容水量,粗孔隙率,細孔隙率および成長有効水分率が高くなる可能性が示唆された。しかしそれ以外については,40~50年という期間では土壌の理学性が大きく変化する可能性は小さいと考えられた。
森林の多面的機能に関わる土壌・生物要因の林相間比較(Ⅱ)-下層植生-(PDF:511KB)
中川昌彦・大野泰之・山田健四・長坂 有・八坂通泰
P137~144
ウダイカンバ二次林,ウダイカンバ,カラマツ,トドマツおよびトウヒ類の人工林において,5月上旬,7月上旬,9月上旬に下層植生の調査を,また8月下旬に相対光合成有効光量子束密度の調査を行った。出現種数は,トドマツ人工林で最も多く,以下カラマツ人工林,トウヒ類人工林,ウダイカンバ人工林の順となり,ウダイカンバ二次林で最も少なかった。トドマツ人工林やウダイカンバ人工林では林外種も見られたものの,出現種のほとんどは林内種であり,外来種は見られなかった。ウダイカンバ二次林,ウダイカンバ人工林およびカラマツ人工林ではクマイザサが優占していた。下層植生全体の被度は,トドマツ人工林においては5月上旬では低かったものの,7月上旬や9月上旬では5林分中で最も高かった。一方,トウヒ類人工林では観察期間中を通じて被度が低かった。相対光合成有効光量子束密度は,ウダイカンバ人工林で最も高く,カラマツ人工林,トドマツ人工林,ウダイカンバ二次林,トウヒ類人工林の順に減少した。種の多様度指数は,トドマツ人工林で最も高く,次にカラマツ人工林で高く,トウヒ類人工林で最も低かった。
下層にクマイザサが優占する広葉樹二次林において人工林を造成した場合,低密度のウダイカンバ人工林を造成しても下層植生の多様性はそれほど高くならないが,カラマツを植栽するか,または常緑針葉樹を植栽しても林床に到達する光を確保することで,下層植生の多様性が高くなるものと考えられる。
森林の多面的機能に関わる土壌・生物要因の林相間比較(Ⅲ)-小型哺乳類-(PDF:1.43MB)
南野一博・明石信廣
P145~151
北海道立林業試験場光珠内実験林の林相の異なる10林分において小型哺乳類の生息調査を行った。調査は6月,8月及び10月の計3回,1回の調査は3日間連続で行った。各調査地において10 m間隔で5行5列の格子状にわな位置を定め,1ヶ所につき2個,合計50個のパンチュートラップを配置した。調査の結果,のべわな数4500トラップナイトに対しネズミ科4種,トガリネズミ科2種の合計354頭が捕獲された。全ての林分でヒメネズミが優占しており,全捕獲数の66.1 %を占めていた。また,環境省のレッドリストで準絶滅危惧種(NT),北海道レッドリストでは希少種(R)に指定されているムクゲネズミが6林分で捕獲された。林相間で種構成に明瞭な違いはみられなかったが,常緑針葉樹林におけるネズミ科の生息密度は,落葉広葉樹林や落葉針葉樹林と比較して有意に低く,下層植生の乏しい林分ではネズミ科の生息数が少なくなることが示唆された。
森林の多面的機能に関わる土壌・生物要因の林相間比較(Ⅳ)-昆虫,地表性オサムシ科-(PDF:390KB)
原 秀穂
P153~156
地表性オサムシ科の捕獲トラップとして生け捕りトラップとプロピレングリコールを入れた溺死トラップとで捕獲種構成と捕獲数とを比較した。設置から2週間後では捕獲種数はともに7種と違いはなく,捕獲された種も同じであった。捕獲個体数はオサムシ亜科では生け捕りトラップの方が多かった。生け捕りトラップにおける捕獲個体の死亡率は設置から2週間後では極めて低かったが,3週間後には大幅に増加した。
ウダイカンバ二次林,ウダイカンバ人工林,カラマツ人工林,トドマツ人工林,トウヒ類人工林で地表性オサムシ科の種数,個体数を比較した。全体で9種捕獲され,ウダイカンバ二次林が最多の7種,トウヒ類人工林が最少の3種であった。総捕獲個体数はトウヒ類人工林で少なかったが,種により林分と捕獲数との関係は異なる傾向が示された。
森林の多面的機能に関わる土壌・生物要因の林相間比較(Ⅴ)-土壌動物-(PDF:838KB)
尾崎浩司・中川昌彦・長坂 有
P157~161
森林の多面的機能に関わる土壌動物相の林相間比較を行うため,ウダイカンバ二次林,ウダイカンバ人工林,カラマツ林,トドマツ林およびトウヒ類人工林において,6月,8月,10月に土壌動物の調査を行った。
大型土壌動物の分類群数は,トウヒ類人工林では少なく,他の4林分では大きな差は見られなかった。サンプルによるばらつきが極端に大きかったアリ(膜翅目)を除外した場合の個体数はウダイカンバ二次林が最も多く,以下ウダイカンバ人工林,カラマツ人工林,トドマツ人工林,トウヒ類人工林の順であった。トウヒ類人工林においては,リター食性の大型土壌動物がほとんど見られなかった。小型土壌動物の分類群数は,トウヒ類人工林でやや少なく,他の4林分ではほぼ同じであった。個体数は,いずれの林分においてもトビムシとダニが大部分を占めており,トウヒ類人工林においては特にその傾向が顕著だった。土壌動物を用いた「自然の豊かさの指数」は,トウヒ類人工林では低く,他の4林分では大きな差は見られなかった。トウヒ類人工林での土壌動物相の貧弱さは,林床植生の貧弱さと関係していることが示唆された。
これらの結果から,ウダイカンバ二次林において人工林を造成した場合,低密度のウダイカンバやカラマツの人工林では土壌動物相はそれほど貧化せず,常緑針葉樹を植栽した際にも適切な施業によって林床植生を豊かにすることで,土壌動物の多様性を維持することが可能であると考えられた。